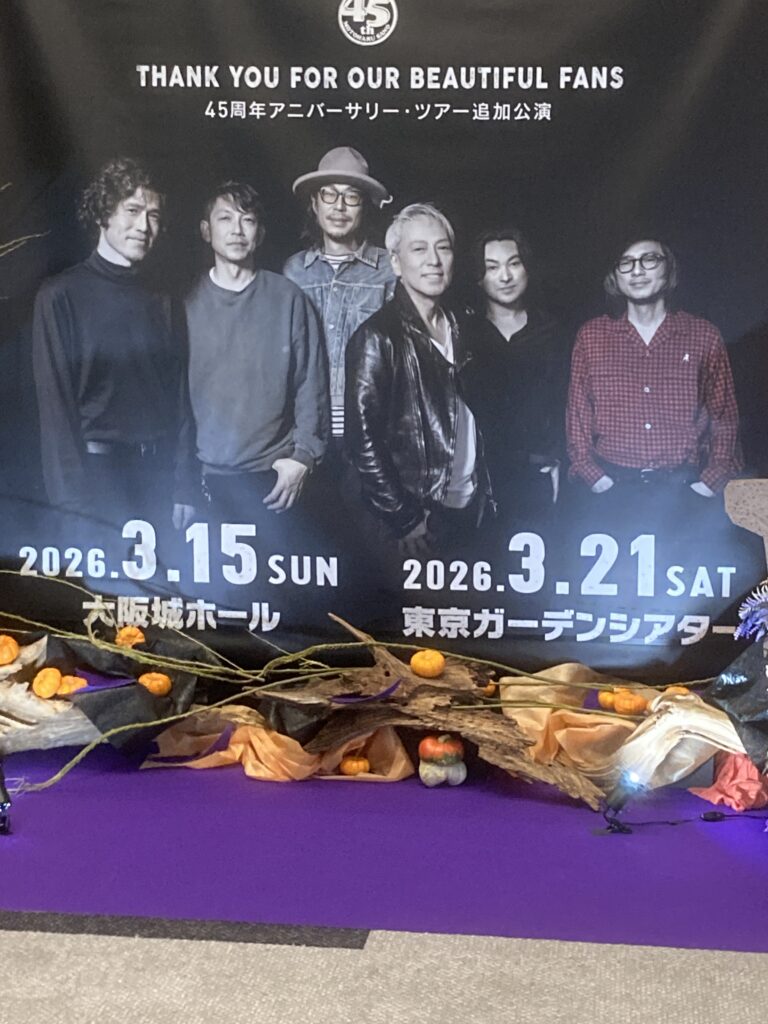




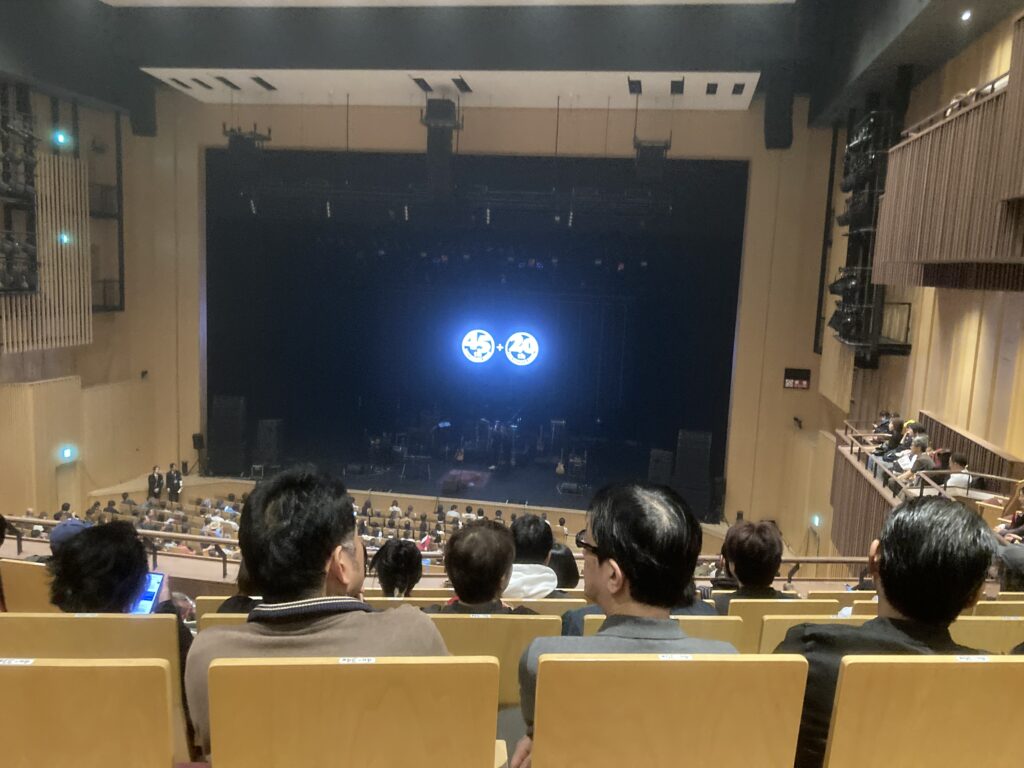
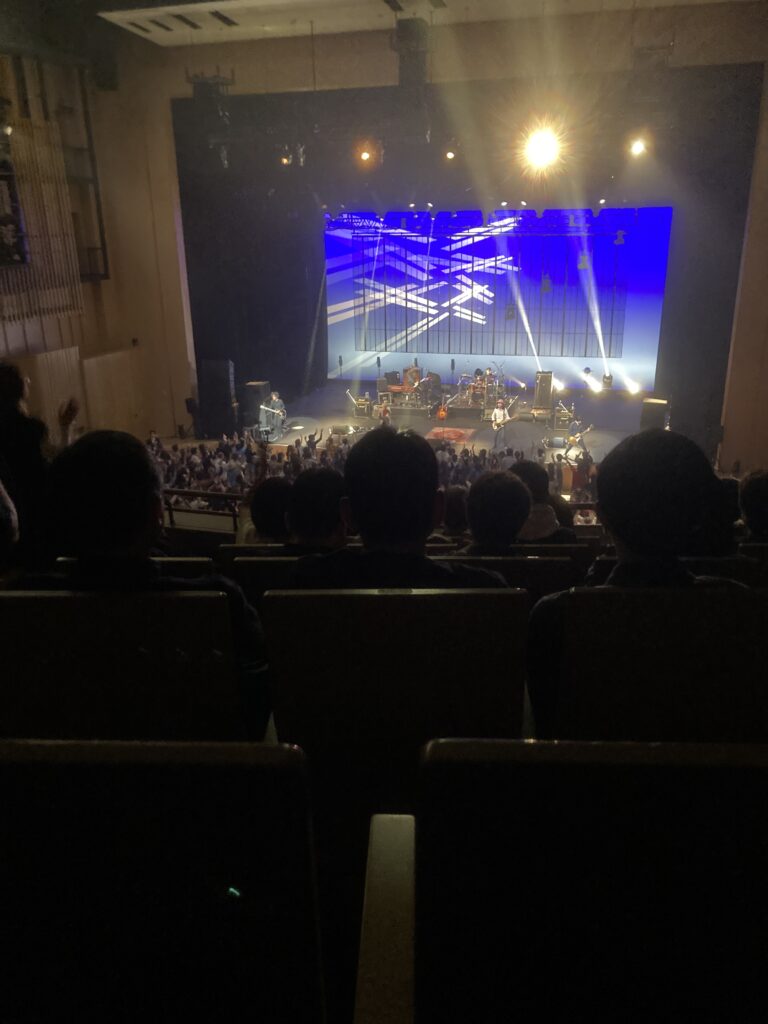
佐野元春が45周年、コヨーテバンドが20周年を迎え、全国ツアーが始まった。
私はこれまでにも20周年の武道館公演、25周年のライブと、節目ごとに彼のステージを見てきた。
マスメディアに姿を見せる機会が減っても、ライブには変わらずファンが集う。
それが、いつも不思議で、そして嬉しい。
今回もその通りだった。最近まで活動の様子をあまり知らなかったが、懐かしい曲を新たなアレンジで聴けるということで、久しぶりに胸が高鳴った。
会場には、やはり年月を重ねたファンが多く、互いにその“時間の重み”を感じ合うような空気があった。
■ 開演前の映像が語る、音楽の歴史
佐野が登場する前、スクリーンにはこれまでのアルバムの映像が流れた。
ポエトリーリーディングに曲を乗せた独特の世界観。
その映像が、彼の歩んできた音楽の道を静かに物語る。
「映像とズレている」との声も聞こえたが、私にはむしろ、そのわずかなズレさえも“生きてきた証”のように思えた。
舞台に上がる前から、すでに彼の“物語”が始まっていた。
■ 観客と共に呼吸するライブ
2階席から見下ろすステージ。
仕事帰りで少し疲れていた私は、「今日は座って聴きたい」と思っていた。
幸いにも、前の3列が座ったままで、私も腰を下ろして音に身を委ねることができた。
遠くからでも、音楽は十分に届く。
ライブには“その場で出会って好きになる曲”がある。
だから私は、コンサートは後方からでいいと思っている。
観客の多くは立ち上がっていたが、年齢を重ねたファンも多く、座って静かに聴く姿も目立った。
佐野は30曲を歌いきり、体力的な変化を感じさせつつも、歌を「諭すように」届けるスタイルへと進化していた。
立川で25歳の頃に観た彼は、終始動き回り、若さそのものの躍動感に満ちていた。
それが今、言葉を噛みしめるような、成熟したステージへと変わっている。
■ 映像表現の進化と「今を生きる」姿勢
今回のステージでは、映像が効果的に使われていた。
私は最近、大阪万博で最新映像技術の展示を見てきたばかりだったので、その映像演出に驚いた。
AIを活用したと思われる映像もあり、これまでの“言葉と音楽”という軸に、“視覚の物語”が加わっていた。
それは単なるノスタルジーではなく、**「今も第一線で表現する意思」**の表れだった。
一部には「映像に集中して音が入ってこない」という声もあったが、私はむしろ、五感で楽しむ総合芸術だと感じた。
嫌なことを忘れ、夢のような世界に浸れる――それこそがエンターテインメントなのだ。
■ 『愛が分母』に見た“いま”の熱量
今回、私が新たに惹かれたのは『愛が分母』。
YouTubeではそこまで響かなかったこの曲が、ライブでは魔法のように輝いた。
佐野が手で和を描き、観客全員が“Say Yeah”と声を合わせる。
その瞬間、ステージと観客が完全にひとつになる幸福感が生まれた。
■ 前半と後半――若さと成熟のあいだで
他のファンのブログでは「前半のほうが良かった」と書かれていたが、私も同感だった。
若い頃に書かれた曲は、やはり直感的に響く。
ここ10年で、これほど気分が高揚したのは、万博とこのコンサートくらいかもしれない。
後半では『君の大事な魂』や『斜陽』など、夕暮れのような哀愁を帯びた“大人のロック”が続いた。
悪くないが、いまの自分の心境とは少し距離があった。
■ 歳を重ねたファンとしての視点
『悲しきレディオ』の「ムード盛り上げれば~」の部分を全員で合唱したとき、私は不思議な感動を覚えた。
若い頃は何かにつけて批判的だった自分が、いまは人の創作に無条件の敬意を抱くようになっている。
これは、歳を重ねることの喜びなのかもしれない。
■ Sweet16と、円熟した自由
中間のインタビュー映像では、「1950年代の雪村いづみさんが好きだった」と語っていた。
無垢な女性への憧れ――その感性が、佐野らしいと思った。
そして『Sweet16Blues』。
「バディ・ホリーのような軽い歌を作りたくて、やっとできた」と語る彼の笑顔が印象的だった。
かつてのように“音で勝負”という硬派な姿勢ではなく、いまは何でもやる。
AI映像も取り入れる。
まるくなったというより、自由になったのだと思う。
■ 最後の言葉に込めた“継続する意志”
終演前、彼は少し言葉を探しながら、こう語った。
「突然渡米したり、変な歌を作ったりもしてきたけれど、自由に歌を作れたことは恵まれていた。
最近は情勢が良くないけれど、これからも自由に歌を作っていきたい。
今日、みなさんといられてとても心強い。ノスタルジーではなく、最前線でやっていきます。」
そして、名曲『Someday』のあとに『明日の誓い』を歌った。
その選曲に、まだ衰えぬ作家魂を感じた。
「彼がいたから頑張れた」――そう思う人が、この渋谷の夜には何人もいたことだろう。
私もその一人だ。
大きな声で彼と一緒に歌いながら、“同じ時を共有できた”喜びに包まれた。
■ 灰色の都市と、創作の10年サイクル
『ニューエイジ』では、灰色の都市の映像が流れ、人の姿がない。
この孤独感――まさに私が長年この歌から感じ取っていた世界そのものだった。
最新技術が、その感情を可視化してくれた瞬間だった。
人間は10年ごとに創作の種を出し尽くすのかもしれない。
『愛が分母』『純恋』『La Vita e Bella』『明日の誓い』――どれも良い曲だが、どこかで聴いたような既視感もある。
それは衰えではなく、一人の人間としての限界と成熟が共存している証なのだ。
結局、「いいものはいい」。
それで十分だと思う。
■ 終わりに――敬意という音楽
この夜、私は改めて思った。
若い頃は“自分はもっとできる”と、他者に厳しかった。
でも今は、人が精魂込めて作ったものに、ただ敬意を持つことができる。
佐野元春の45年は、私たちにそんな生き方を教えてくれている。
会場を出た後の渋谷の街↓











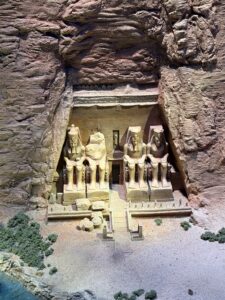


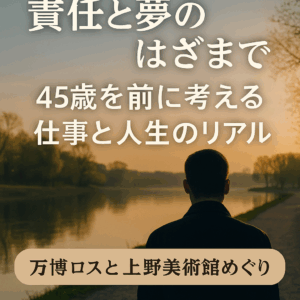
コメント