
殺人的な労働の日々と、心の叫び
気づけば、仕事の日々は「殺人的な忙しさ」が続いている。
最初は気合でなんとかしても、3か月経つと休みの日に全身が鉛のように重くなる。社会のシステムをもっと早く知っていれば…と思うが、私はただ「レールから外れること」が怖かった。そして情報もなかった。
生成AIcampで得た幸福と別れ
そんな私にとって救いだったのが、生成AIcamp。
AI界のカリスマ・オザケンさんと直に話せたことは「人生の幸福」の一つと言っていい。半年間は無料で学べたが、これからは課金制になるという。AIを仕事にするほどの覚悟は、今の私にはない。
だから今月で一区切り。画面越しに講義を聴きながら、不覚にも涙がこぼれそうになった。
戦後の日本人が問いを立てた時代
今朝の『映像の世紀』では、本田宗一郎やソニーの創業者たちが、焼け野原から世界に羽ばたいた物語が描かれていた。
彼らは「問いを立てて行動した人々」だった。手塚治虫、力道山、本田宗一郎――その背中に日本人は素直に従い、汗水を流して復興を支えた。
一方で、オザケンさんが言うように、現代の日本人は「自ら問いを立てる力」が弱い。AI時代にこそ求められるのは、この力だ。論理的整合性を欠くものには、誰も従わなくなる世の中が来るだろう。
ロスジェネ世代の嘆き
戦後を駆け抜けた世代、バブルを逃げ切った世代――その後を生きるロスジェネ世代の私は、ただ「割を食う世代」として残されている。
あと10年、20年。耐えきれるか分からない。でも、逃げることもできない。
万博と飛田新地、そして人間の本能
そんな私の小さな楽しみは、今月の大阪万博。
夜の宿泊先がなく、ふと「飛田新地に行ってみよう」と思い立ち、近くの東横インを予約した。翌朝はビュッフェを楽しみ、海遊館でゆっくりして帰る予定だ。
だが正直、四十路の体力で飛田新地に挑むなんて無謀だ。20代気取りは命を落とす――そう肝に銘じた。
本能の快楽は、理性をあっけなく吹き飛ばす。パビリオン予約に神経症のようになっていた自分も、飛田新地の存在を思い浮かべた瞬間、すべてを包み込まれてしまったのだ。
労働者の滑稽さを笑ってほしい
宿泊先探しに2時間、飛田新地に行くかで2時間――私は、万博に行くのにすら悩み続ける。
これは、普段のストレスから逃げたい心の表れかもしれない。
労働者は辛い。でももっと辛い人もいる。
もし、私のこの滑稽さを笑ってくれる人がいるなら、それが誰かの役に立つことになるのだろう。
そう思うと、不思議と少しだけ救われる。

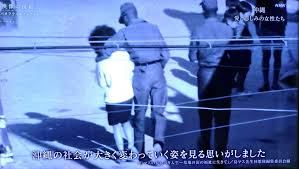







コメント