― 孤独と感動の狭間で、人類の美しさに触れた ―
大阪・関西万博の熱気がまだ身体に残っている。
あの大屋根リングの下で、世界中の人々が笑い、語り、優しくなれた――
そんな空間を失った喪失感、いわゆる“万博ロス”。
その代わりを探すように、私は上野へ向かった。
1日で5つの大型展覧会を巡る、ミニ・パビリオンツアー を決行したのだ。
- 東京国立博物館「運慶展」
- 国立科学博物館「大絶滅展」
- 東京都美術館「ゴッホ展」
- 上野の森美術館「正倉院展」
- 国立西洋美術館「印象派展」
歩きながら思ったのは、万博と上野の決定的な違い――
**“孤独”**だった。
■ 万博ロスとは何だったのか
万博の魅力は展示物以上に、
「世界は手を取り合える」
と感じられる空気だった。
大屋根リングの下では、知らない人同士が微笑み合い、
「人に優しくしたい」という感情が自然に湧き上がる。
宮沢賢治も、
“世界の人々と愛し合って歩きたい”
という理想を書いた。
恋とはそのミニチュアであり、平和のイデアだと。
万博は、まさにその理想が具現化した場所だった。
だから喪失感も大きい。
しかし、上野を歩きながら、私は別の形で“人類の美しさ”を見ていくことになる。
■ 国立西洋美術館「印象派展」
― 絵画の“生きた気配”に打たれた
ルノワール、ドガ、モネ。
教科書で見た名前が、目の前で息をしている。
● エルネスト・デュエズ《ランプを囲んで》

チェス盤を挟む中年紳士と若い女性。
ランプの周囲だけが眩しいほど明るく、
画面の端に向かうほど薄暗くなる。
静謐だが、どこかエロティック。
「こんな時間を一度でいいから過ごしてみたい」
そんな淡い憧れを掻き立てる。
● アルベール・バルトロメ《温室の中で》
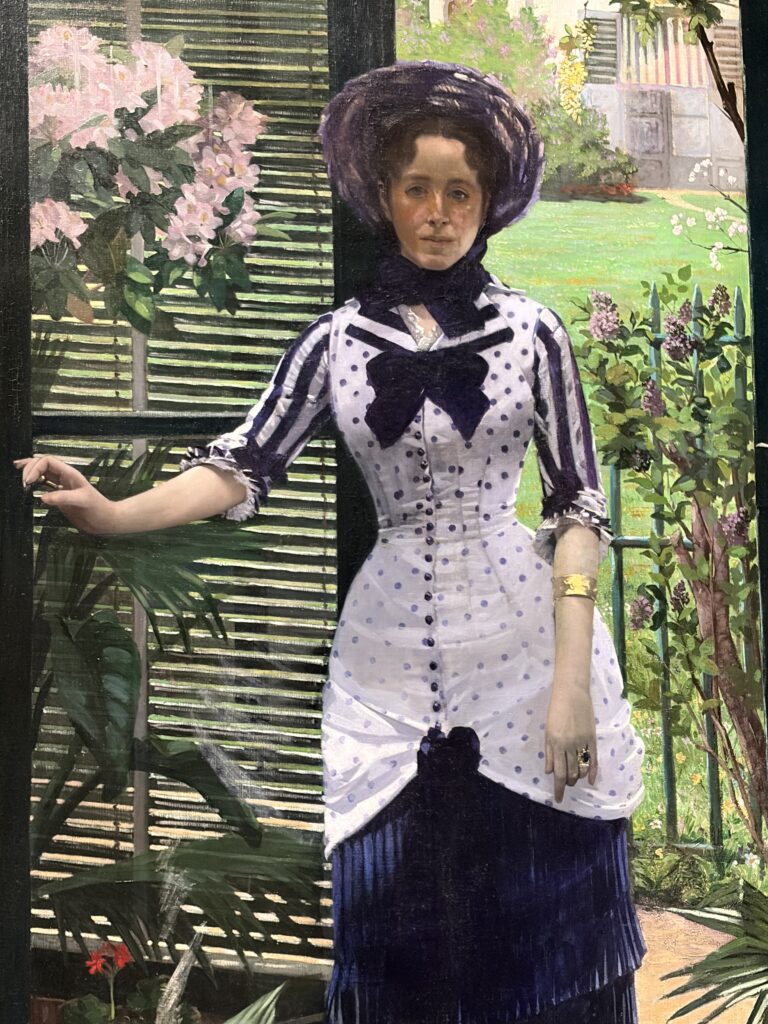



等身大の婦人がそこに“存在している”。
麦わら帽子をかぶった貴婦人が不安げにこちらを見つめる。
ネット画像では絶対に伝わらない生々しさだった。
絵画は時に、現実を超える。
それを痛感させられた展示だった。
■ 国立科学博物館「大絶滅展」
― 地球の“終わり”を覗き見る場所
ここは毎回、期待を裏切らない。
今回は地球規模の“死の歴史”に踏み込む、壮大な特別展だ。
● 巨大隕石が落下した瞬間の映像
恐竜の時代を終わらせた隕石衝突を、迫真の映像で描く。
映像なのに、まるでその場に立っているような感覚。
● 三葉虫アンピクスの“行列”
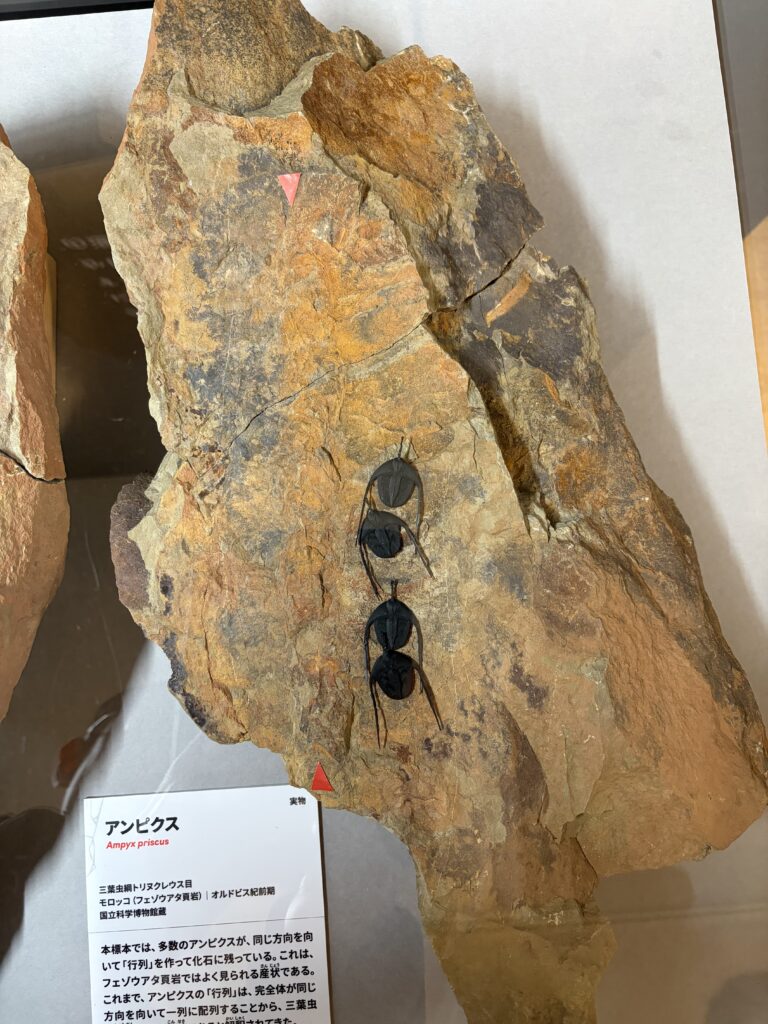
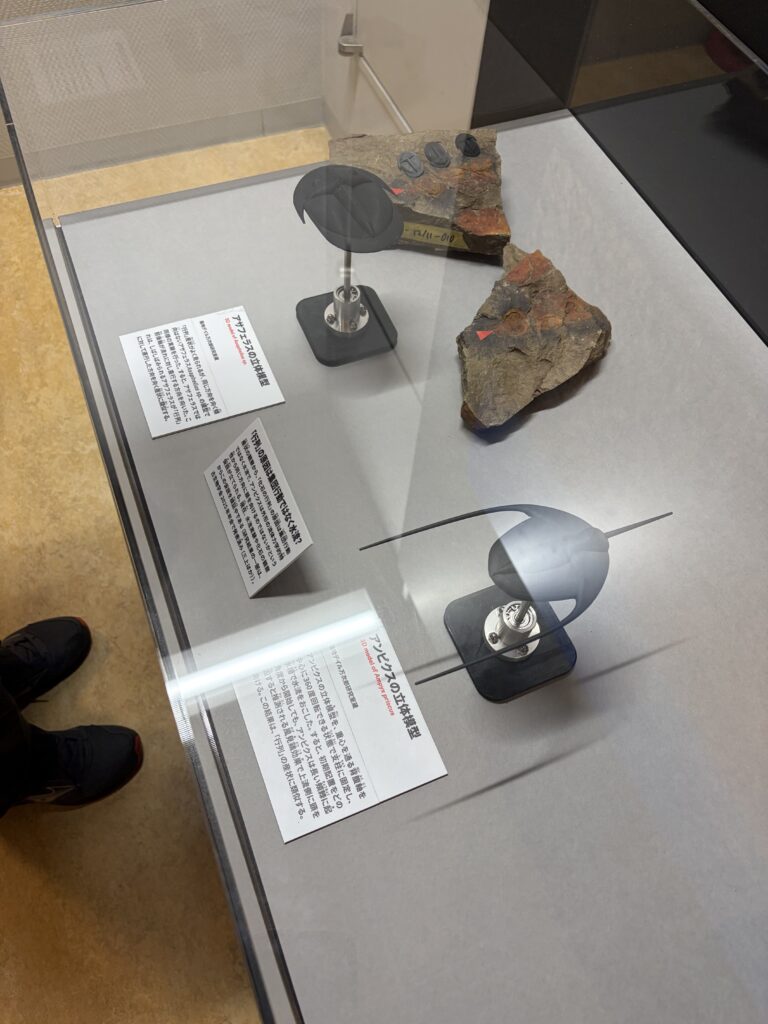
三匹が一列になって歩いた化石。
4億年前の生物が残した「習性」の痕跡。
生物の戦略が、昔も今も変わらないことに胸がざわつく。
● “夢中になる”人は幸福に見える


展示品を一枚ごとに丁寧に撮影する女性がいた。
京都の苔寺で苔を撮っていた人のことも思い出す。
夢中になれる対象を持つ人生は、それだけで美しい。
井上靖の言葉のように、
「何かに夢中になっているとき、人はもっとも幸福」
その意味がよくわかる光景だった。
■ 東京国立博物館「運慶展」
― 日本が誇る“圧倒的リアリズム”


金剛力士像の迫力は、実物を前にすると言葉を失うほどだ。
掲げた左手の仏具を眺める姿はまるでロビンフッド。
そこに宿るのは、運慶の圧倒的な創造性。
僧侶2体の穏やかな表情も素晴らしい。
情報が少なかった時代の“素朴なリアリズム”が、かえって心を掴む。
日本の彫刻は、人間に似ていないようでいて、
“何か”を宿している。
その距離感の神秘こそ、仏像の魅力なのだと再認識した。
■ 東京都美術館「ゴッホ展」
― 個性と闘いながら描いた“魂の筆跡”
小林秀雄は
「ゴッホの絵は美しいのではない。発作の避雷針だ」
と言った。
その意味が、会場の作品を前にするとよくわかる。
● 《オリーブ》

絵具の一筆一筆が叫んでいる。
筆致が荒々しく、色そのものが生命を持っているようだ。
「絵具はゴッホの血だ」とさえ思うほど強烈だった。
弟テオとその妻がいなければ、
この作品群は日の目を見なかった。
芸術は“支えてくれた人”によって守られる。
その事実にも胸を打たれた。
■ 上野の森美術館「正倉院展」
― 日本人の“根”を知る時間
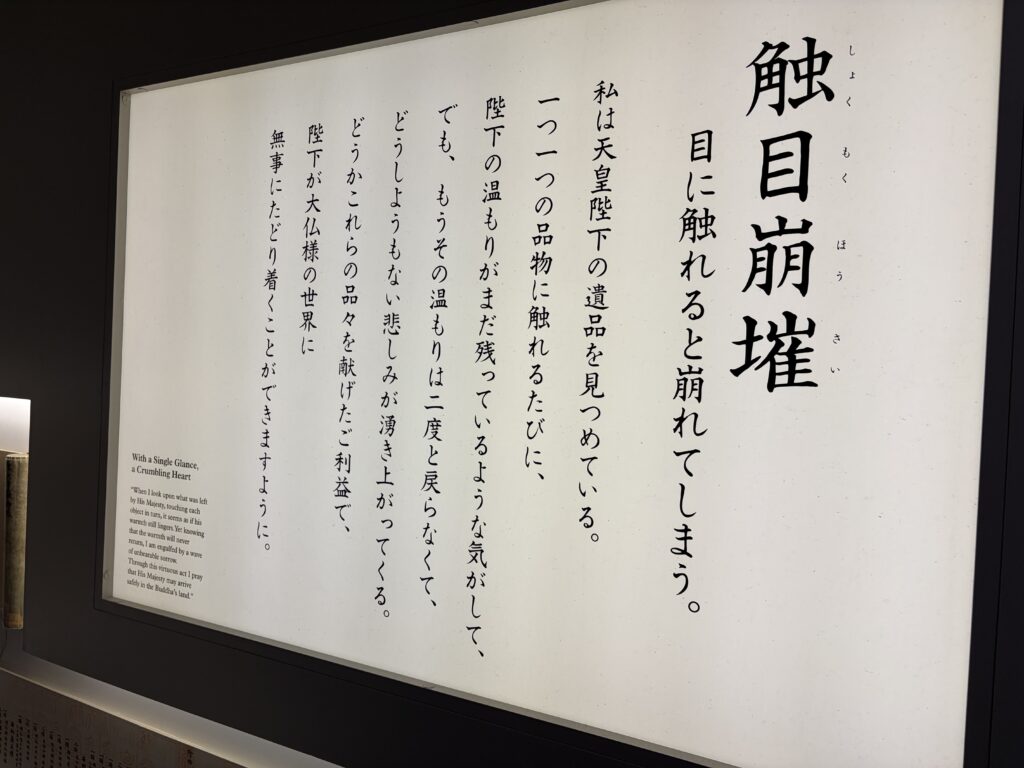



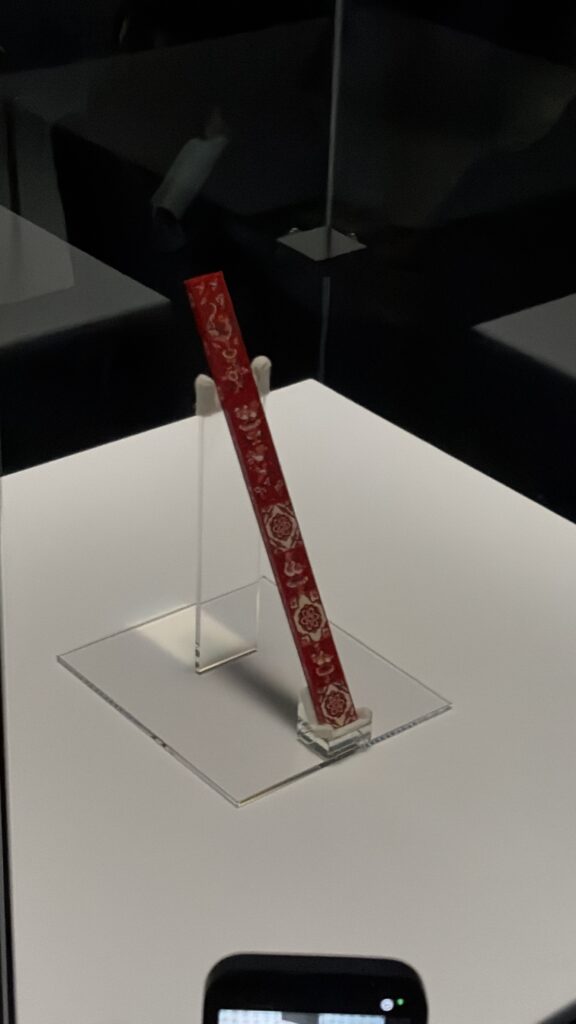
奈良の大仏建立と共に集められた宝物。
1300年の時を超えて、ほぼ無傷で残る奇跡。
● 蘭奢待

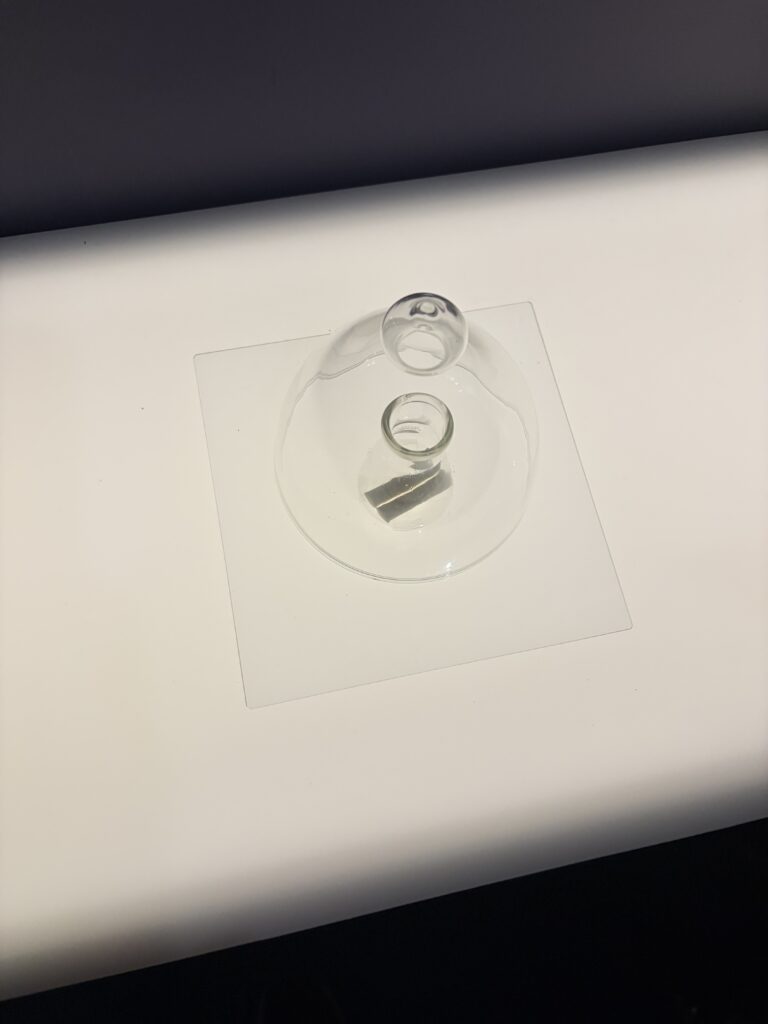
香りは、京都や奈良のお寺で漂う“あの匂い”。
甘酒のようで、どこか神聖。
信長がこれを切り取って持ち帰ったという逸話も、
香りが権威と結びつく歴史を語っていた。
楽器の音の体験コーナーは長蛇の列で断念。
それほど人々の関心を集める展示だった。
■ 上野を5つ巡ってわかったこと
― 孤独を深めたはずが、人類への信頼が少し戻った
万博で感じた 「世界は手を携えて歩ける」 という希望。
上野で感じた 「孤独だからこそ美を求める」 という真実。
そして気づいた。
芸術にも、世界平和のイデアは宿っている。
孤独を抱えながらも、
私たちは美を求め、誰かとつながろうとする。
その営みが“人類の尊さ”なのだろう。
上野の道を歩きながら、私は少し確信した。
まだ、世界は捨てたものじゃない。
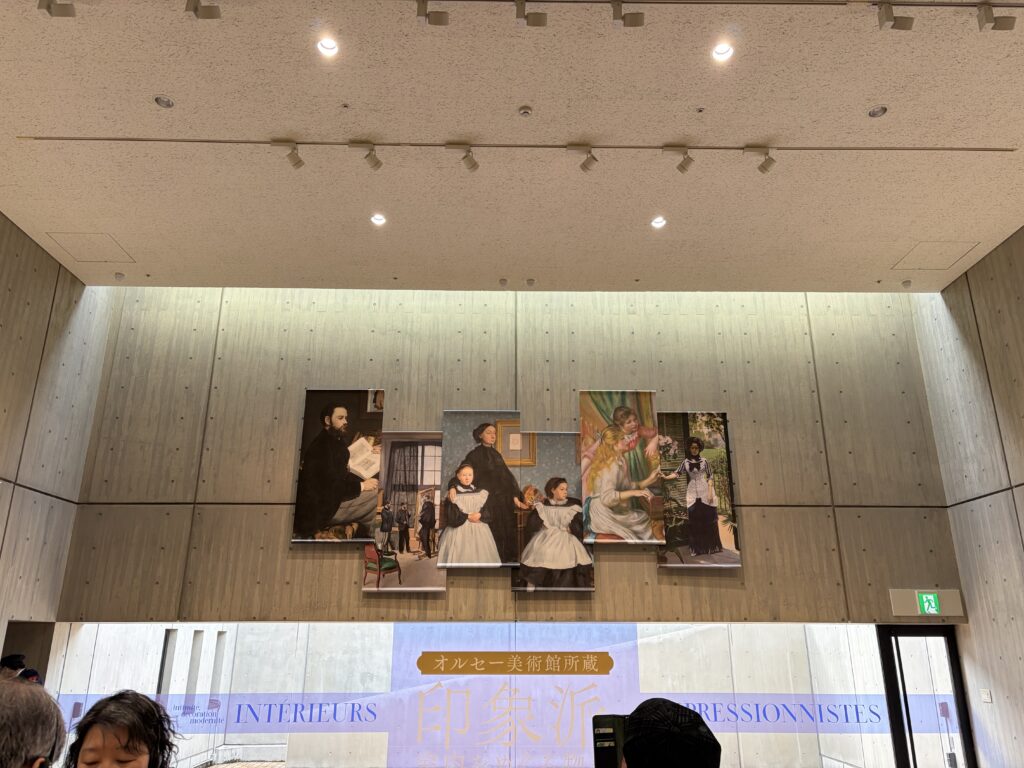


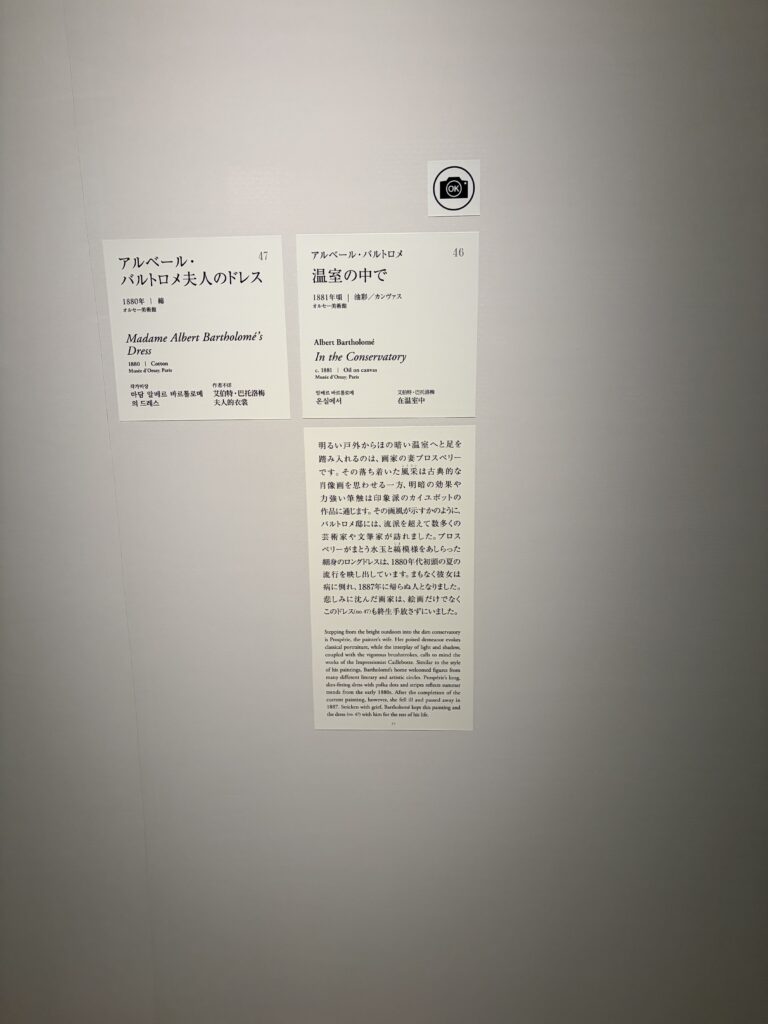





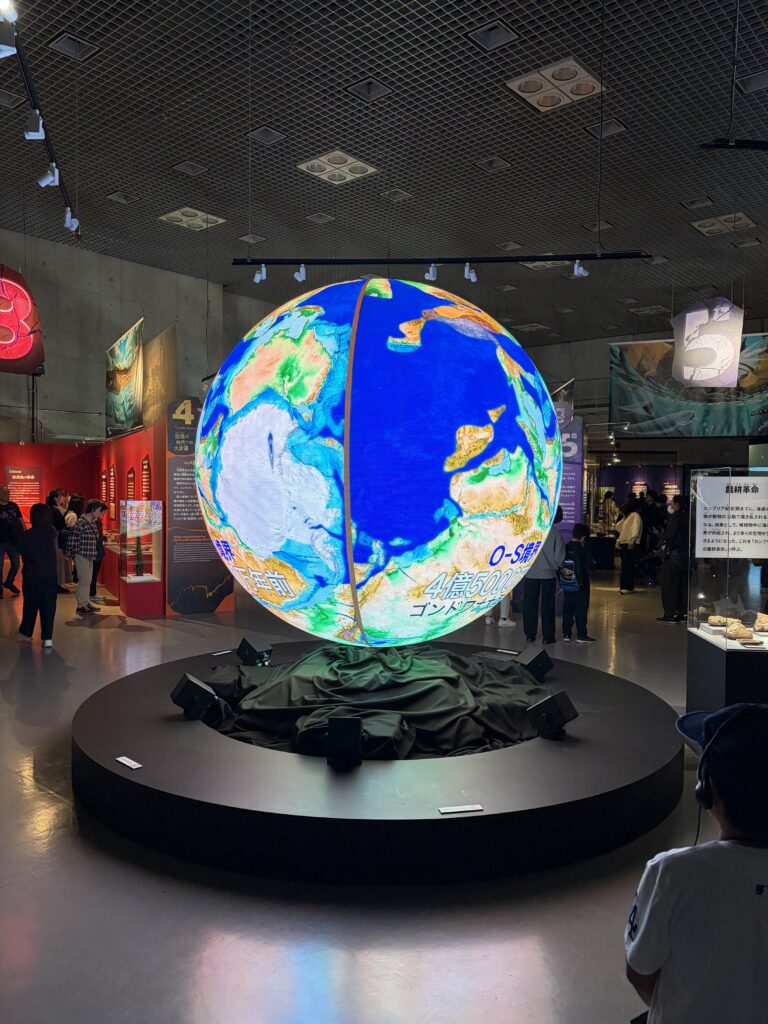

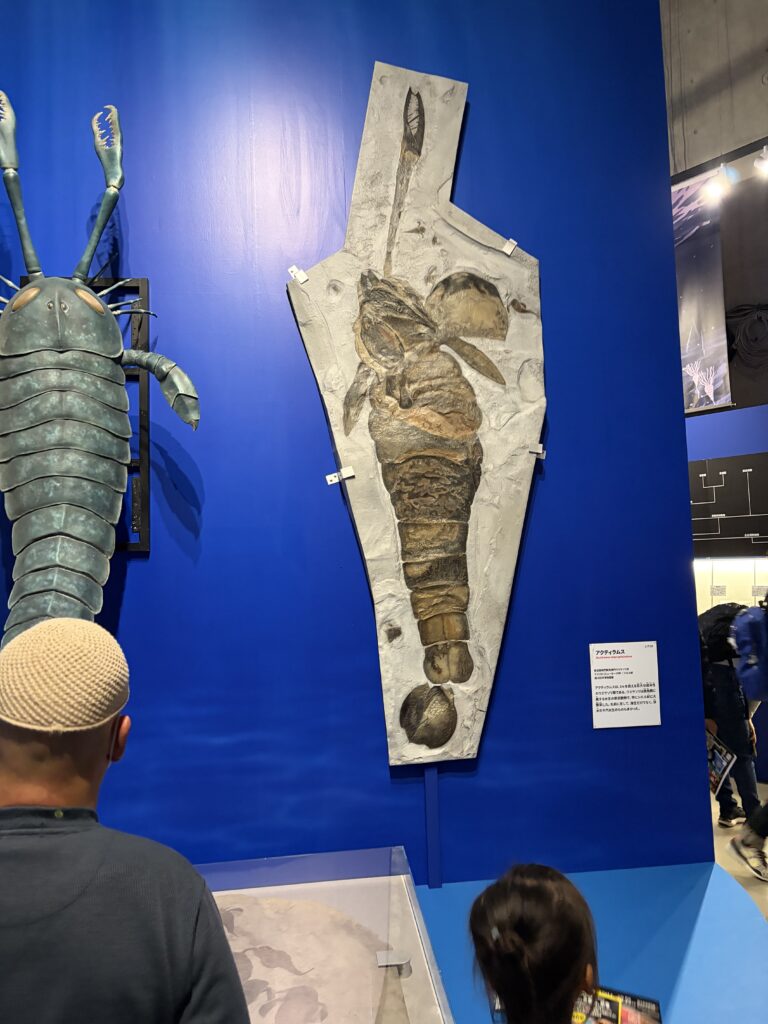

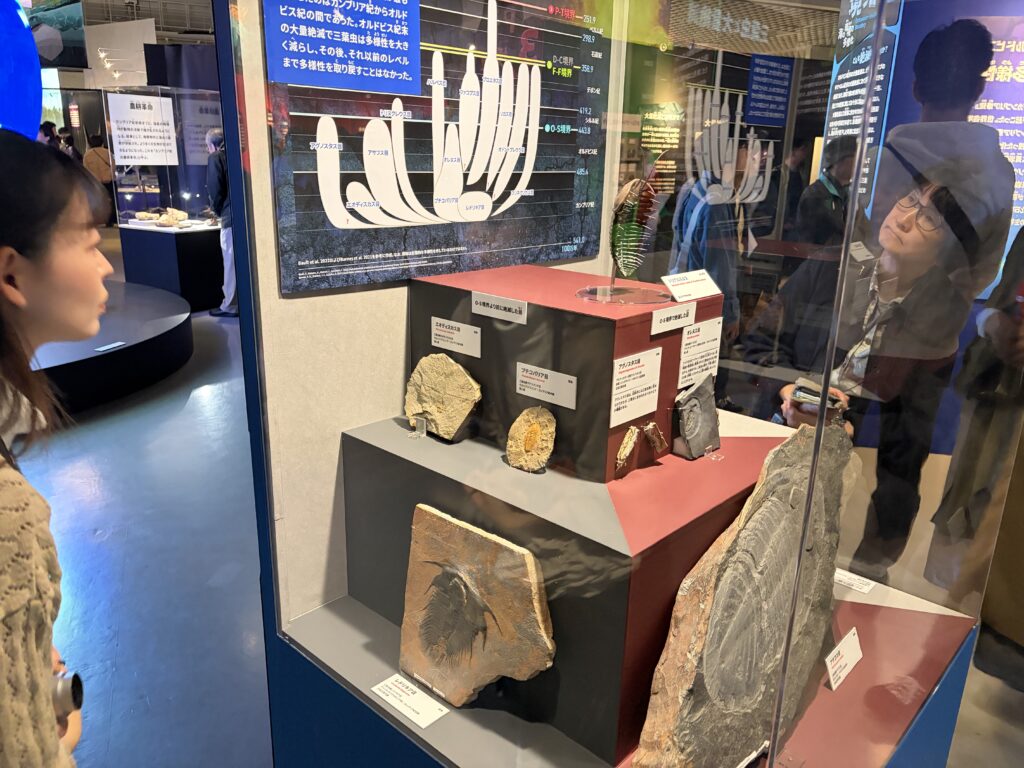

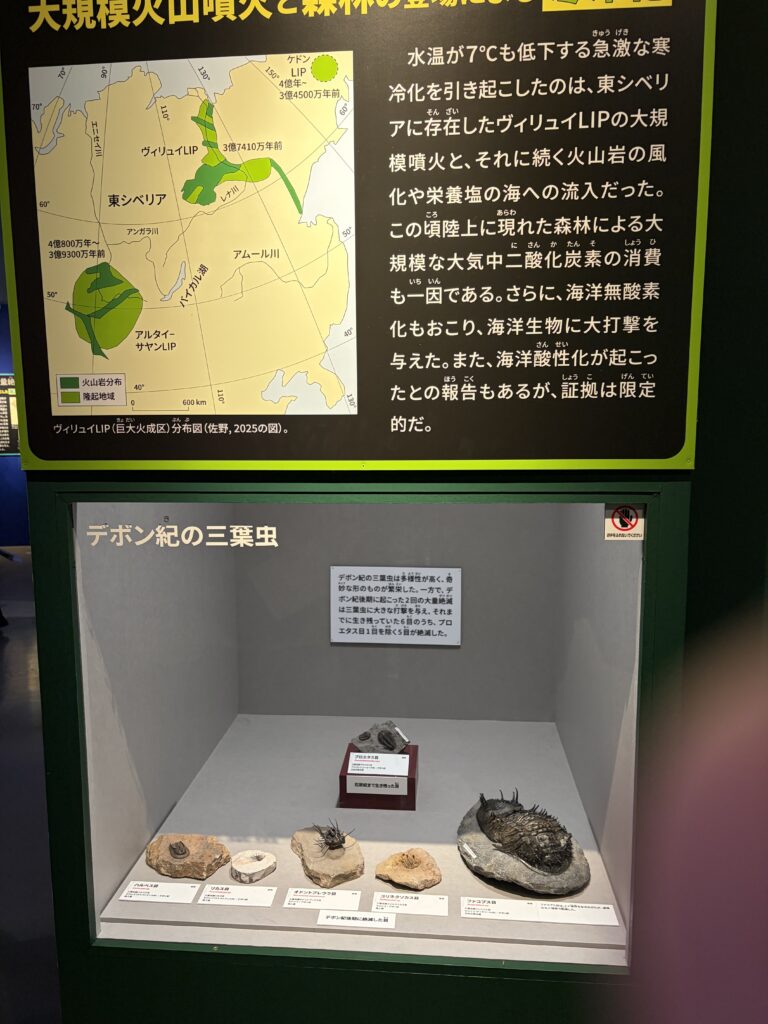
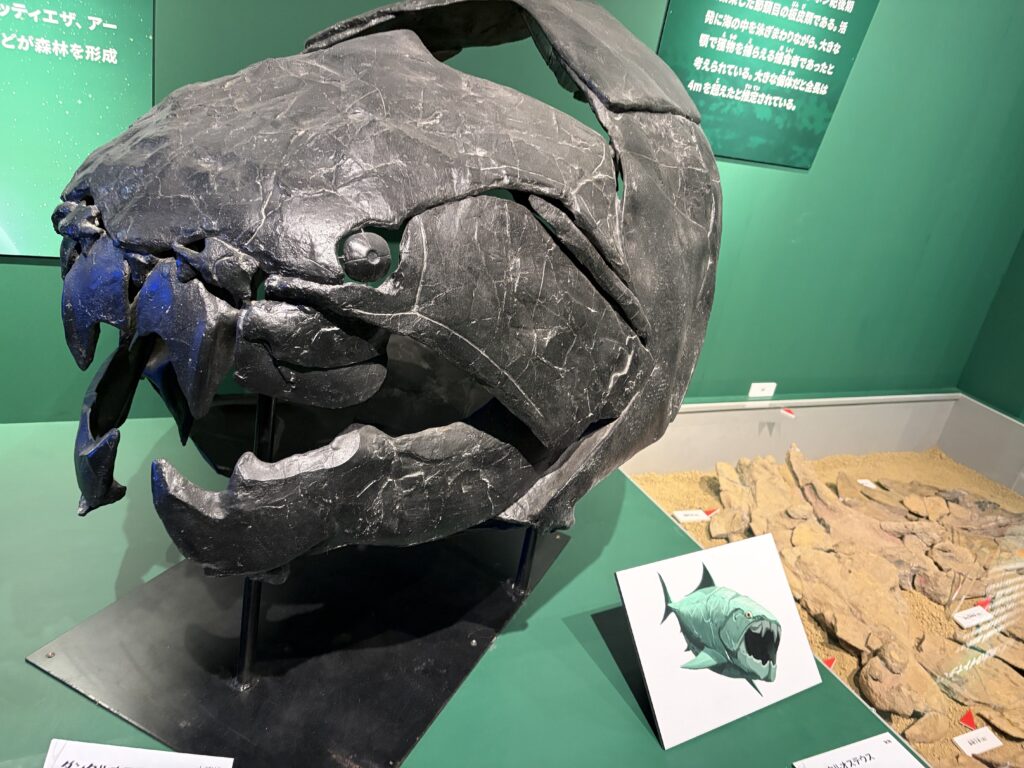
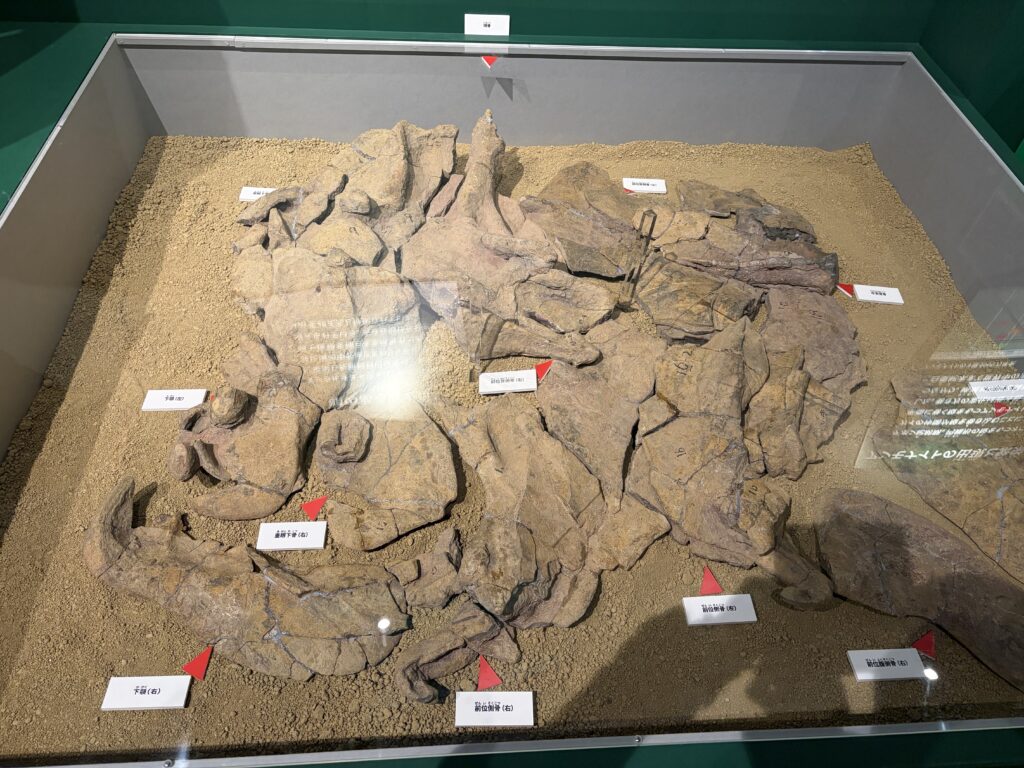
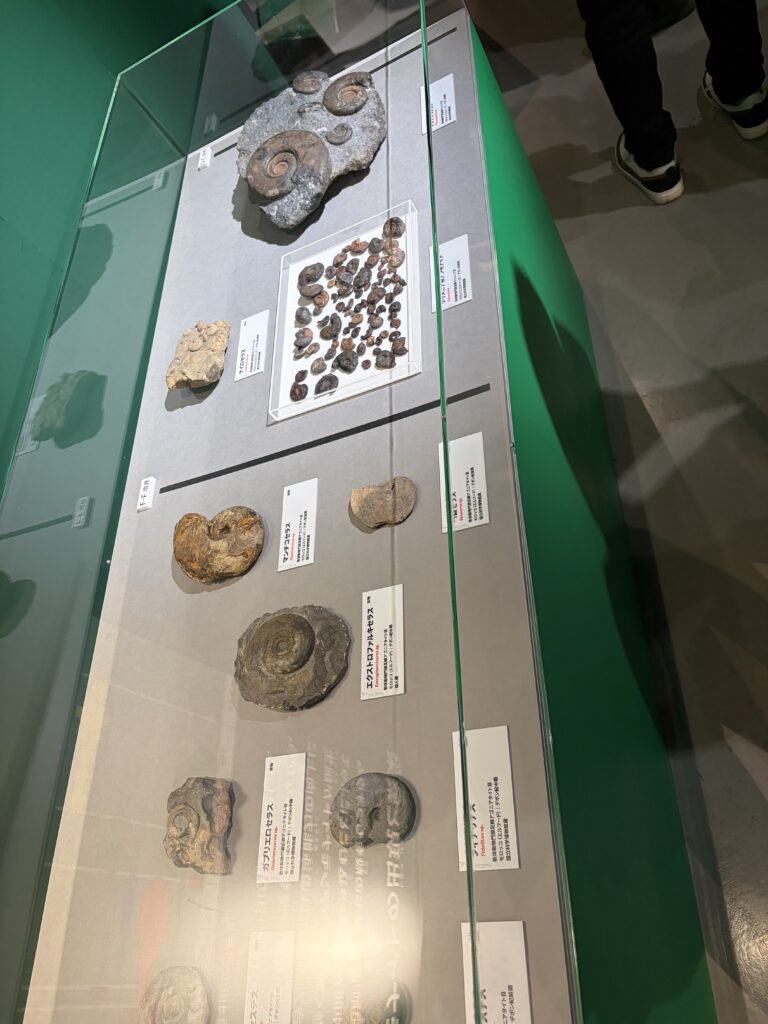
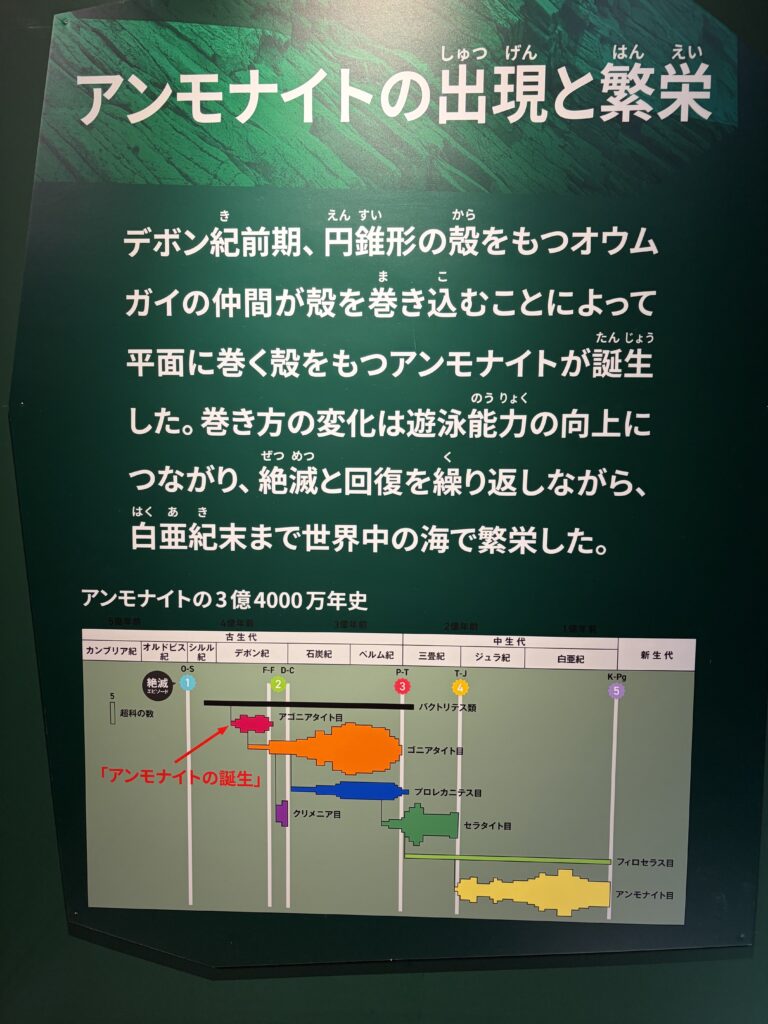
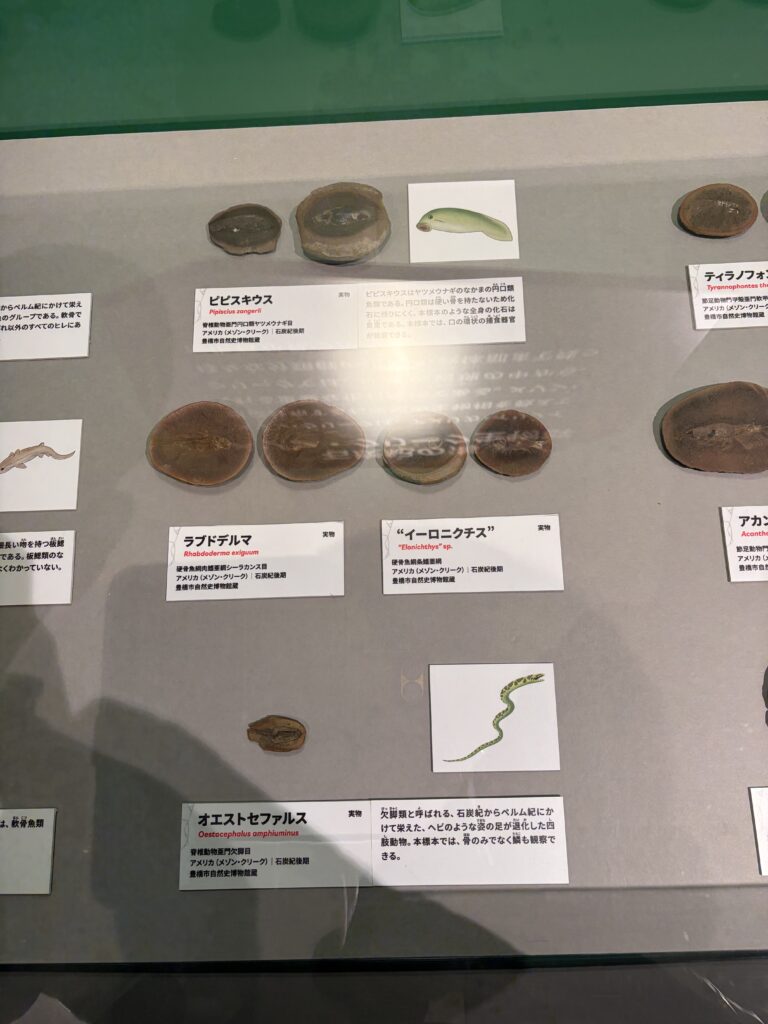
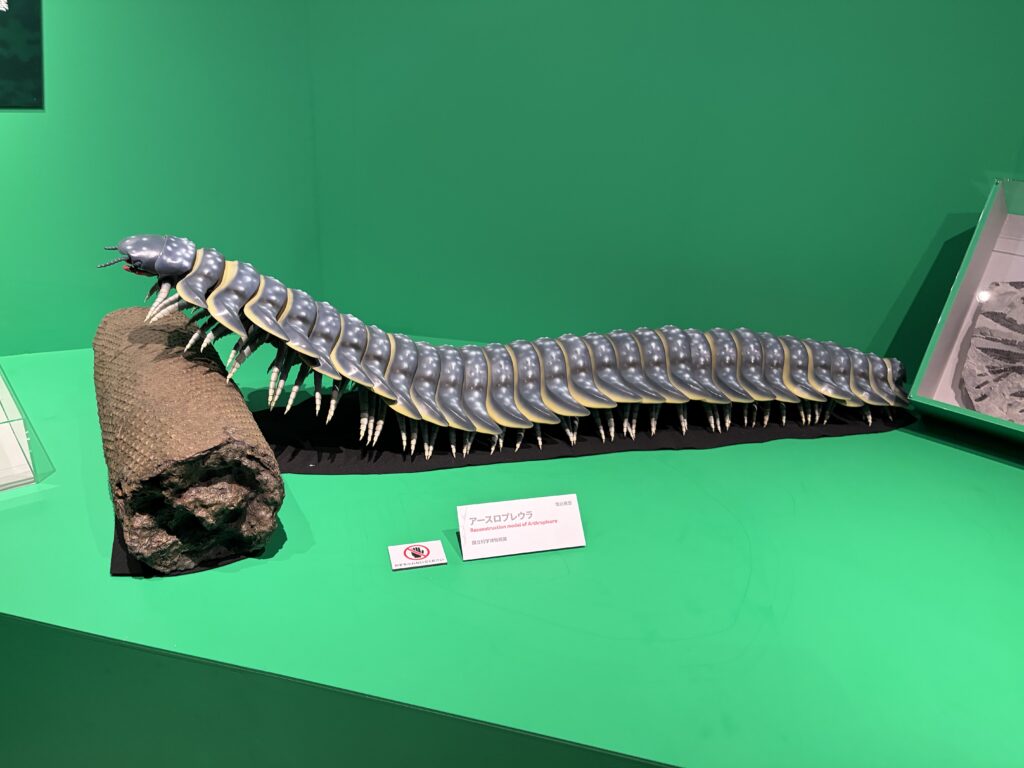



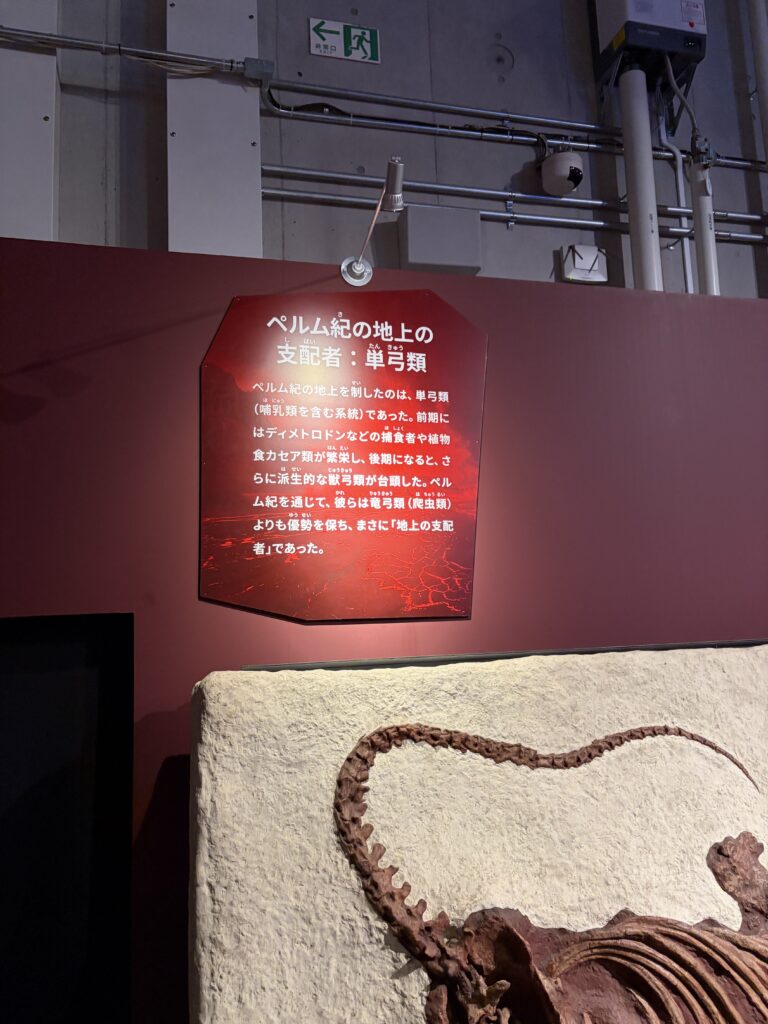



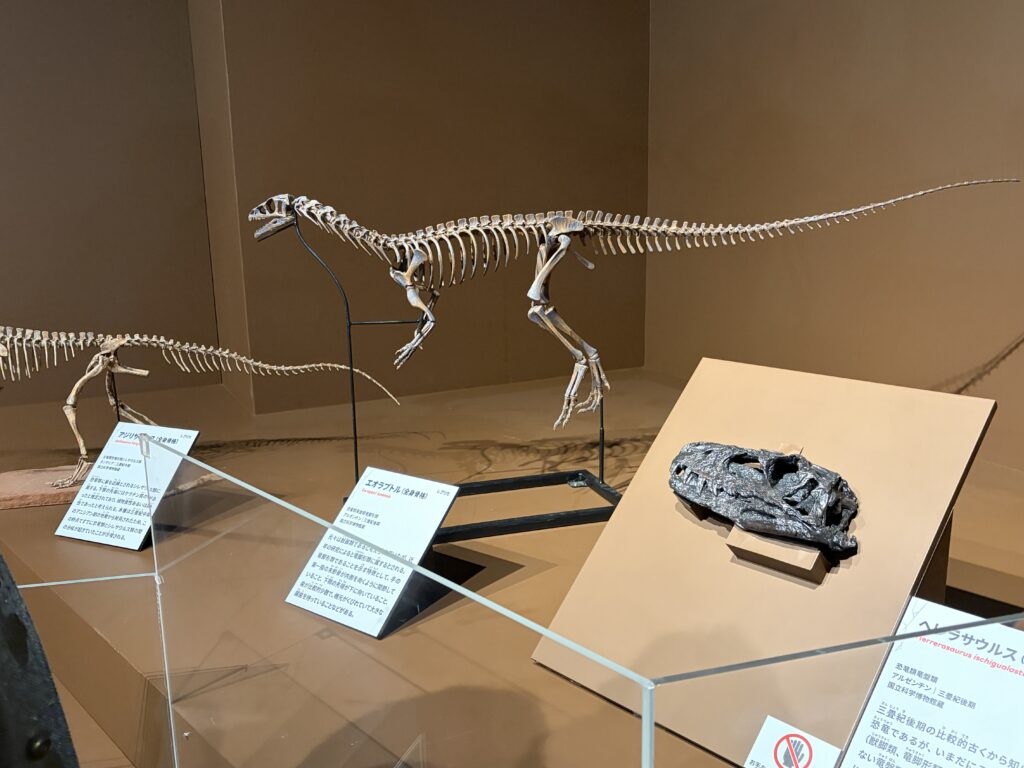
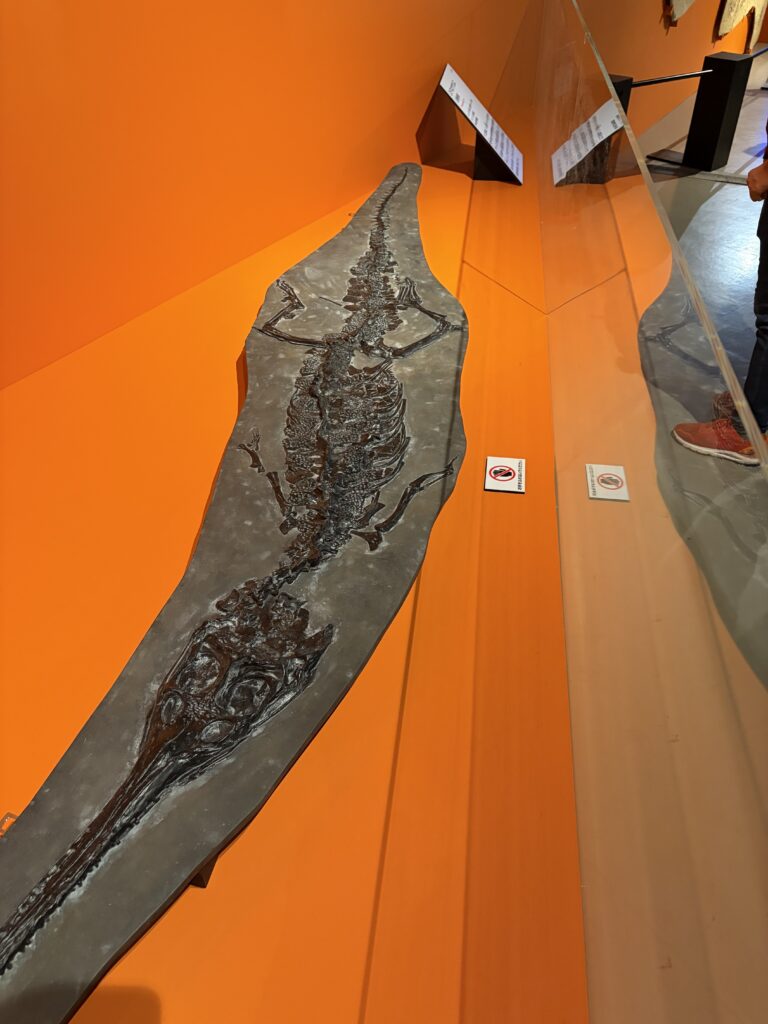
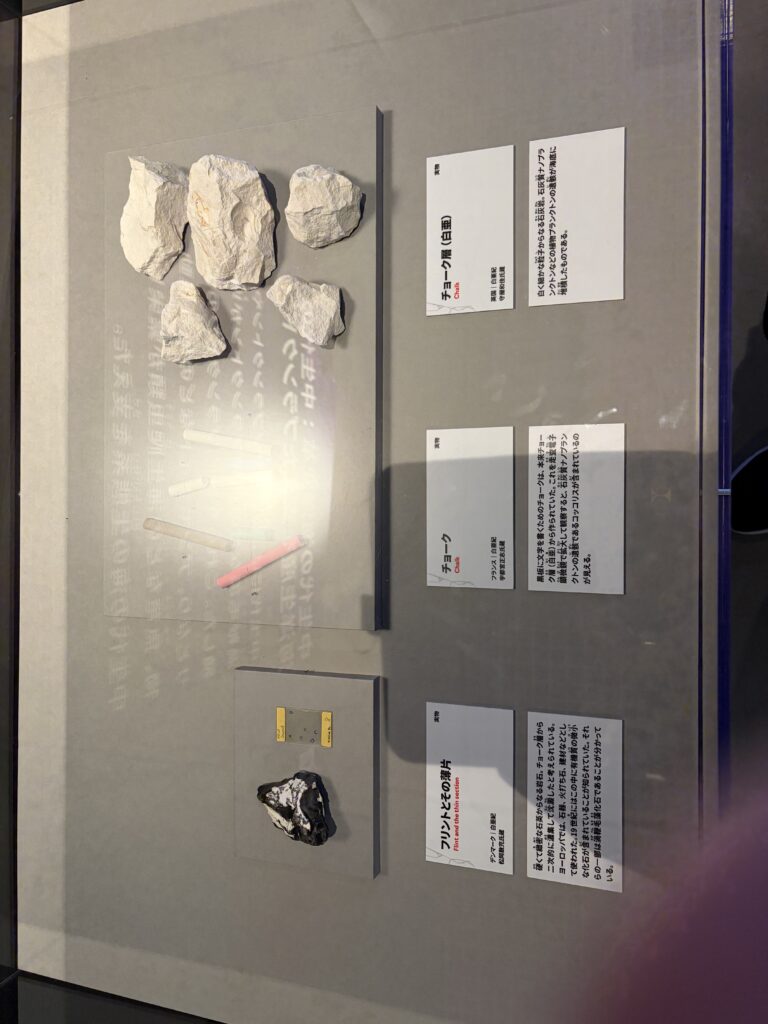
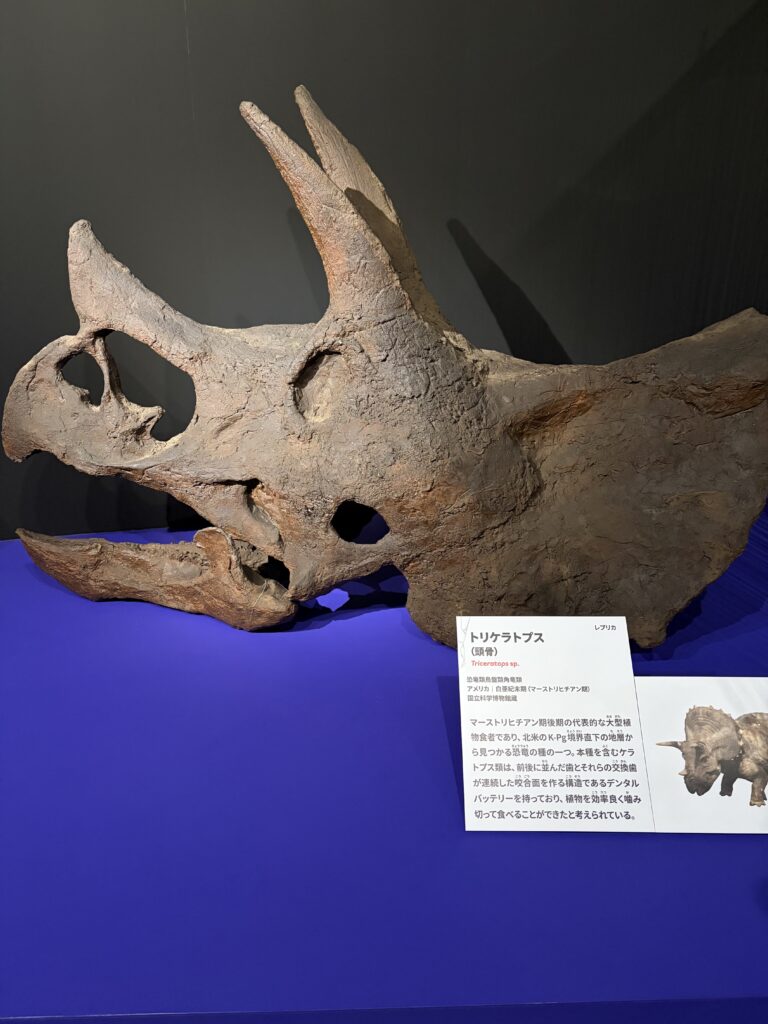
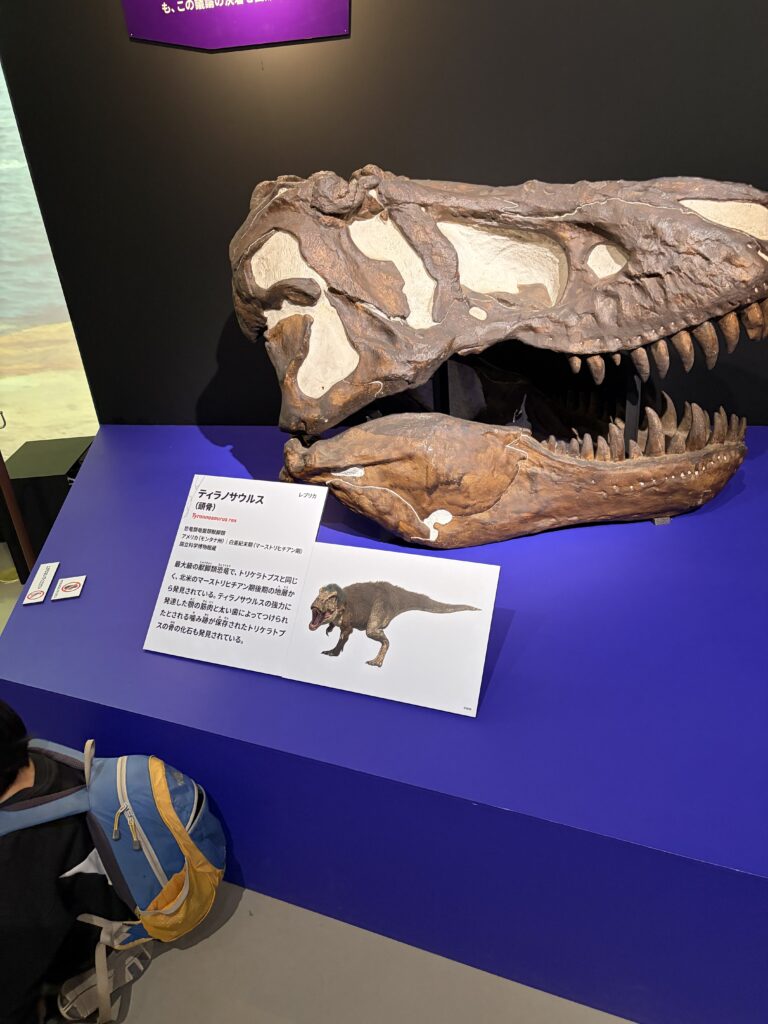



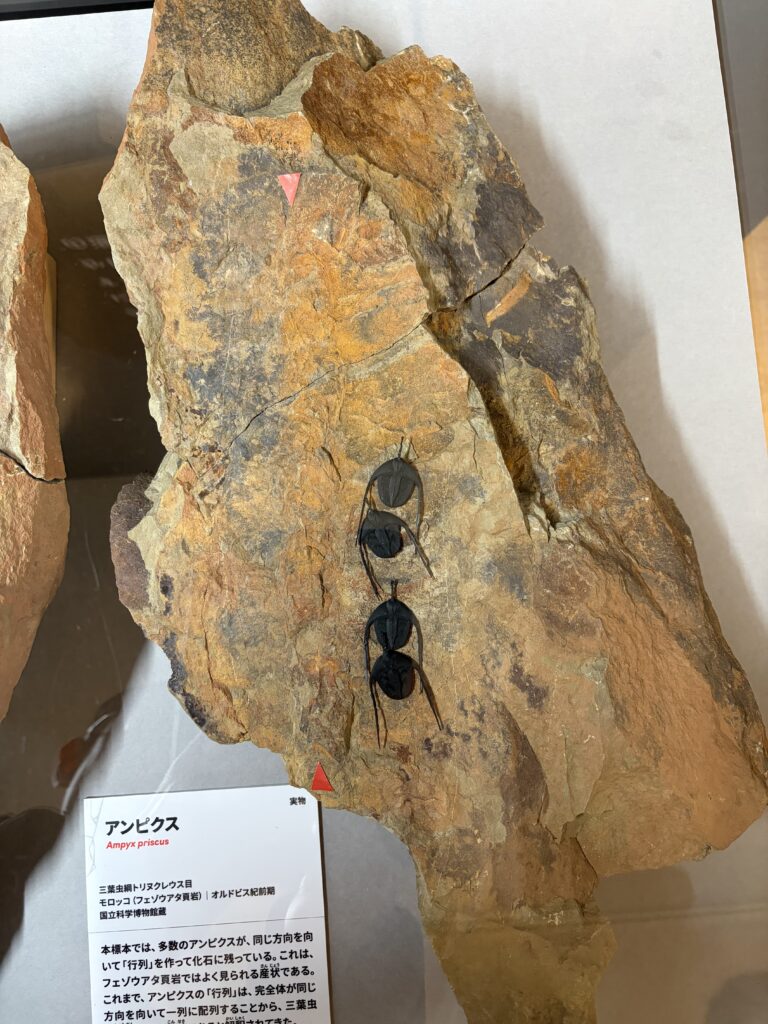
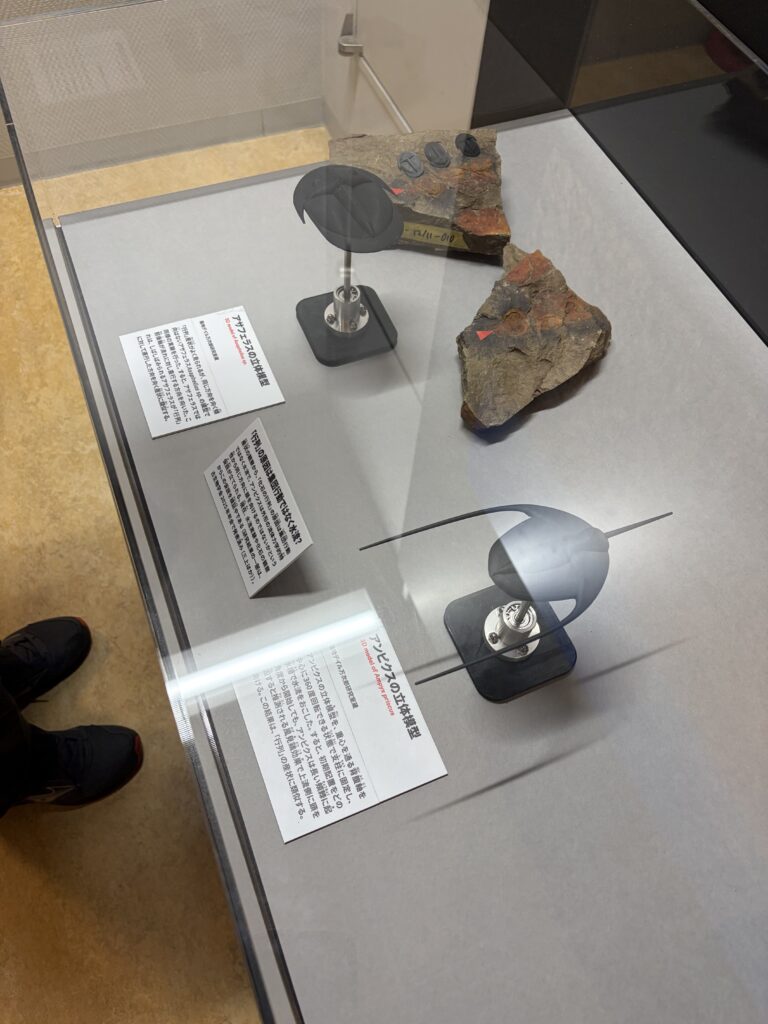
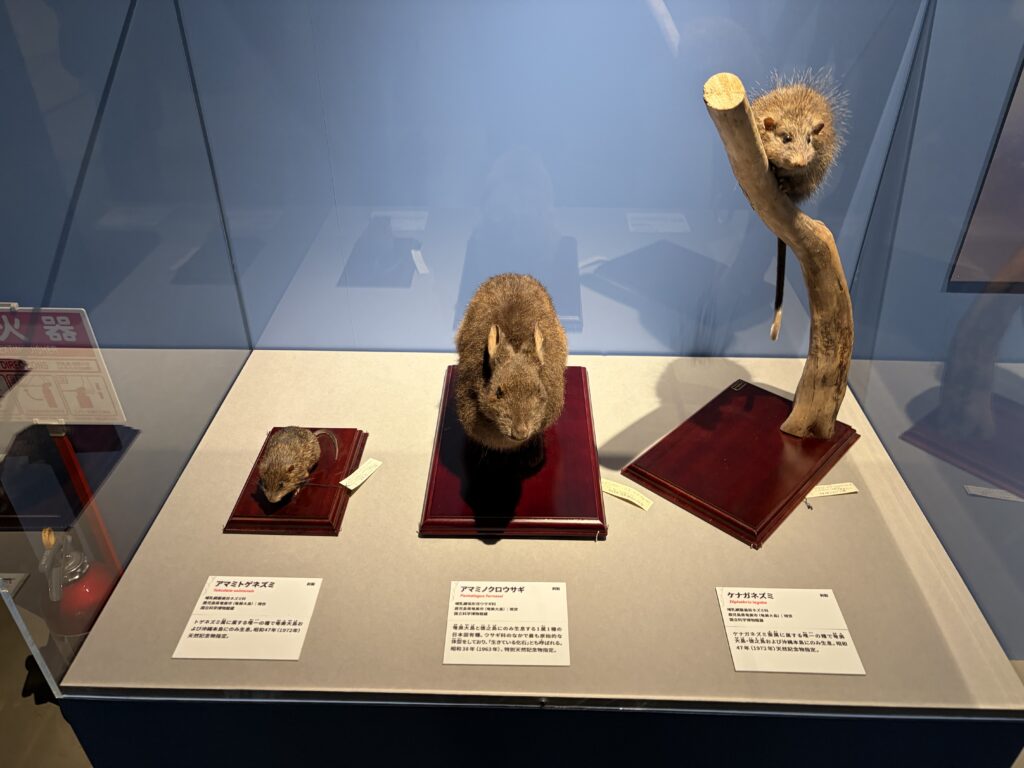
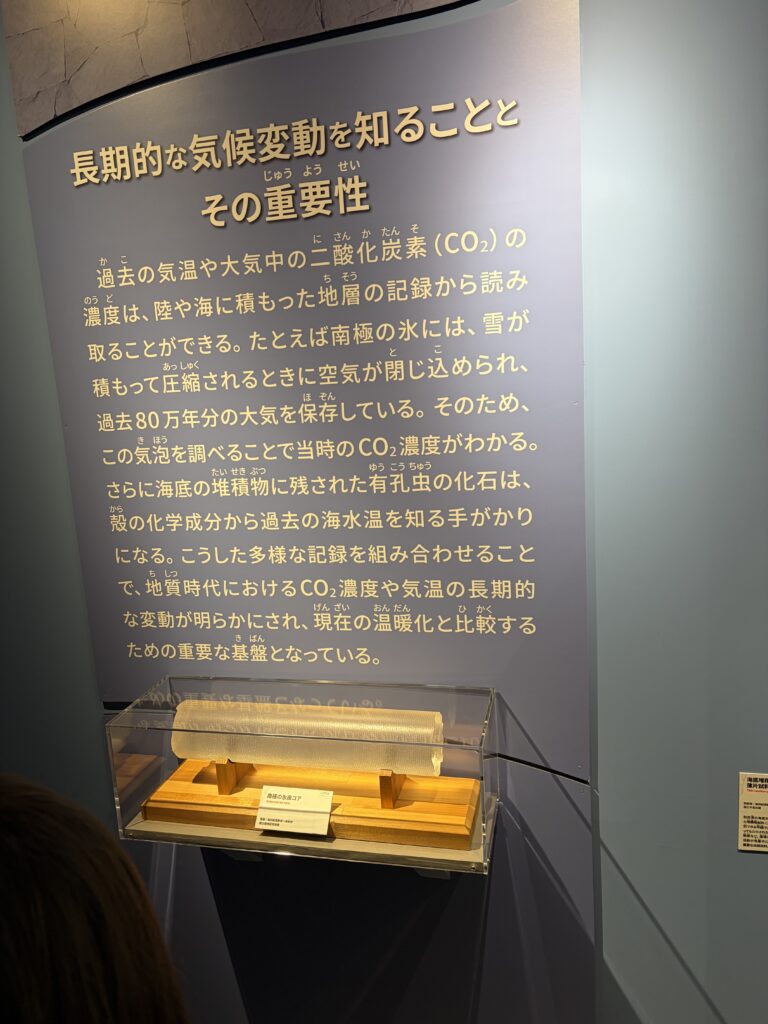



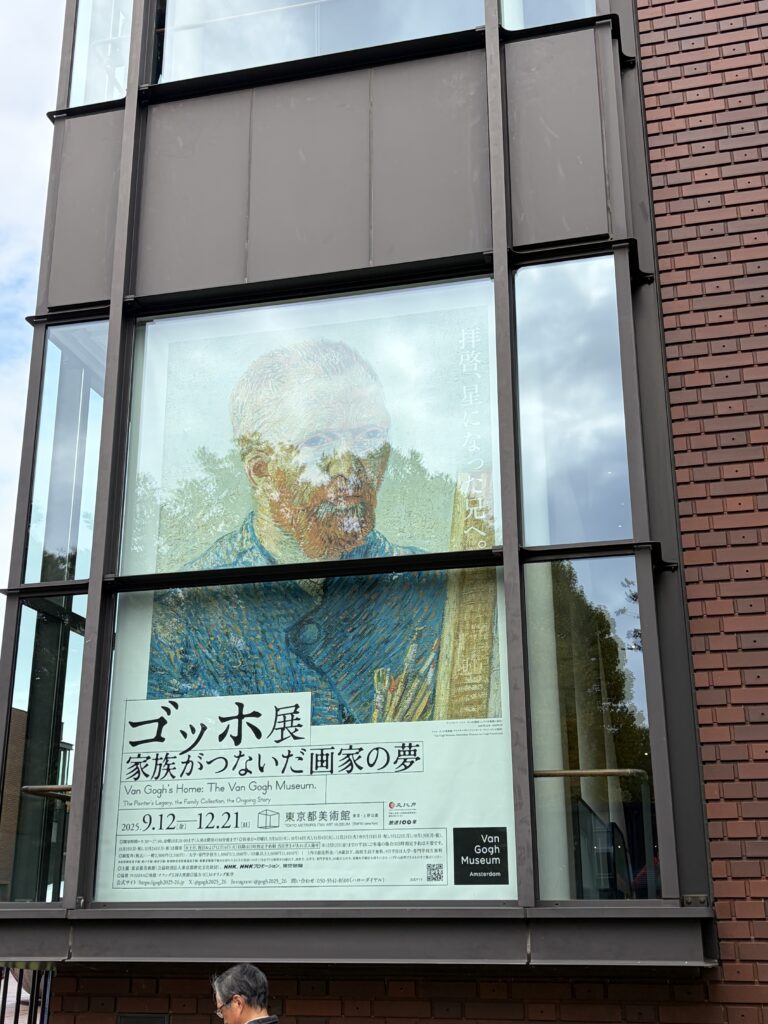


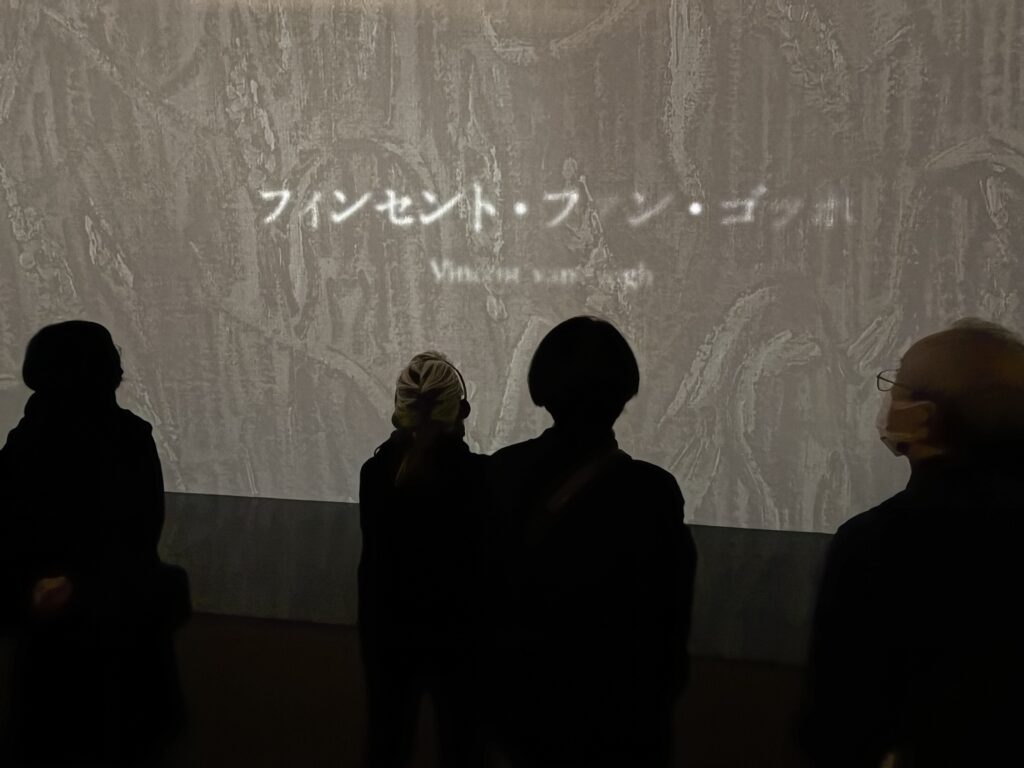

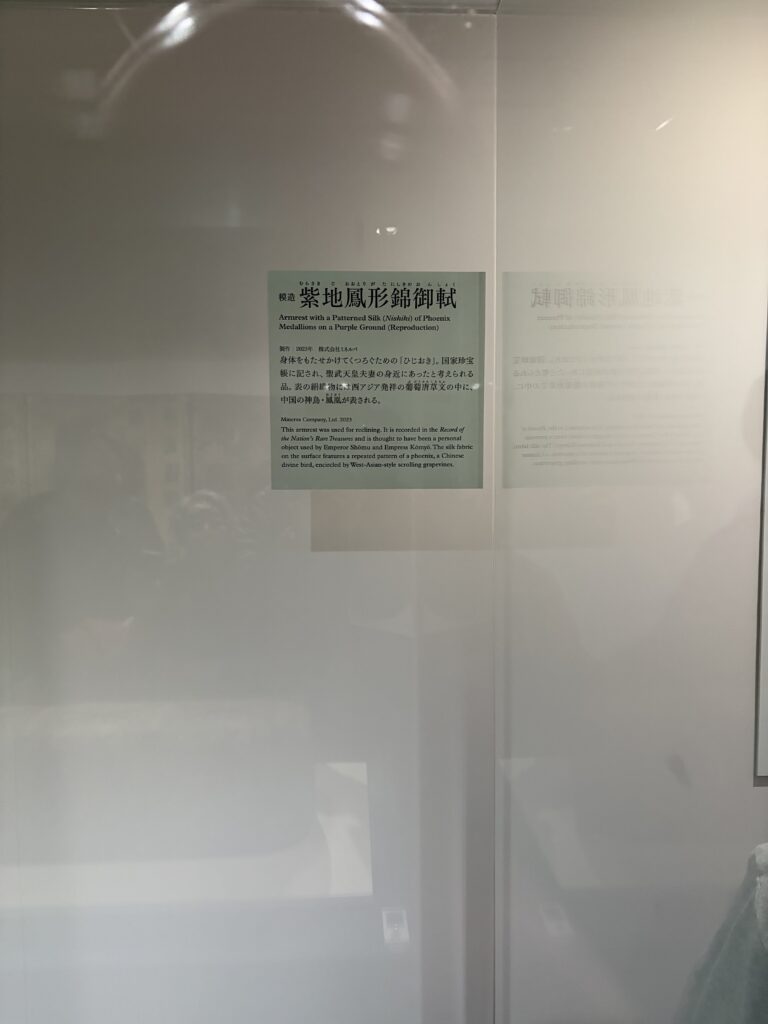

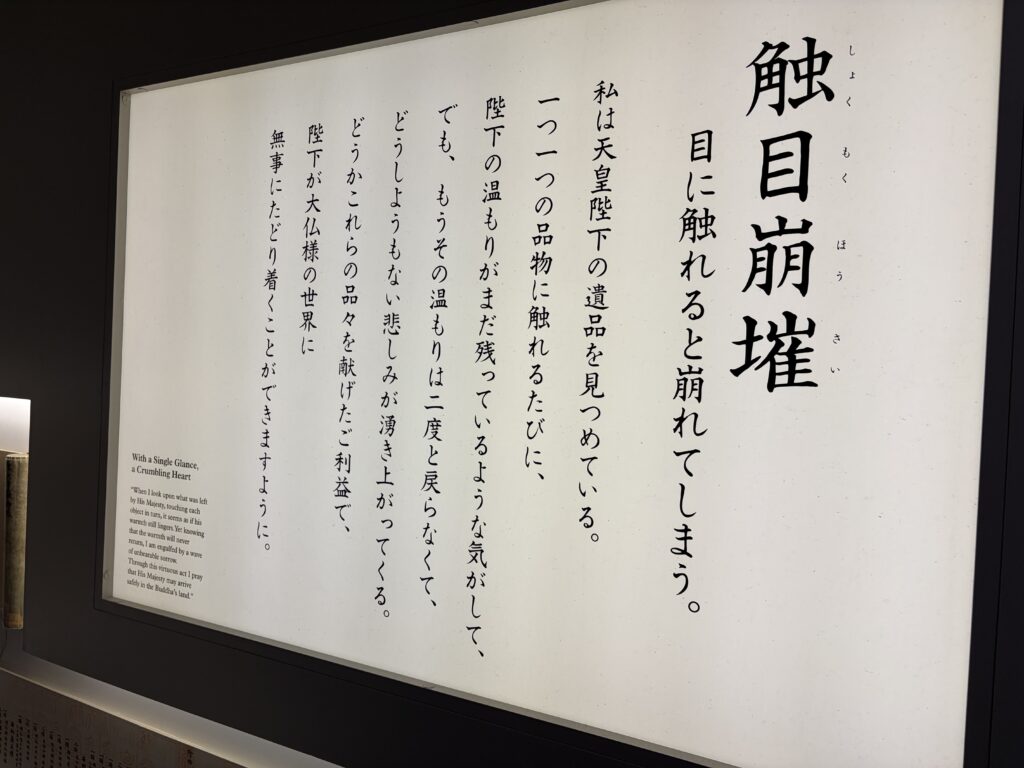

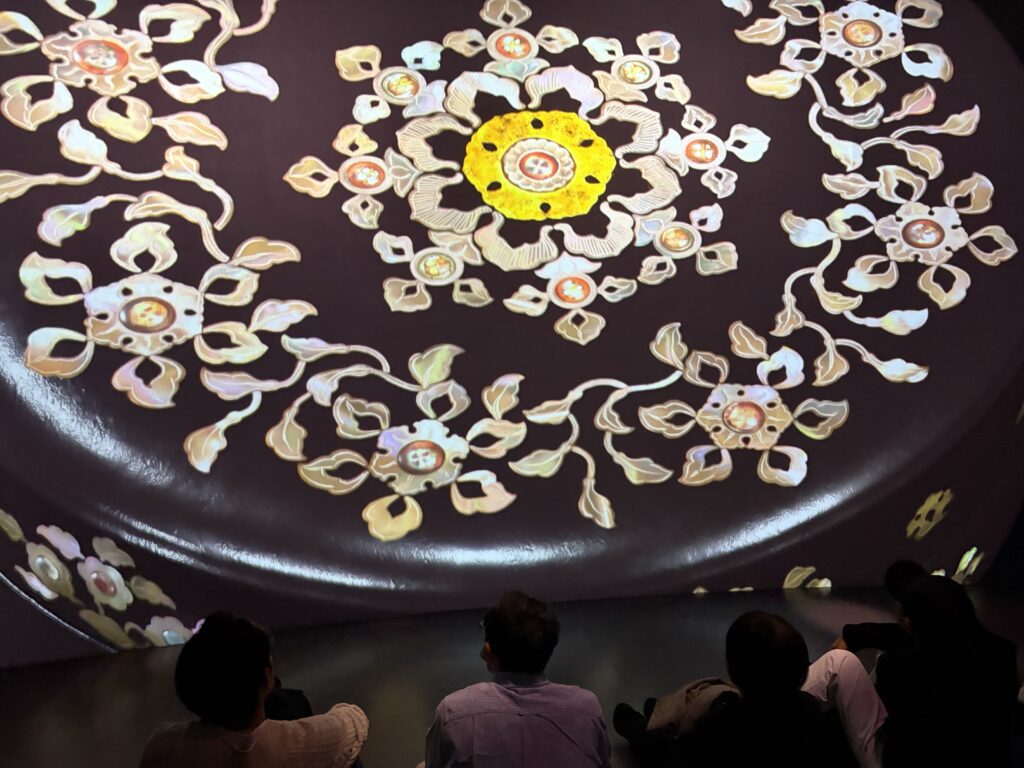


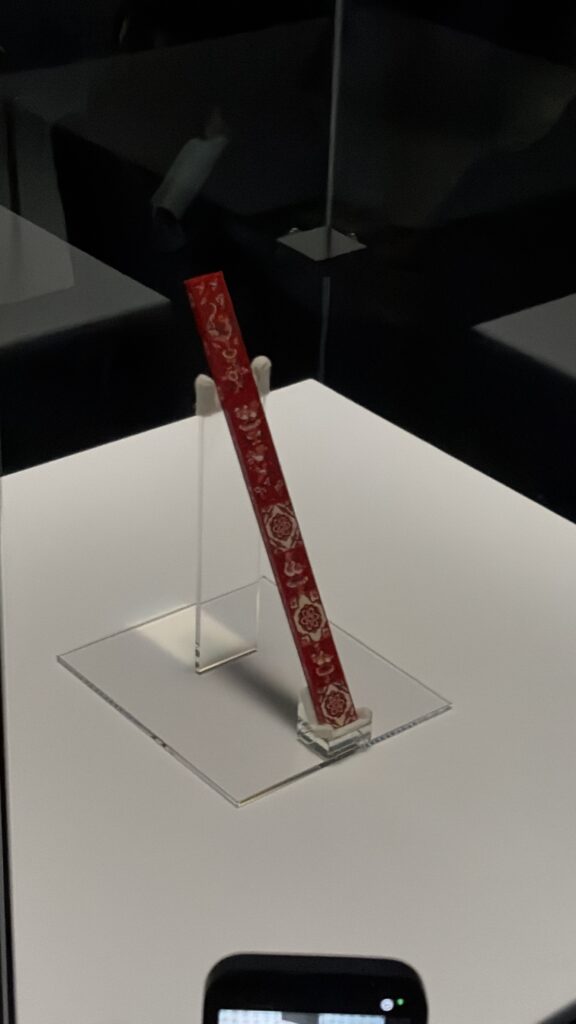
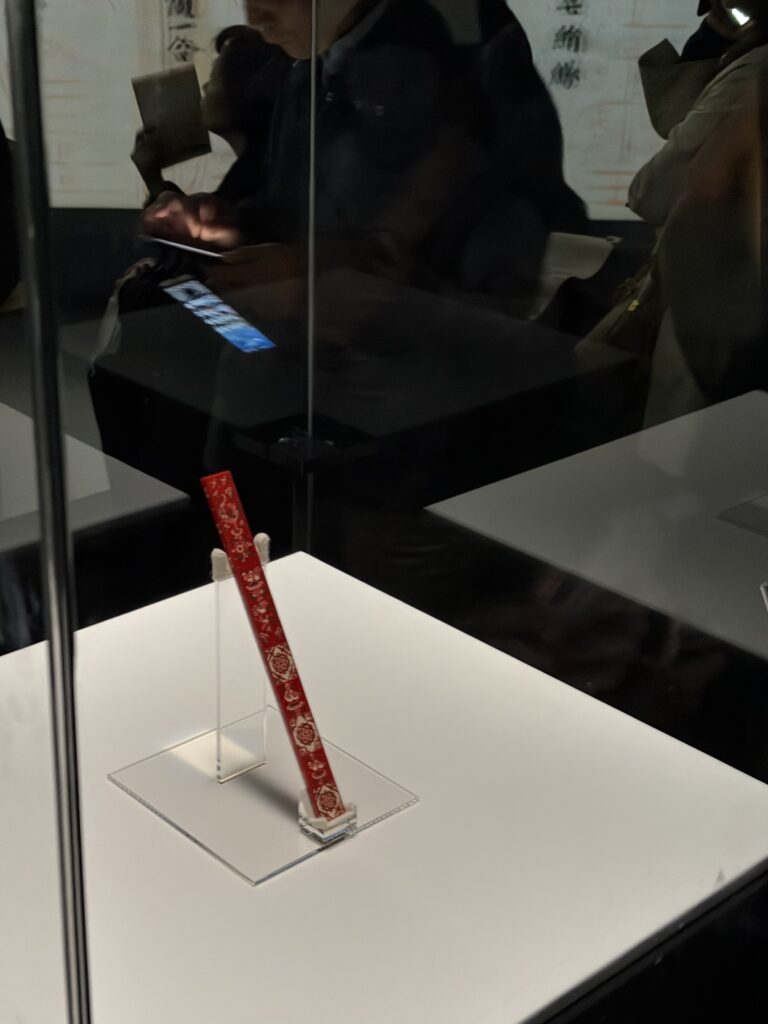

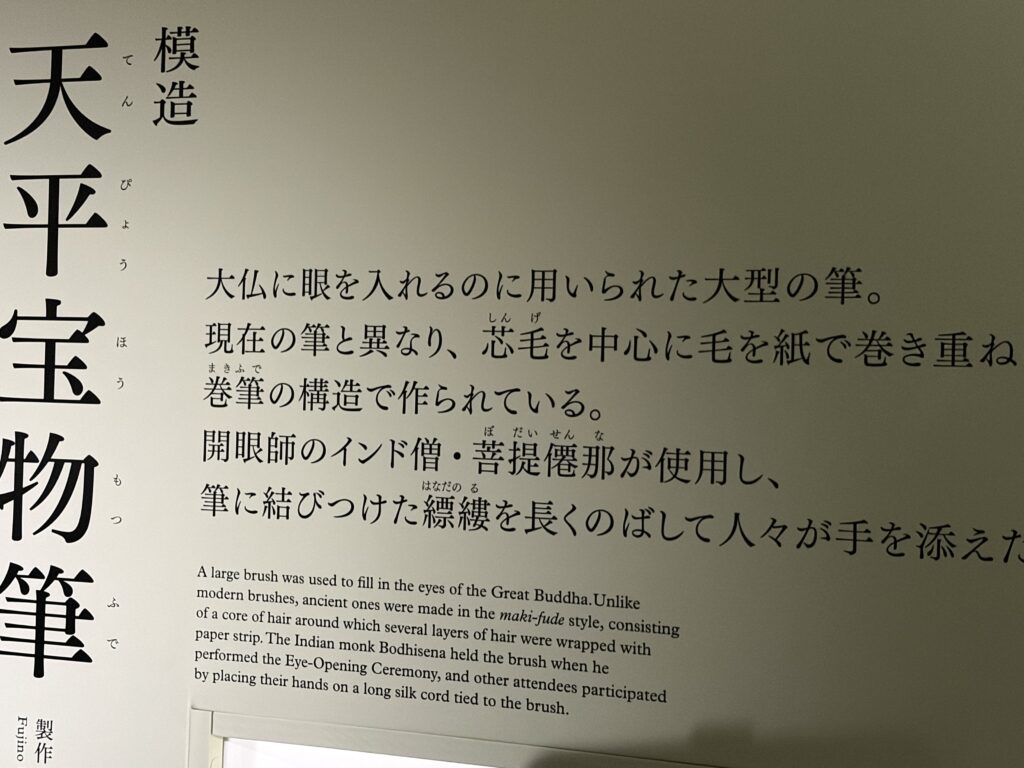





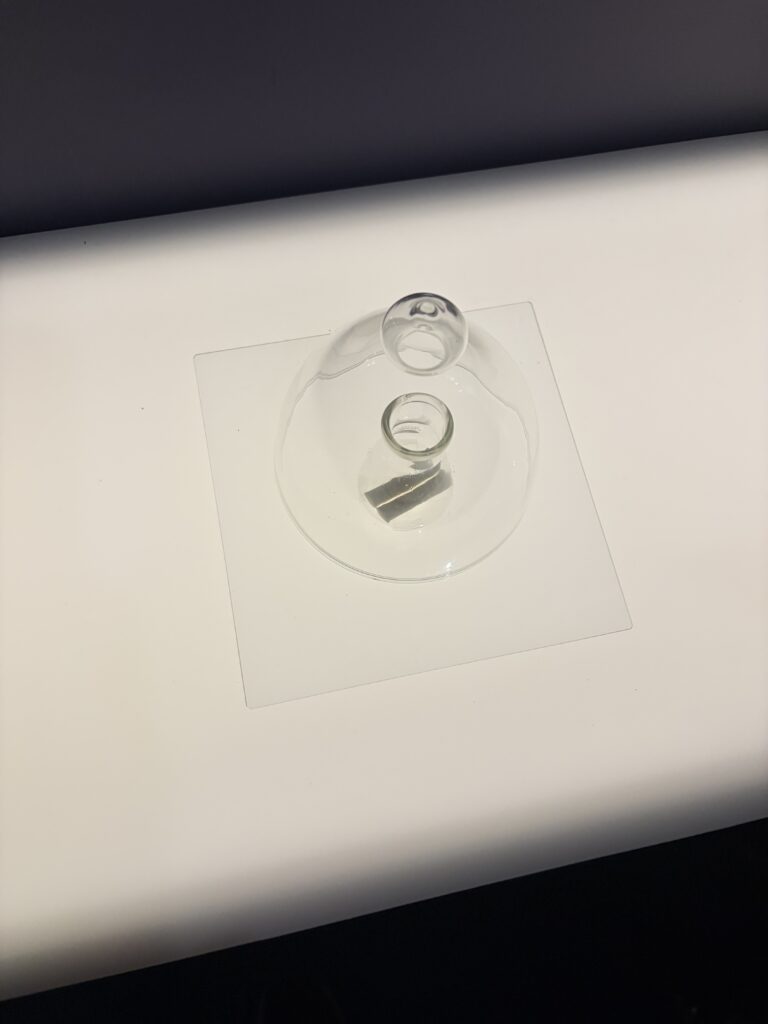

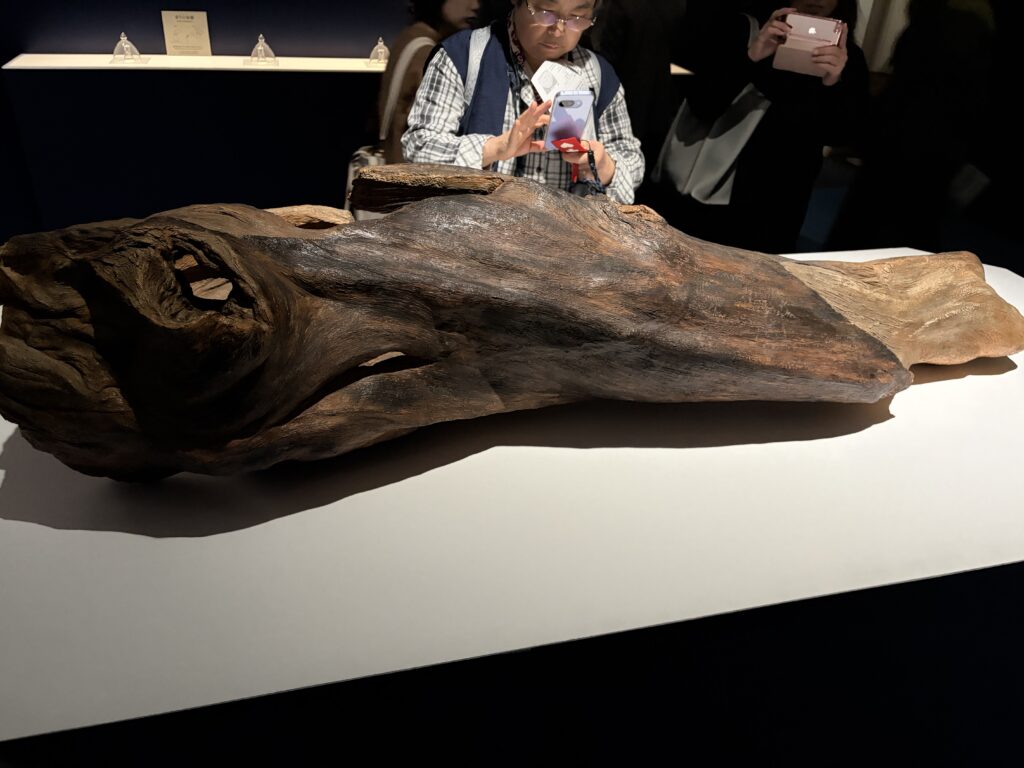



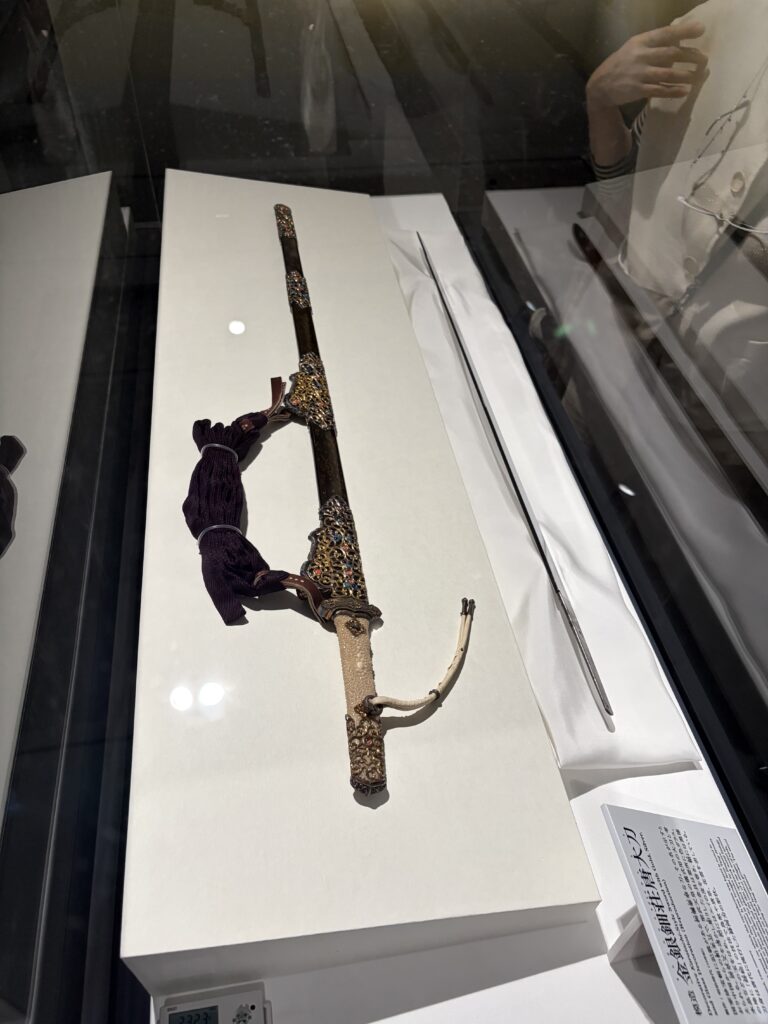






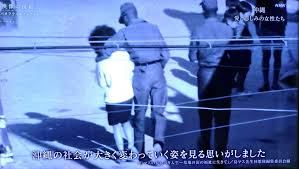





コメント