
私は、夢洲の地に二度足を運んだ。
一度目は九月十六日、そして二度目は十月七日。
どちらも火曜日だった。
朝焼けのなか、弁天町からタクシーで向かい、
人々の熱気と歓声の中に溶け込んだあの時間を、今もはっきりと思い出せる。
二度目に訪れた日は、来場者数二十万人。
人の波、列、歓声、音楽、そして風――
あの場にいたすべての人が、どこか“未来”という共通の幻を見ていた。
それは国境も年齢も超えた、奇跡のような祝祭空間だった。
世界のすべてが一瞬、調和したように思えた
万博の醍醐味は、ただの展示や技術ではない。
各国の人々が微笑み、違う言語で交わされる挨拶の数々。
その中で感じるのは、「人間って、本当はここまで優しくなれるんだ」という実感だ。
それは私たちが日常の中で失いかけている“理想の人間像”そのものだった。
だからこそ、終わった今、その理想の喪失が胸に深く残る。
帰りの電車の窓に映る自分の顔が、どこか現実に戻りきれていない。
あのときの輝きが、いまだ心の奥で光を放っているのだ。
万博ロスとは、終わりではなく“再生”の予感
多くの人は万博ロスを「祭りのあと」の虚しさだと言う。
だが、私はそうは思わない。
それはむしろ、何かが自分の中で動き出す前の静けさだ。
あの祝祭の光景は、確かにもう戻らない。
しかし、あの場で見た人々の笑顔や、心を震わせた展示の数々は、
私の中で“次の創造”を促している。
「もう一度、あの熱を生きたい」――そう思う限り、人生は続いていく。
万博の終焉は、心の中の“はじまり”である
人は熱狂の終わりにこそ、自分の生を見つめ直す。
それが高校野球の引退試合であっても、恋愛の別れであっても、
あるいは万博の閉幕であっても、同じだ。
“もう終わってしまった”という感情の裏には、
“また始めたい”という命の衝動が潜んでいる。
万博ロスとは、言い換えれば――
**「人生の祝祭が終わったあとに訪れる、創造の前兆」**なのだ。
そして、次の夢洲へ
もう一度、あの場所に立ちたい。
だが、次の万博を待つよりも、
私は自分の中に“夢洲”をつくる方を選びたい。
それは、日常の中に理想を見出し、
誰かの心に希望の火を灯すような仕事や言葉を紡ぐこと。
万博ロスとは、私たちが“未来を愛してしまった”証なのだ。
その痛みこそが、次の創造の出発点になる。






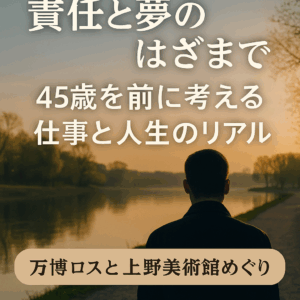


コメント