私は万博に二度足を運んだ。
一度目は、終盤を迎えつつあった九月十六日。
そして二度目は十月七日、同じ火曜日だった。
この日は来場者数が二十万人を超え、夢洲の地は熱気と喧騒に包まれていた。
最初は一日だけの予定だった。
「イタリア館と日本館、そして〈いのちの未来〉さえ見られればそれでいい」と思っていた。
だが一度行っただけでは、あの場所を離れがたかった。
心に残る“万博ロス”に耐えきれず、私は再び夢洲へ向かった。
二度目の訪問では、この光景を網膜に焼き付けるように、ほとんど駆けるように歩き回った。
そして、三日経った今も私は、まるで失恋した後のように、胸の奥が空洞になったままだ。
なぜ、これほどまでに惹かれるのだろう。
夢の中で、かつて甲子園を目指していた高校時代の監督が現れた。
私は再びチームの一員として練習に励んでいる。
けれど、周囲の温度はどこか冷たく、緊張感も希薄だった。
「所詮、スポーツなんてお金にならない。真剣になりすぎるのも馬鹿らしい」――
そう思い直すと、あの眩しかった高校野球の世界さえ、現実には存在しなかったのだと悟る。
あれは多くの大人たちの思惑と保護によって作られた“理想の世界”だったのだ。
万博もまた同じだ。
アメリカ資本が日本のラスベガスを夢洲に築こうと手を伸ばし、
政府と大阪の産業振興の名のもとに、
幾重もの思惑が交錯している。
それでも、ゲートをくぐった瞬間、そこには確かに“平和”があった。
世界中の人々が笑顔で迎え入れ、歌い、踊る。
警備は厳重で、秩序が保たれ、
まるで東ゲートと西ゲートの内側だけが“地上の楽園”であるかのように感じられるのだ。
実際には存在しないはずの世界。
けれど、私は五感で確かにそれを経験した。
だから「たしかに平和はそこにあった」と言いたくなる。
だがそれは、大屋根リングに囲われた半年間だけの幻――
多くの思惑の上に建てられた、砂上の楼閣のような平和だったのかもしれない。
パビリオンに入らずとも、各国の前では歌声が響き、
即興の芸に拍手が湧いた。
私もその拍手の一人に混じりながら思った。
――ここに平和がある、と。
いつか「富士山の頂上で百人のおにぎりを分け合いたい」と願ったあの日の夢が、
ついにこの夢洲で叶ったような気がしたのだ。
すべての人種が、すべての動物が、
あらゆる存在が愛おしく感じられる夢の世界。
それこそが、各パビリオンが描こうとした理想ではなかったのか。
そして、“万博ロス”の正体とは、
人間が本能の底で渇望してやまない――
「夢の中の平和」への郷愁なのではないだろうか。










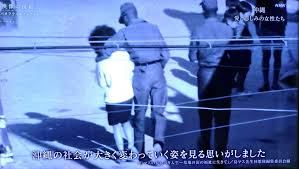




コメント