コモンズD──“食こそ万博の中心”
住友館の予約まで、50分ほど余裕があった。
時間は13時10分。万博の来場者数がピークを迎える頃だ。
私は軽い気持ちで「コモンズD」を歩いてみた。
ところが、入ってすぐに入場規制。間一髪のタイミングだった。
コモンズDの中では、各国の文化や産物が飾られ、現地スタッフがパンフレットを配っていた。
派手さはないが、素朴で、それぞれの国の空気が滲み出ている。
一方で、現地料理を提供するカフェやフードブースは長蛇の列。
万博のもう一つの主役は“食”なのだと改めて感じた。
人は「安心・安全」の中で、世界の味覚を楽しみたいという欲求を持っている。
万博の食エリアは、その欲求を満たすための最高の舞台だった。
単体のパビリオンがなくても、食の香りと人の賑わいだけで、そこは一つの「世界」だった。
住友館──ランタンが灯す森の記憶
そして、今回もっとも楽しみにしていた「住友館」へ。
物語は、見えない微生物の世界から始まり、“マザーツリー”と呼ばれる森の母の誕生へとつながる。
来場者はランタンを手に、暗い森の中を歩く。
光をかざすと、クワガタやキノコ、リス、キツネが浮かび上がる。
木の洞の中では、キツネの親子がじゃれ合う映像が流れ、
子どもの頃に林でカブトムシを追いかけた夏の記憶が、ふと蘇った。
係員が懐中電灯を手に「上を見てください」と声をかけると、
テラスの梁の上に猫やリスの姿が。
人と自然の“共生”を、視線の先にそっと置いてくれる演出だ。
朝一で見かけた若い夫婦が、同じ回に参加していた。
きっとあの時、2人で住友館を予約していたのだろう。
ランタンを手に森を進むその姿が、どこか微笑ましかった。
「いつかこの夫婦にも子どもができたら、ぜひこの体験を一緒に味わってほしい」
そんな願いが自然に浮かんだ。
最後の演出では、白い衣をまとったダンサーが現れ、
風の映像と一体化するように舞う。
近年のパビリオンは映像中心になりがちだが、
“生身の人間”が立つことでしか生まれない感動がそこにあった。
ひとつの命が、ひとつの風になる——。
その瞬間、グラフィックのメッセージが、心の奥へ深く染み込んだ。


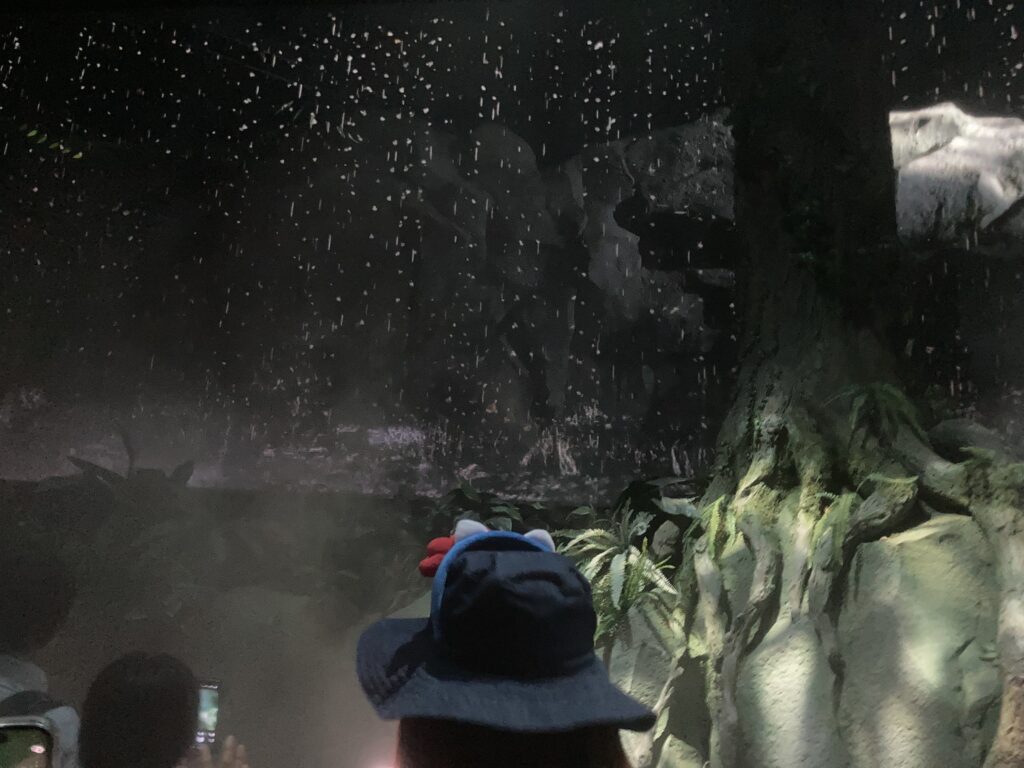
オランダ館──海と共に生きる国の知恵
次に向かったのは、予約していたオランダ館。
入場は予定より遅れたが、内容は期待を上回った。
入場時に球体を渡され、それを“チャージ”しながら展示を巡る。
オランダの歴史は、水との戦いの歴史である。
展示は「水と戦う時代から、水を活かす時代へ」と進行し、
最後には天井に映された地球が、海に沈みゆく映像へと変わる。
やがて天井全体が水面となり、観客自身が海中に包まれるような錯覚を起こす。
これはただの映像ではない。
オランダが何百年もかけて向き合ってきた“現実”そのものだ。
海水面の上昇を他人事として見られなくなる、静かな衝撃があった。
飯田グループ×大阪公立大学館──未来の住まいと人間の挑戦
意外な掘り出し物だったのが「飯田グループ×大阪公立大学館」。
事前評判は高くなかったが、ここには真摯なメッセージがあった。
テーマは「未来の住まい」。
二酸化炭素を分解して水素に変換し、家庭で再利用するという構想は、
夢物語に見えて、どこか現実味も帯びている。
火星での生活を想定した住宅デザインや、
糞便から健康状態を分析する装置など、
人間の生活を根本から見つめ直す提案が並んでいた。
無理かもしれない。
だが、こうした“無理への挑戦”こそが、未来を切り拓くのだと思う。
2階では、未来型住宅を体験できるエリアがあり、70分待ちの表示。
次にガンダム館の予約が迫っていたため断念したが、
後ろ髪を引かれる思いでその場を後にした。
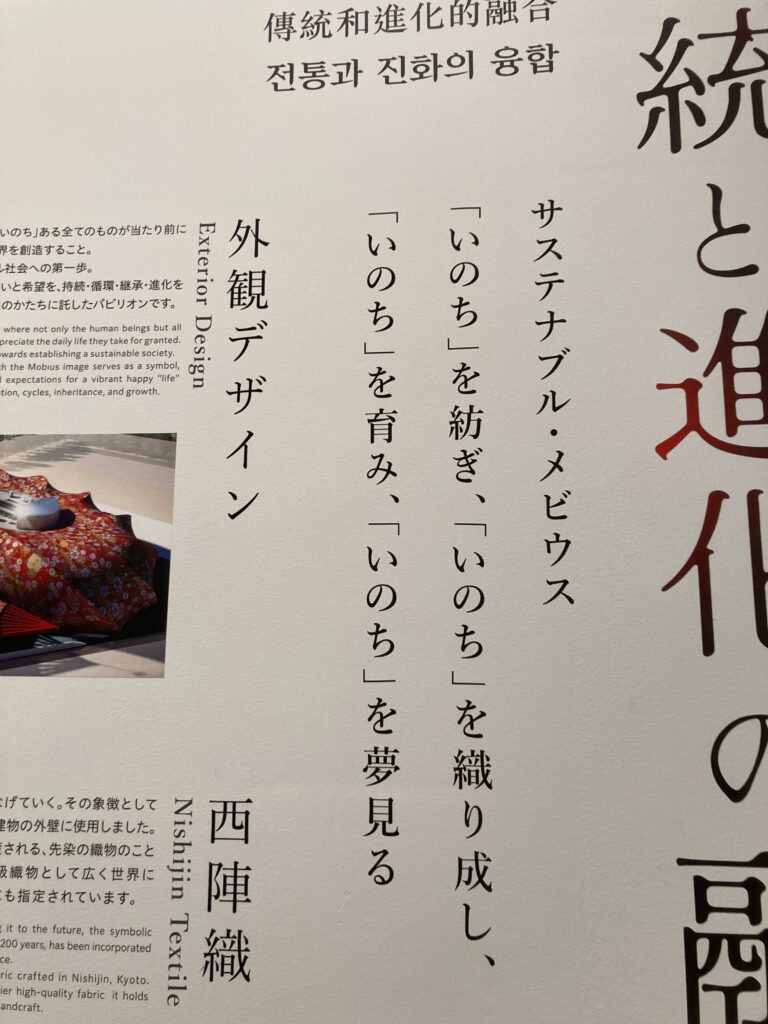
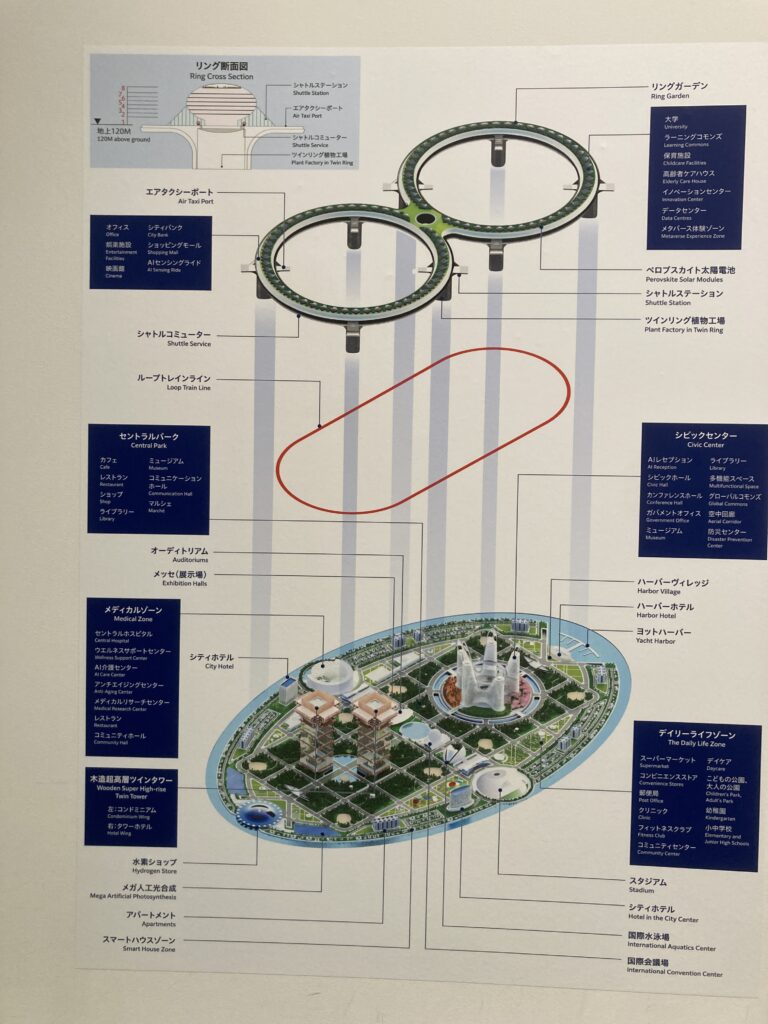

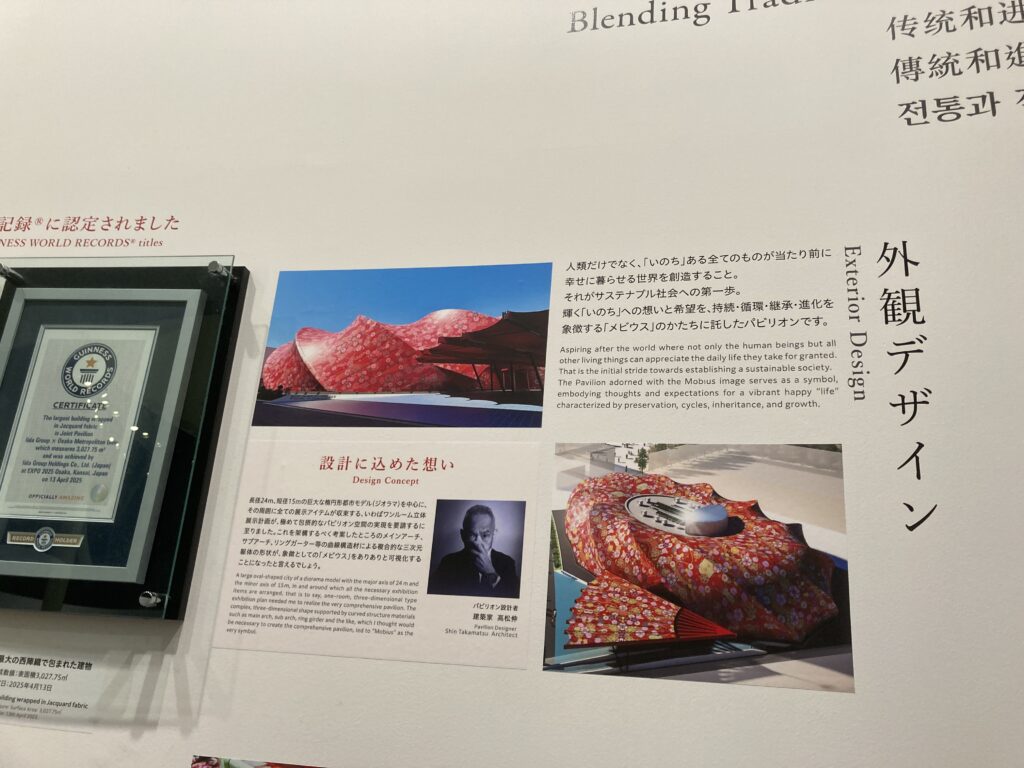



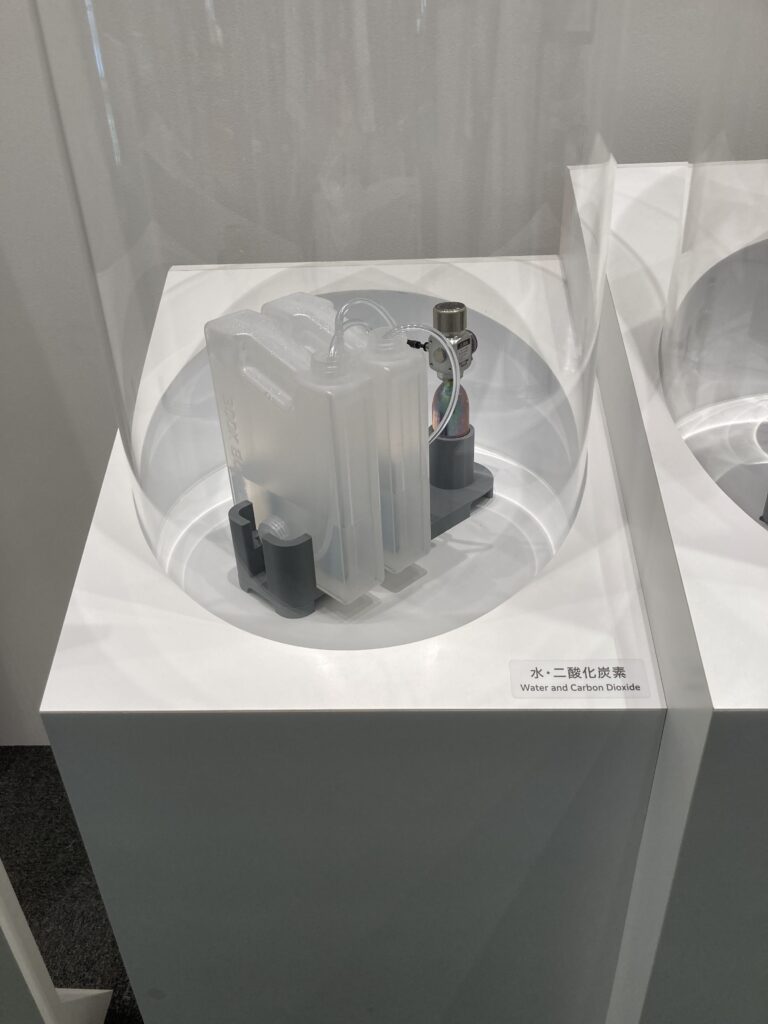
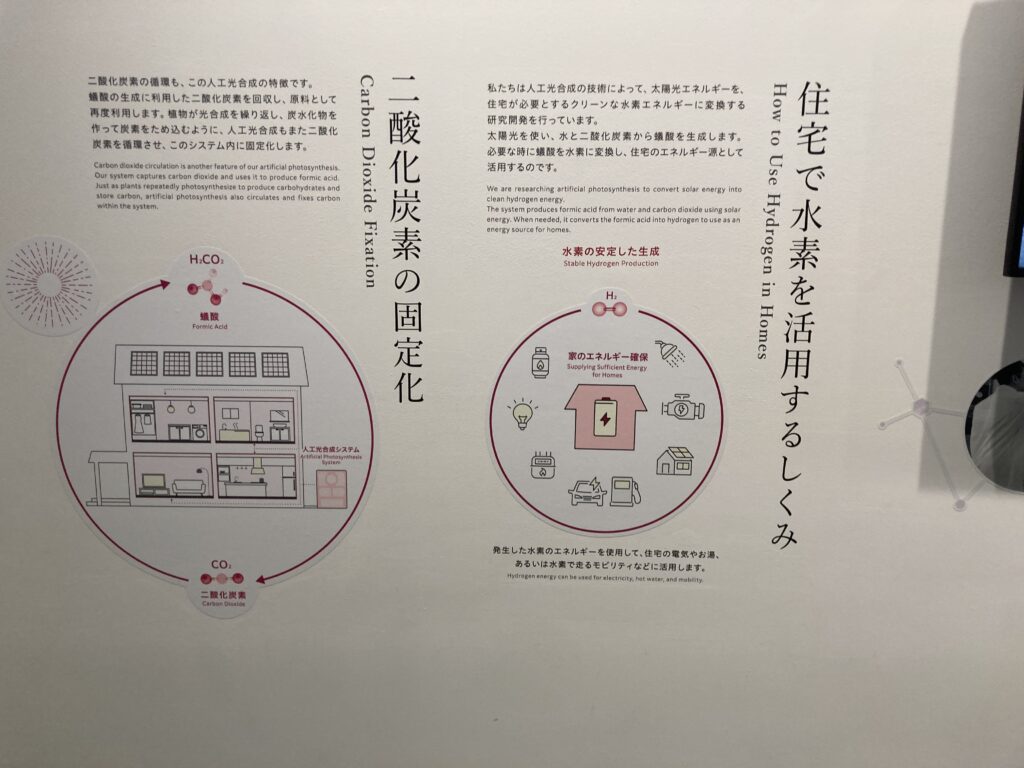
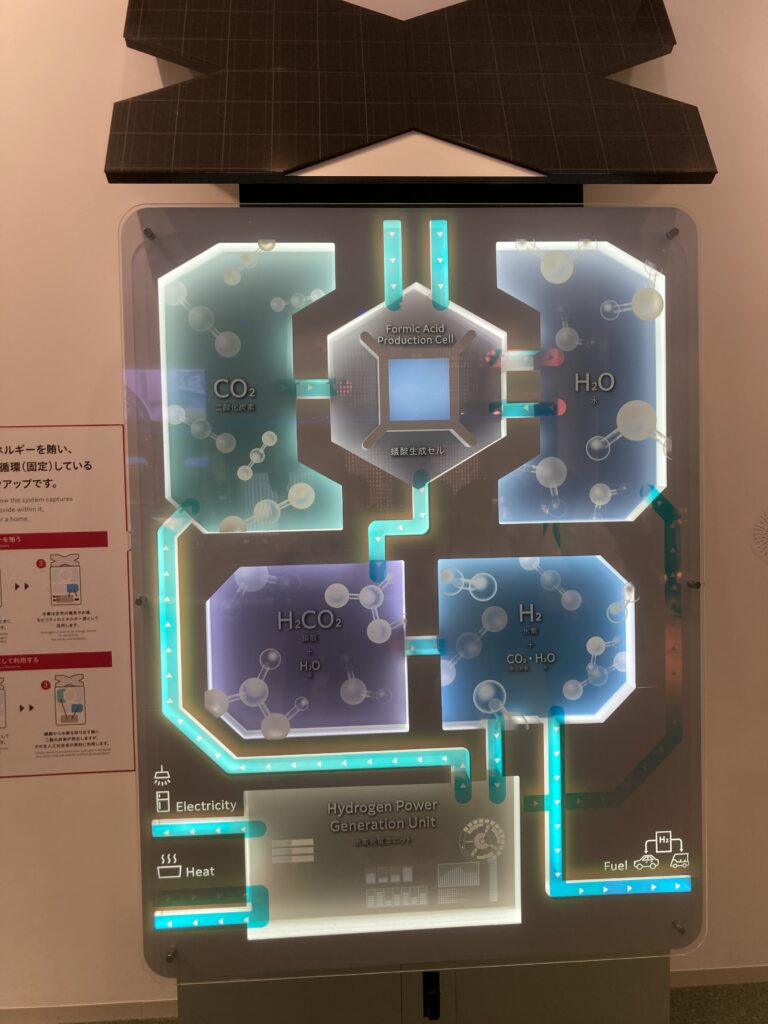
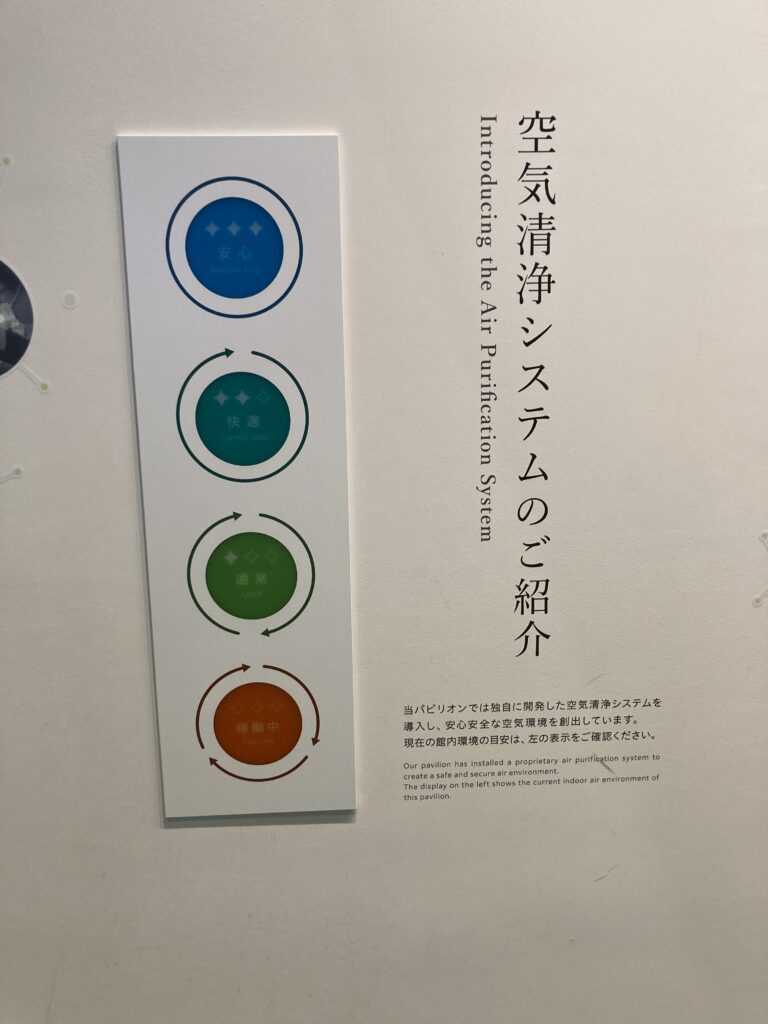


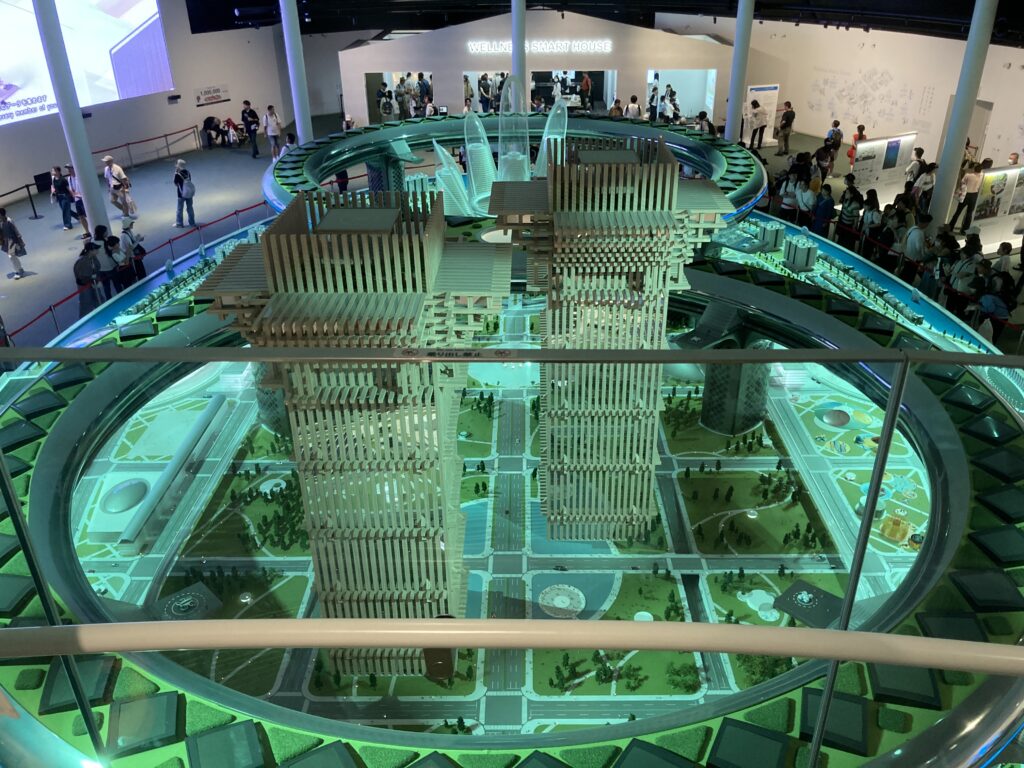
ガンダム館──久しぶりに味わう“勝負の快感”
X(旧Twitter)では、「ガンダム館は当日予約が取りやすい」と書かれていた。
だが、実際には簡単ではない。
予約開始と同時に3度のリロードを繰り返し、ようやく成功。
画面に「予約完了」と表示された瞬間、思わず拳を握った。
「やった……!」
高校野球でレギュラー番号を勝ち取った時のような高揚感。
最近の職場では、努力しても結果が形にならない。
だからこそ、この“勝負の世界”に勝つ感覚がたまらなく嬉しかった。
ガンダム館は、4つの部屋を順に進む構成で、
映像の迫力と演出の緊張感がすばらしい。
最後には、巨大なガンダムが地球を守る姿が映し出され、
観客はそのスケールに圧倒される。
外に出ると、背中越しにそびえるガンダムのシルエットが見え、
ガンダムをよく知らない私でさえ、思わず「ありがとう」と呟いた。
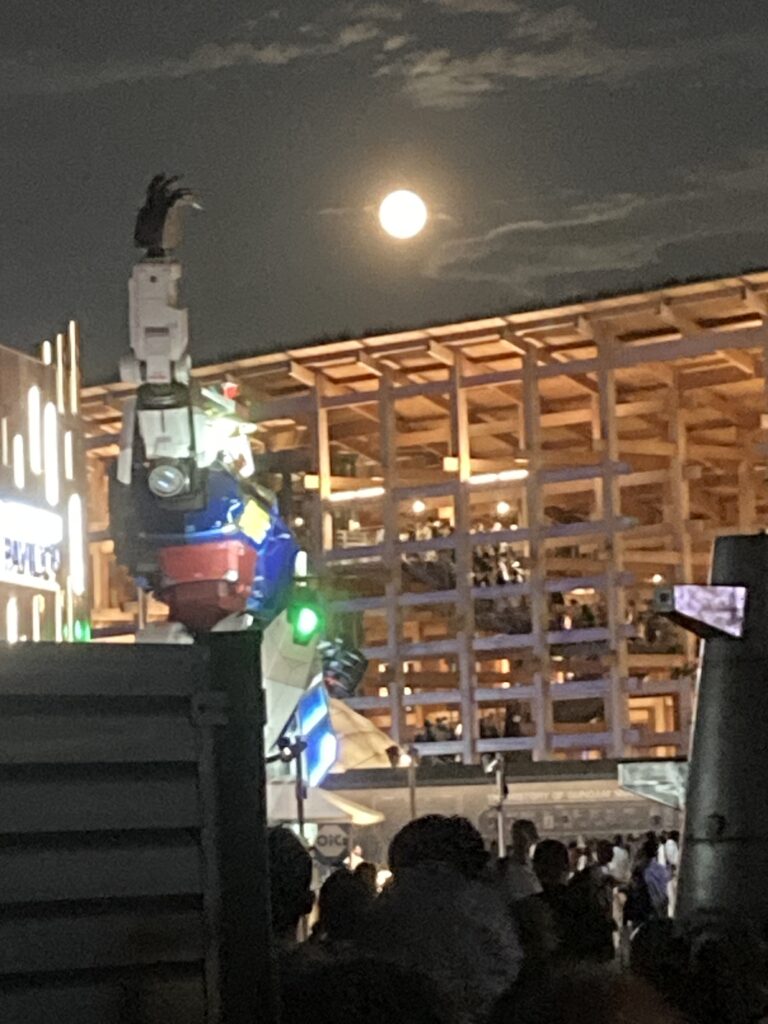





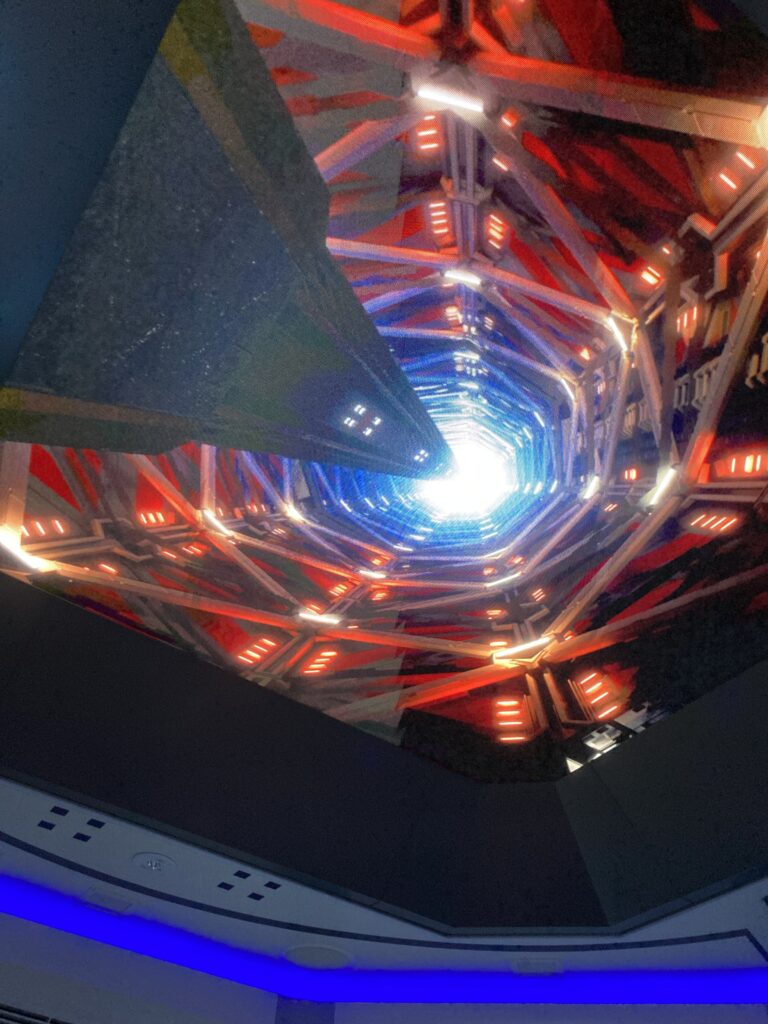




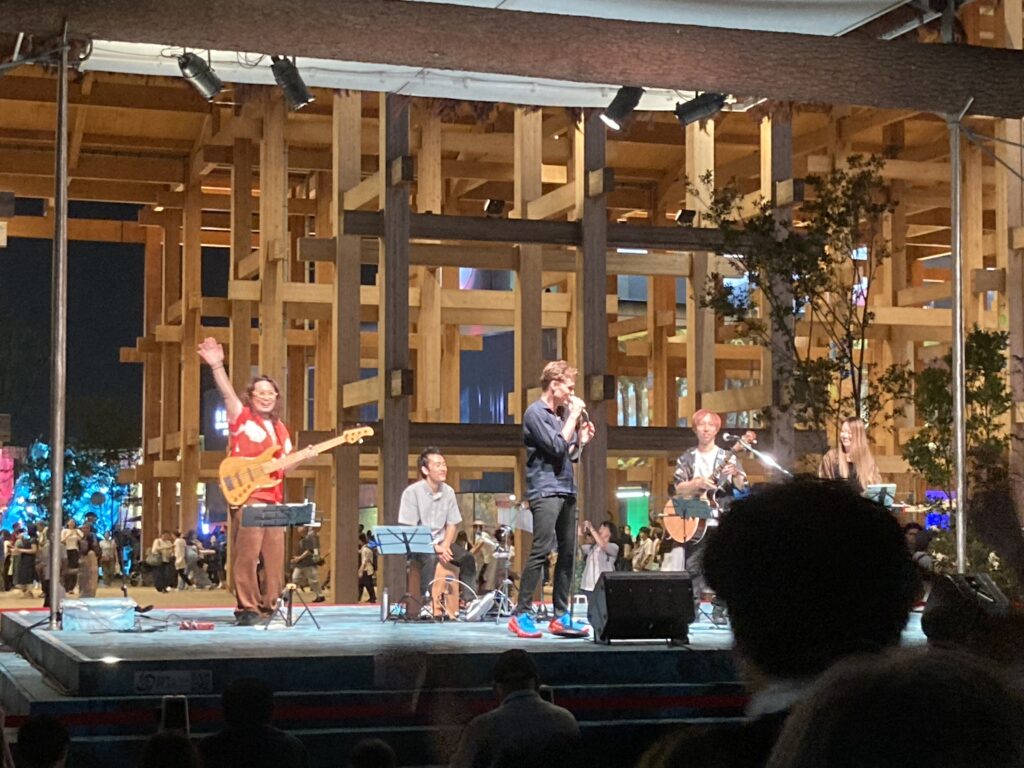
万博の“食”と、身体の限界
この日も、持参したおにぎり8個が活躍した。
並びながら少しずつ食べる作戦は功を奏したが、
外食エリアでは、相変わらず高価格に驚かされる。
バイエルンソーセージ5本480円を買い、
ベンチに座って残りのおにぎりを食べながら思った。
「空腹のときの食事ほど、美味しいものはない。」
野球部時代、練習後に食べた飯の味を思い出す。
あの頃と同じように、努力のあとに訪れる“報い”の味だった。
だが、長時間の滞在で体は限界を迎えていた。
水分を控えたせいで尿の色が濃くなり、めまいがする。
熱中症のサインだ。すぐに水を飲む。
するとまたトイレに行きたくなる。
人間とは実に面倒な生き物だと苦笑いした。
フランス館──芸術の都が見せる赤い糸
夜の帳が降りた頃、フランス館へ。
昼間は3時間待ちだったが、夜8時を過ぎると待機列は半分に減っていた。
ギリギリのタイミングで入場。
館内には、焼失したノートルダム大聖堂の守護像、ロダンの彫刻、
赤い光に照らされたダンス映像、鏡張りのヴィトンルーム、
樹齢2300年のオリーブの木——
芸術の都パリが誇る“再生と愛”の象徴が並ぶ。
テーマは「赤い糸」。
芸術が人と人を結ぶ力を、静かに語りかけてくる。
男性がアメリカ館にロケットの夢を見るように、
女性がフランス館で美と愛を見出すのも納得だった。

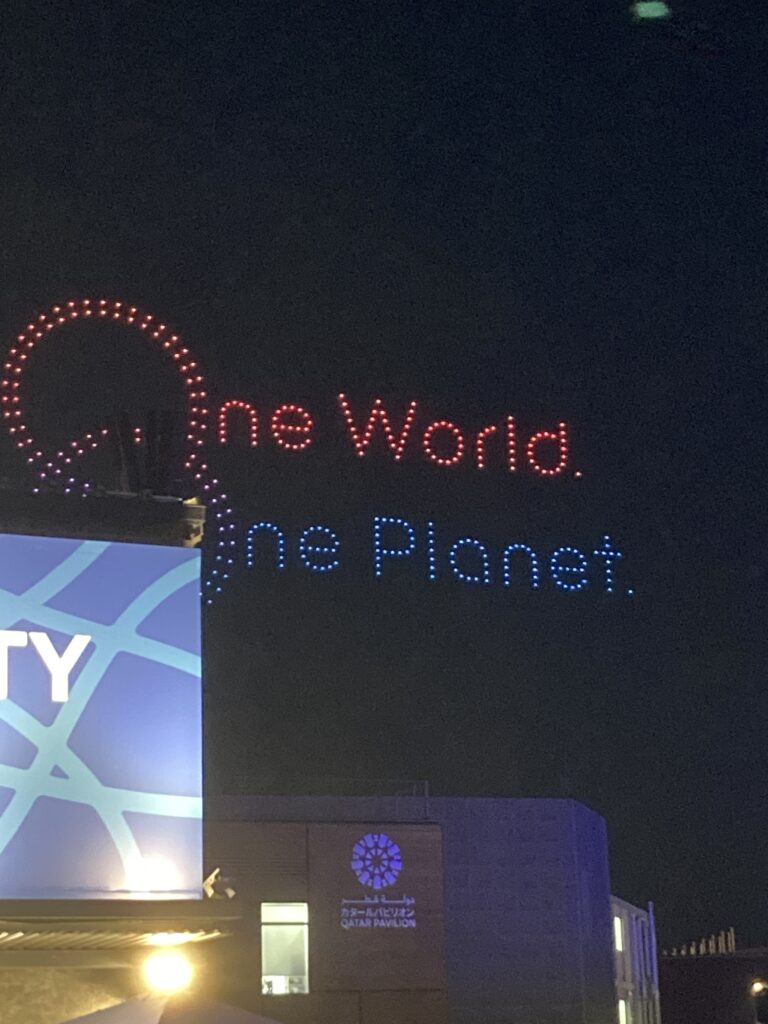
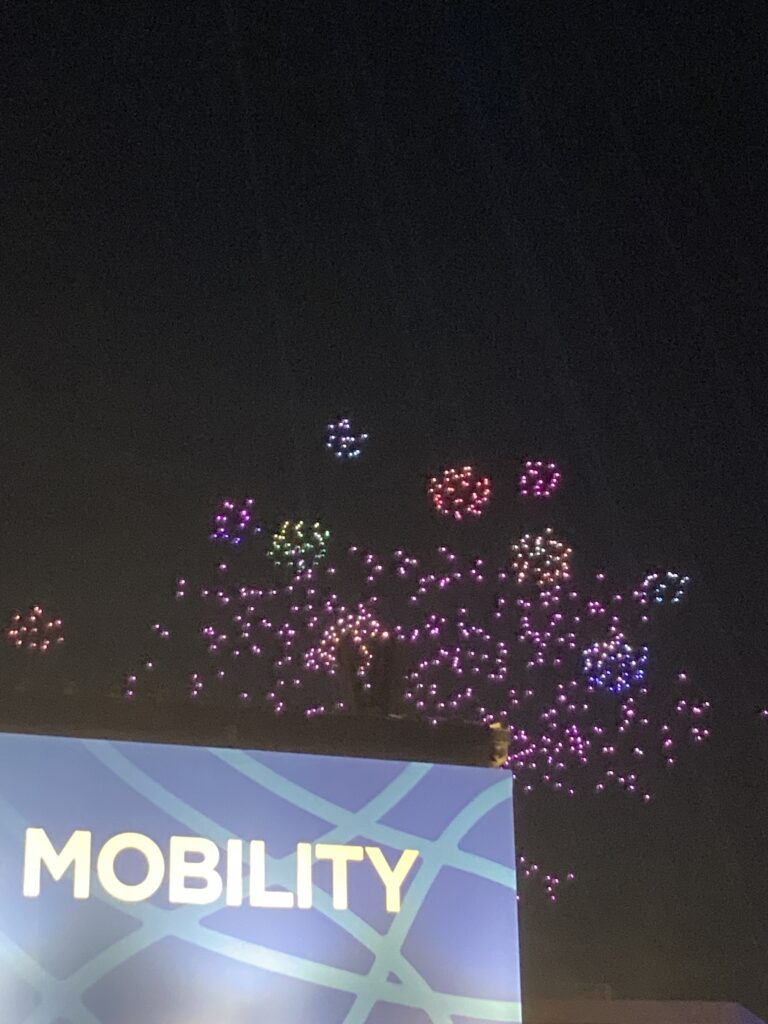





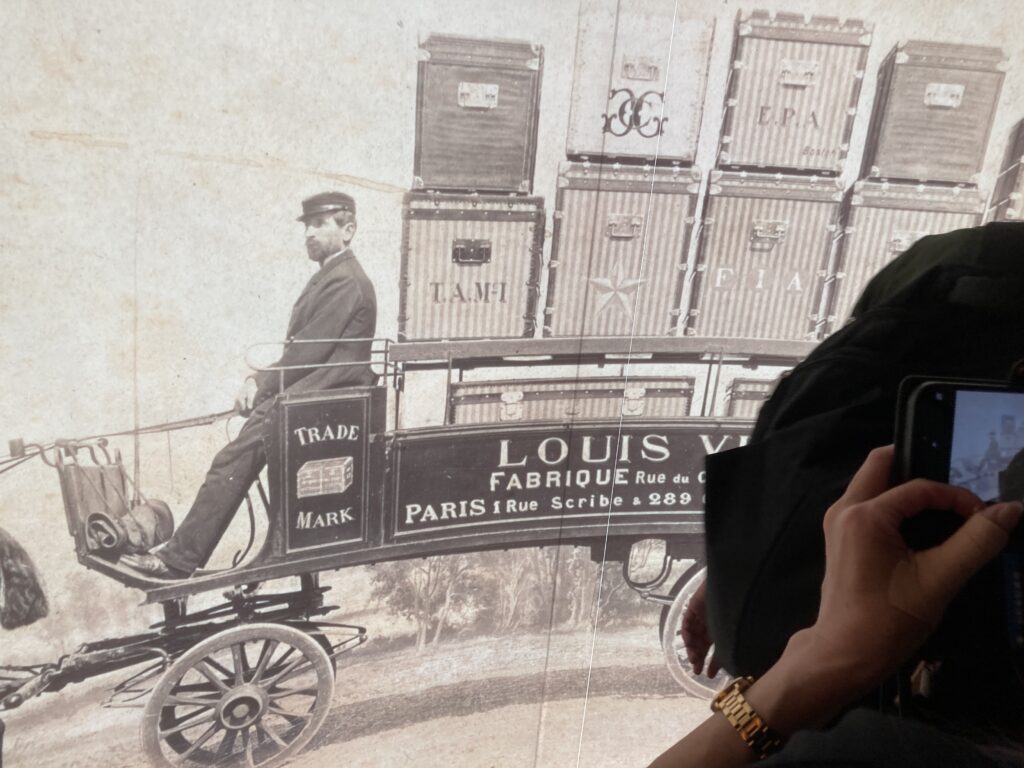


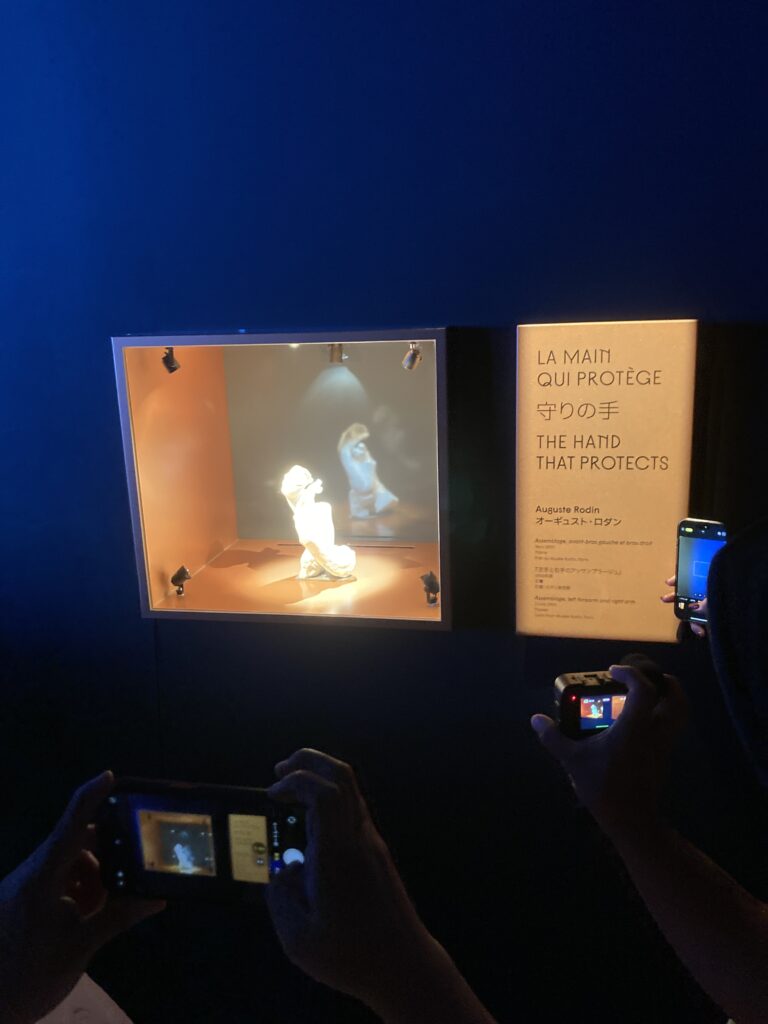


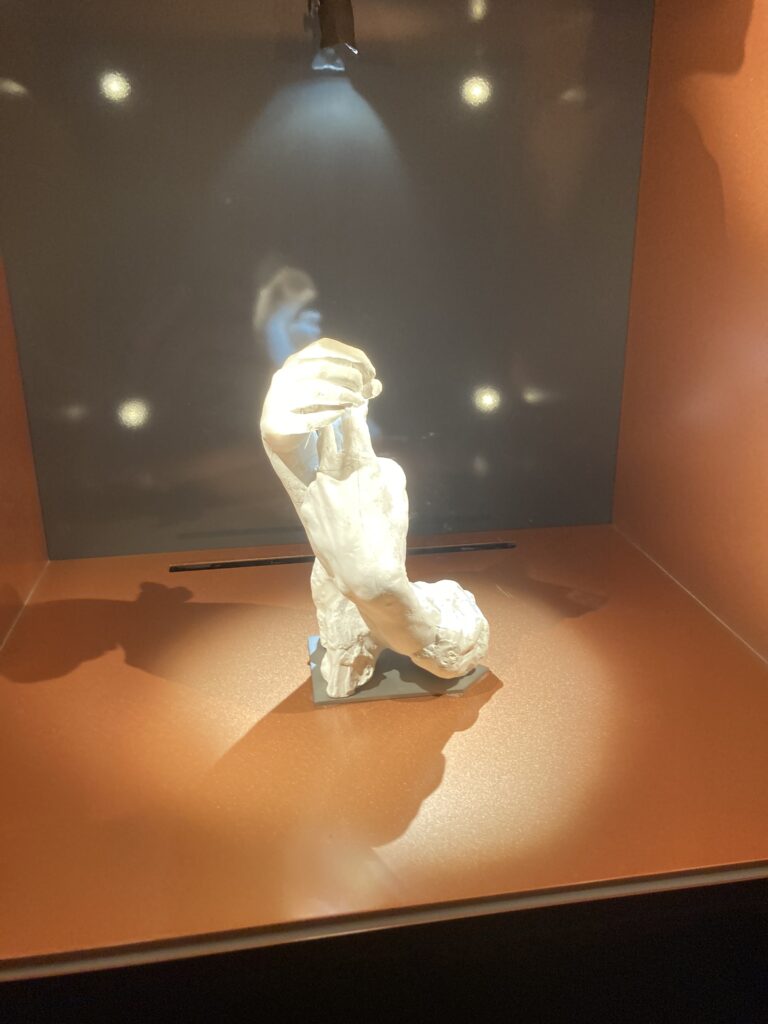

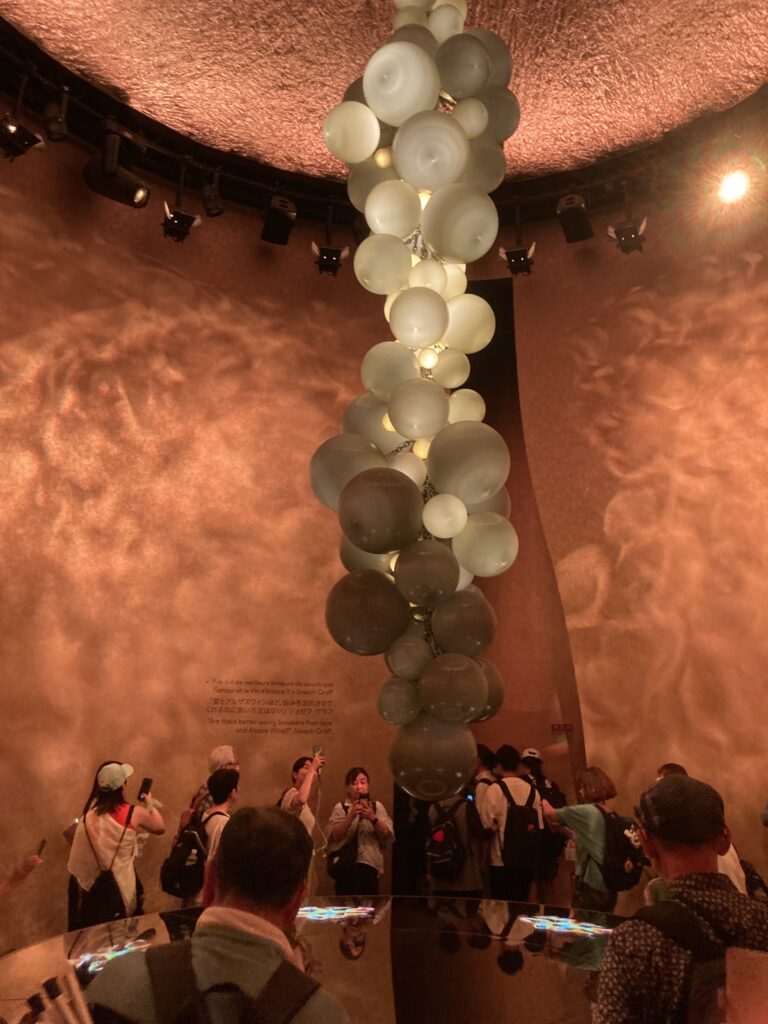
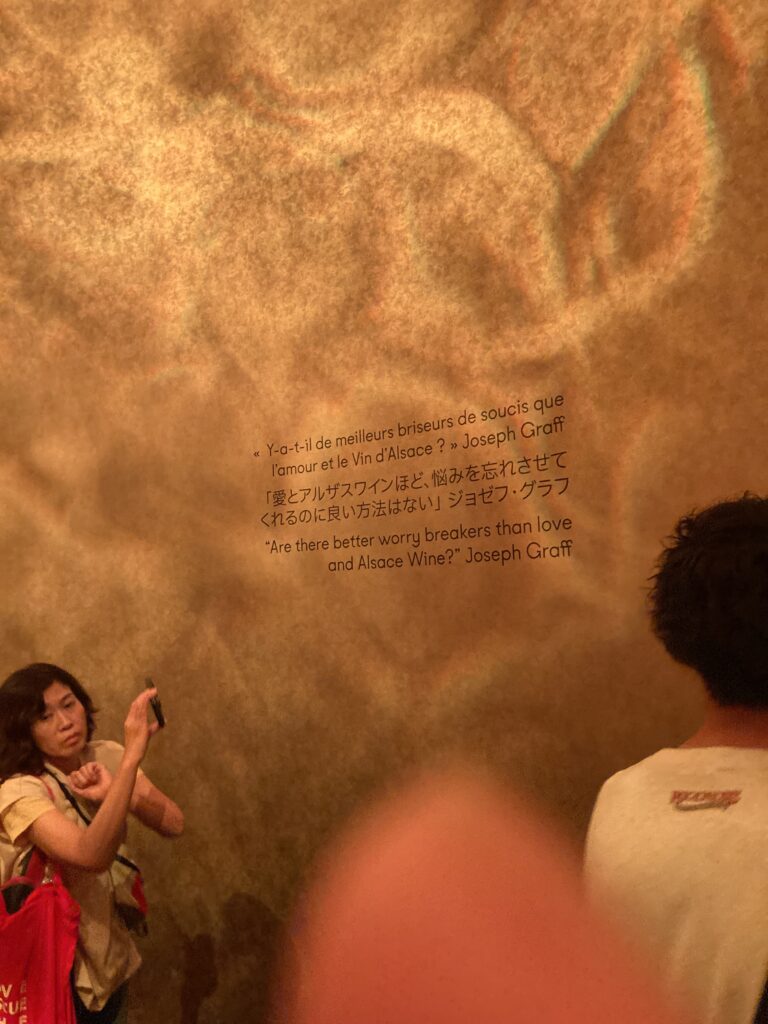
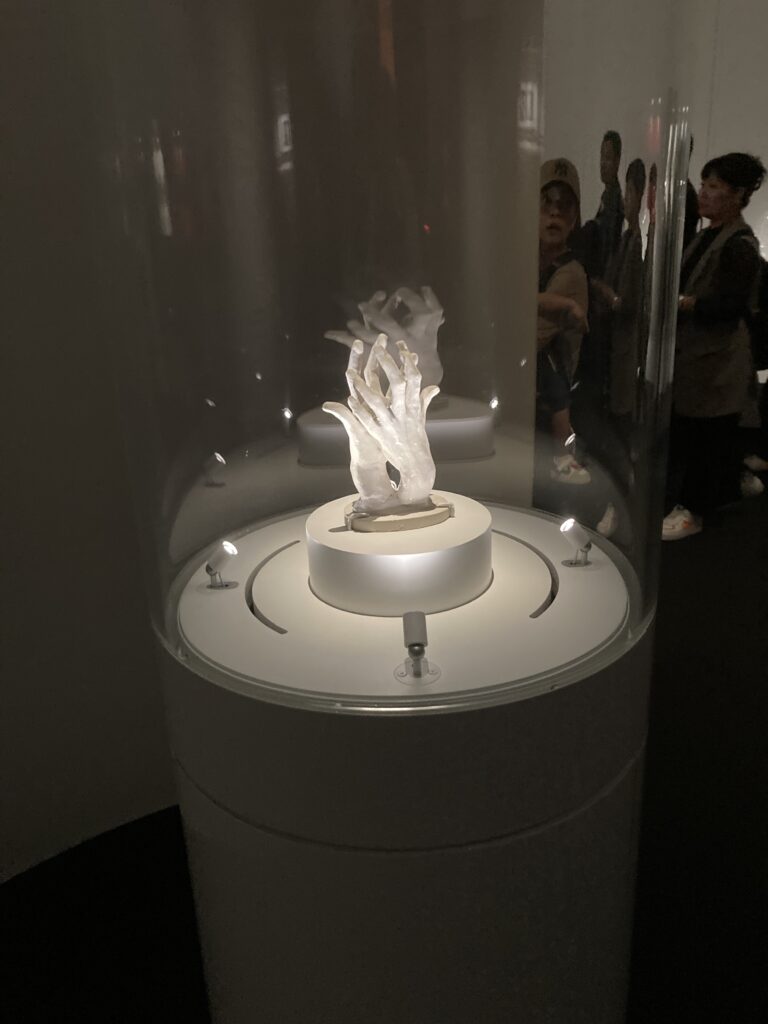



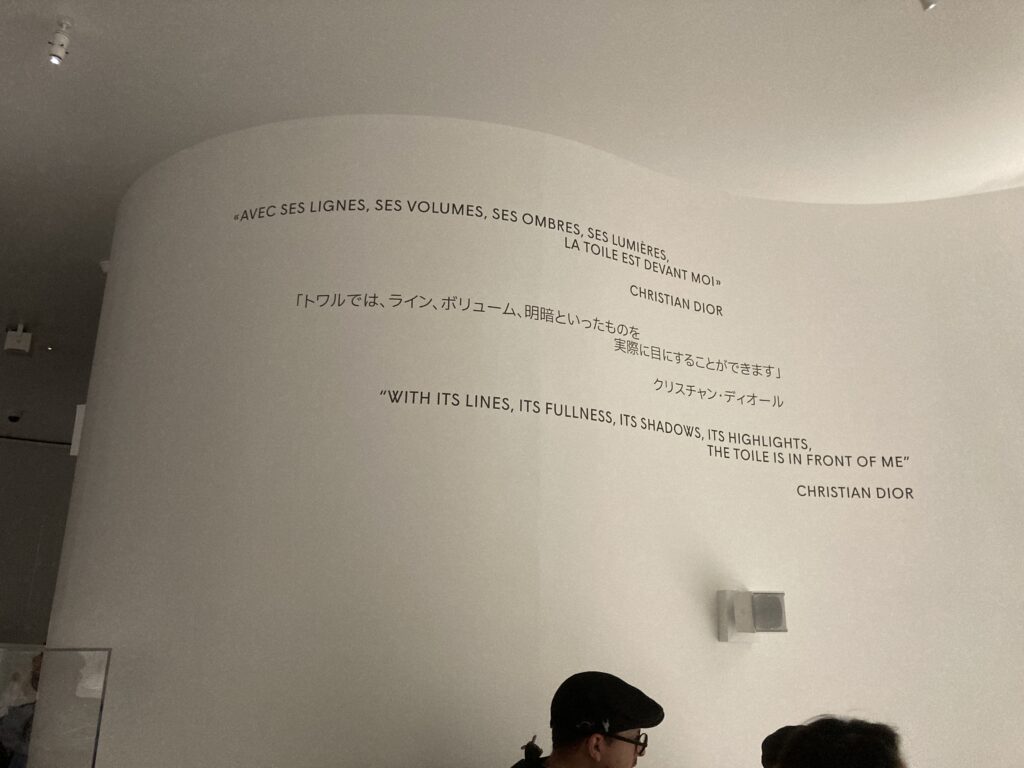

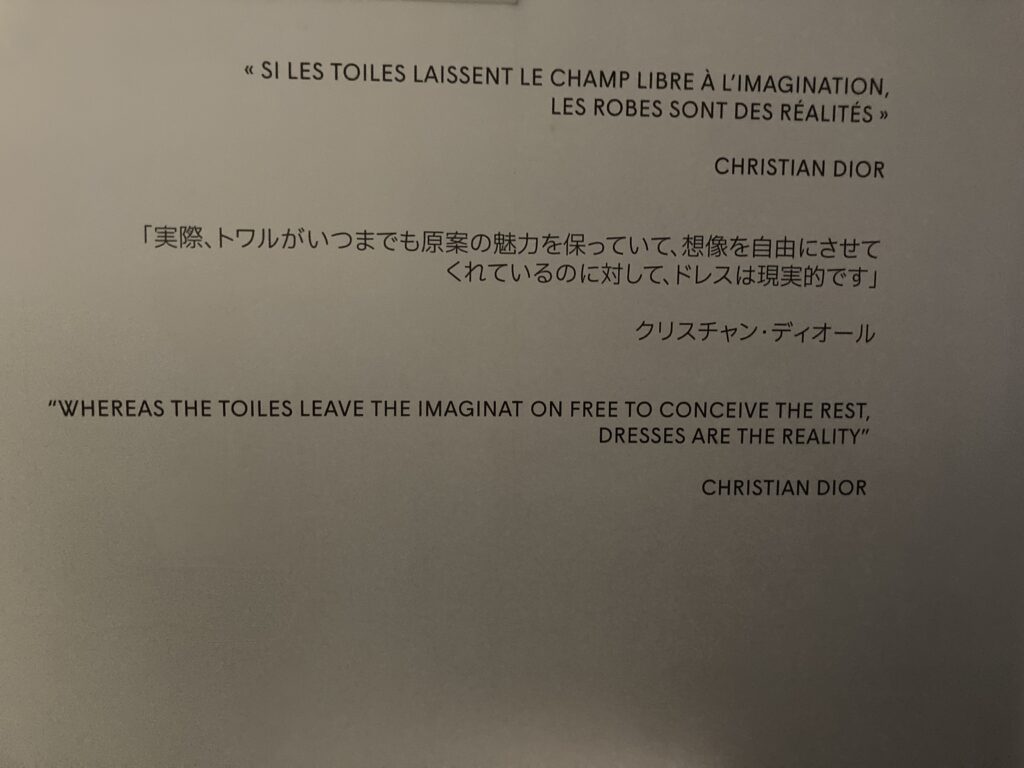
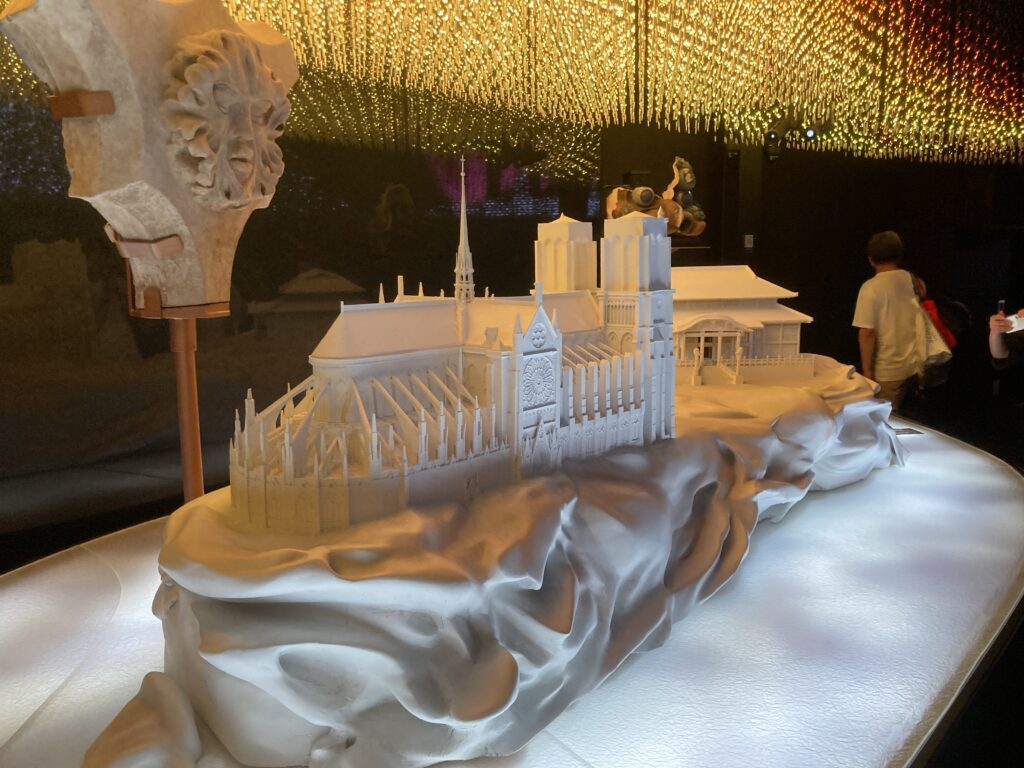
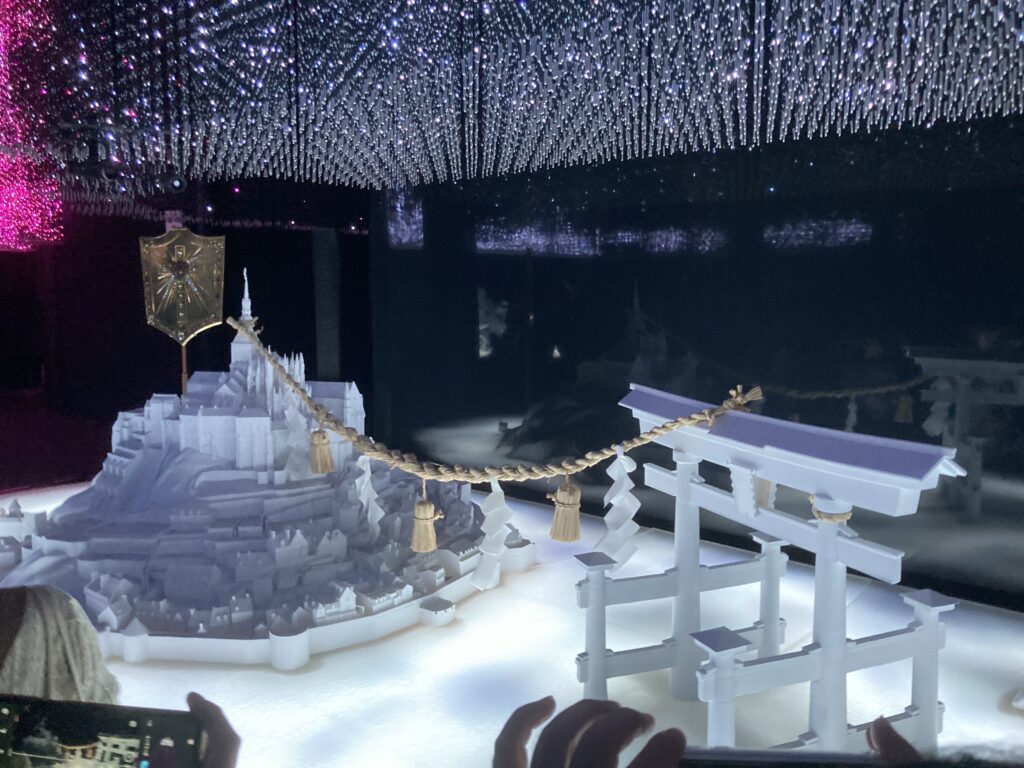

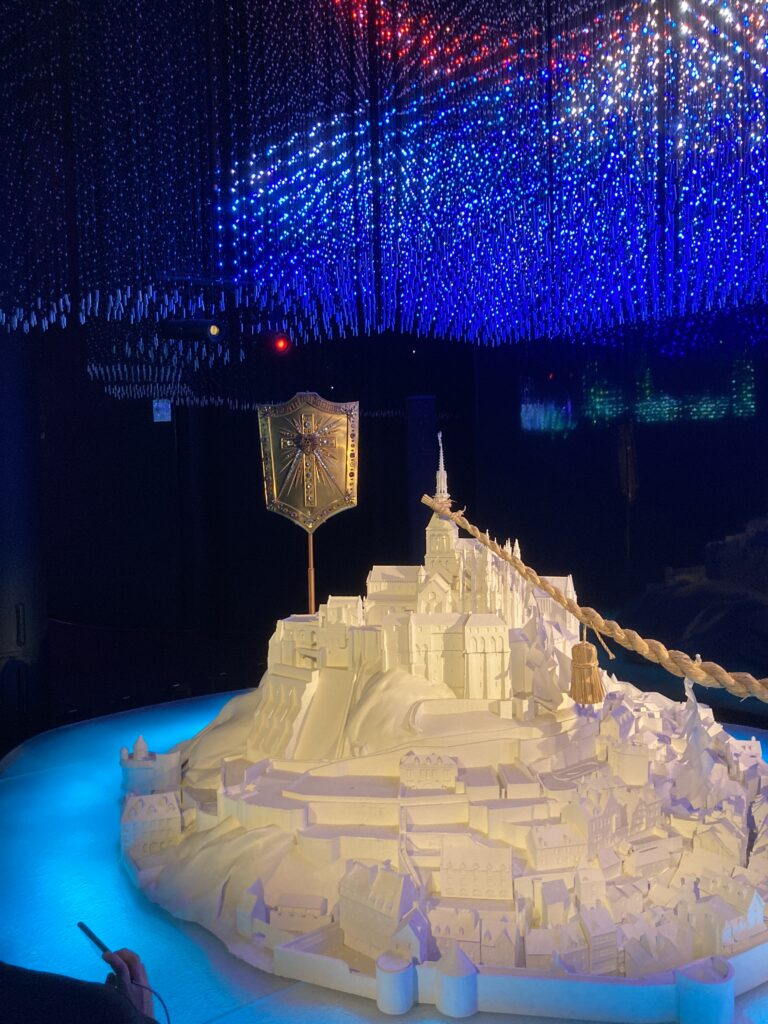


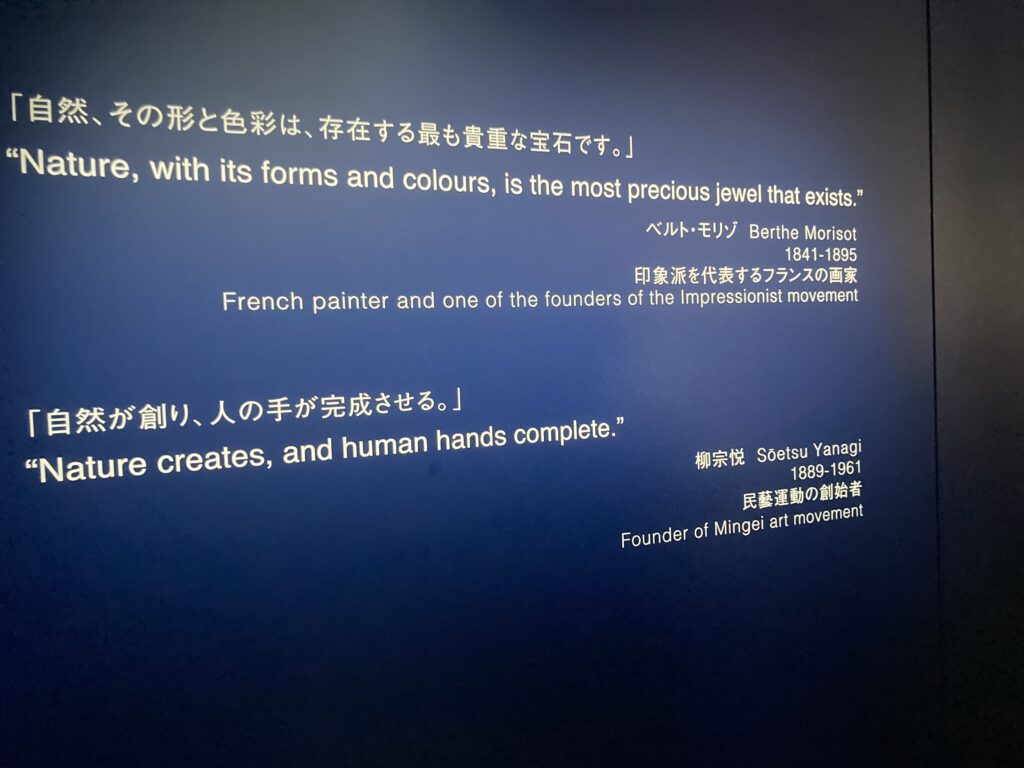


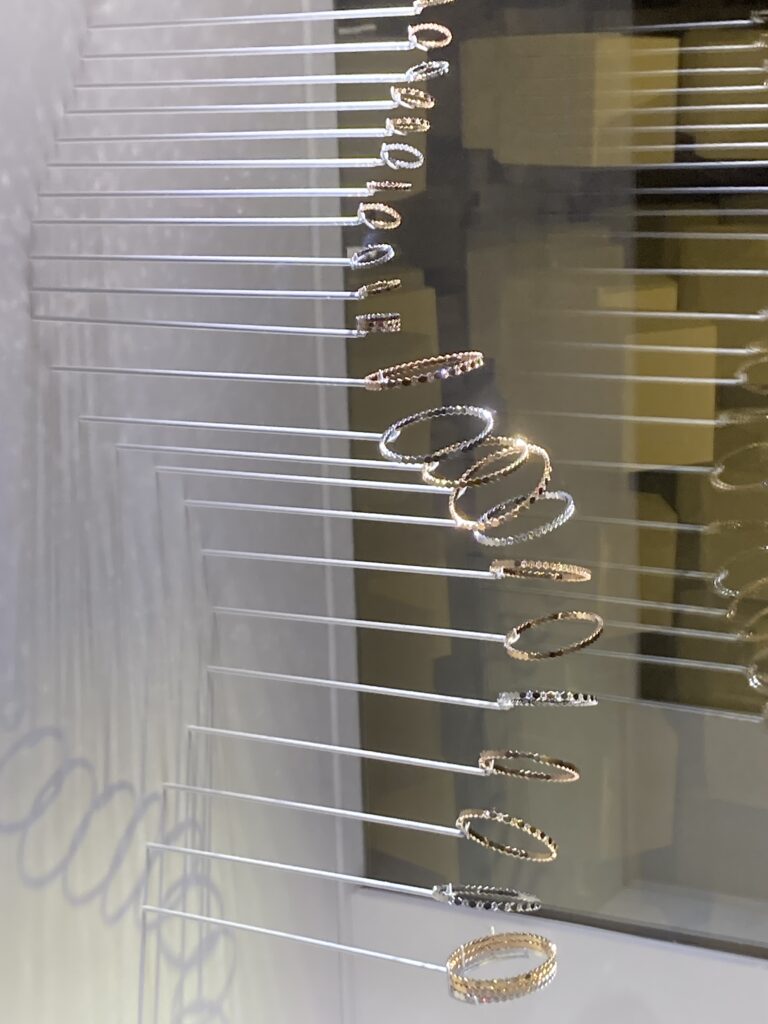

大屋根リング──夢洲の夜にて
夜9時20分。
私はエスカレーターを上り、夜の大屋根リングを一周しようとした。
パビリオンの光が水面に映り、幻想的な光景が広がる。
だが途中で警備員が「降りてください」と制止。
夢の時間が終わりを告げるようだった。
西ゲートに向かう途中、ポーランド館の前で楽器の音が響く。
戦争で失われた楽器を復活させるために演奏しているという。
通訳の言葉に耳を傾けながら、
人間の文化を“繋ぐ力”を改めて感じた。
日本館の前では、中秋の名月が大屋根を照らしていた。
多くの人がスマホを掲げ、月と建築を重ねて撮影している。
この光景の中で、私はふと思った。
「SNSに流れる写真の数々も、この一瞬の選ばれた美の断片なのだ。」
東ゲートを出て、弁天町の宿までの帰路を、静かに歩いた。↓大阪ヘルスケアの予約無しブースも、最後に見られました。
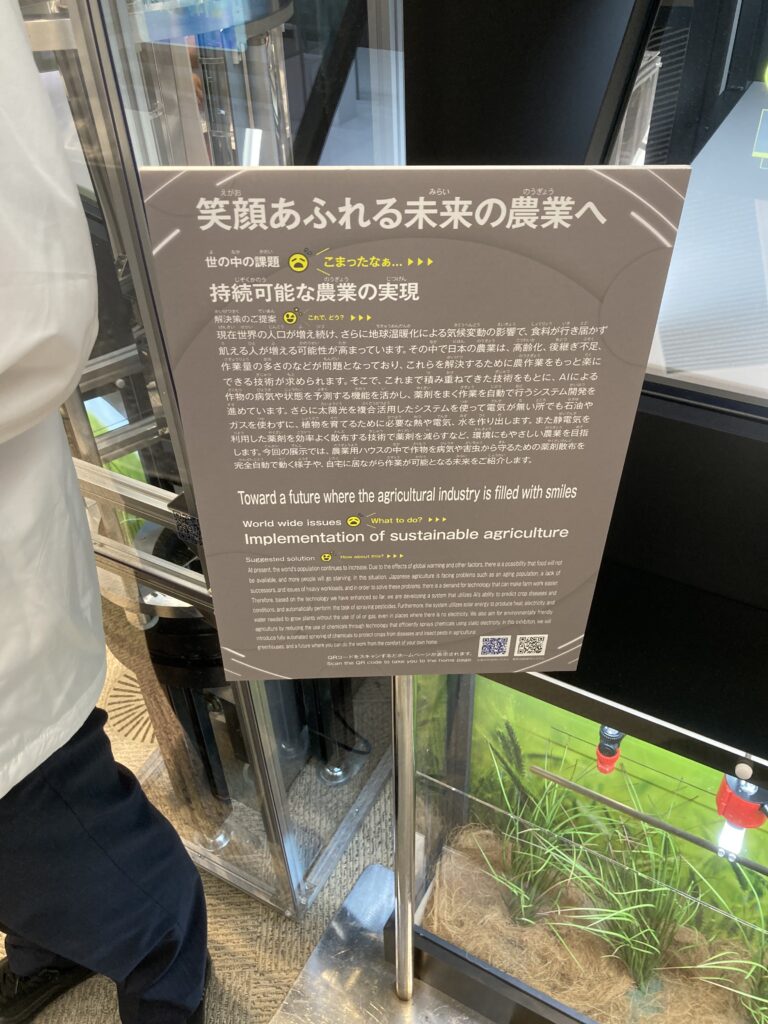


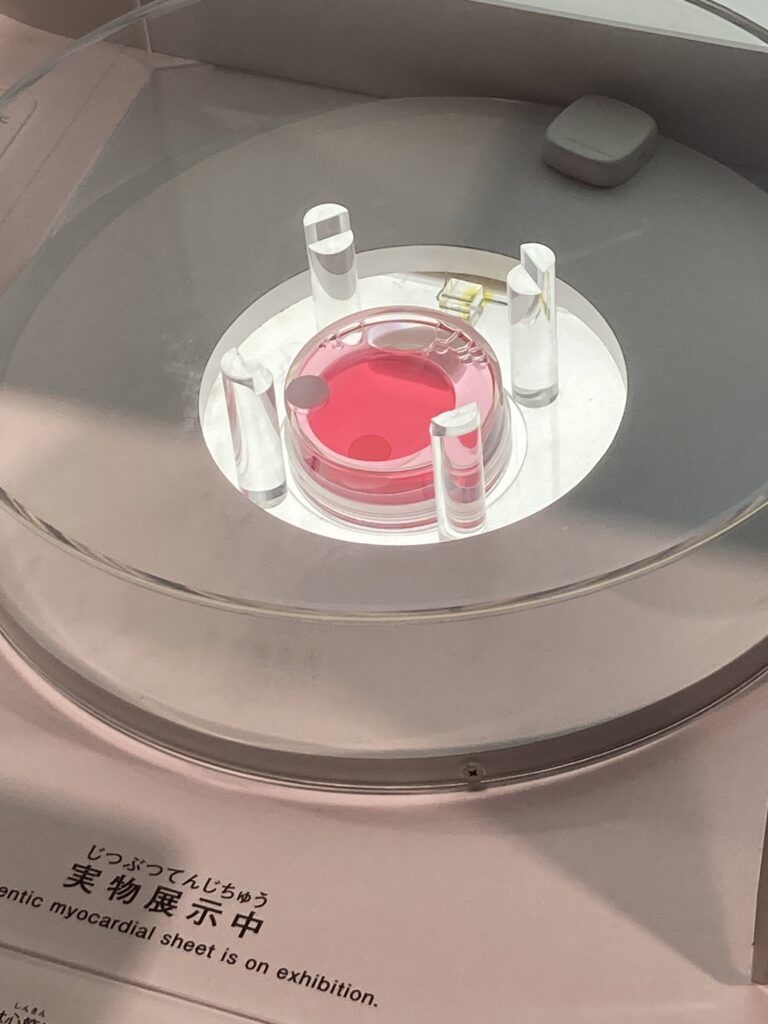

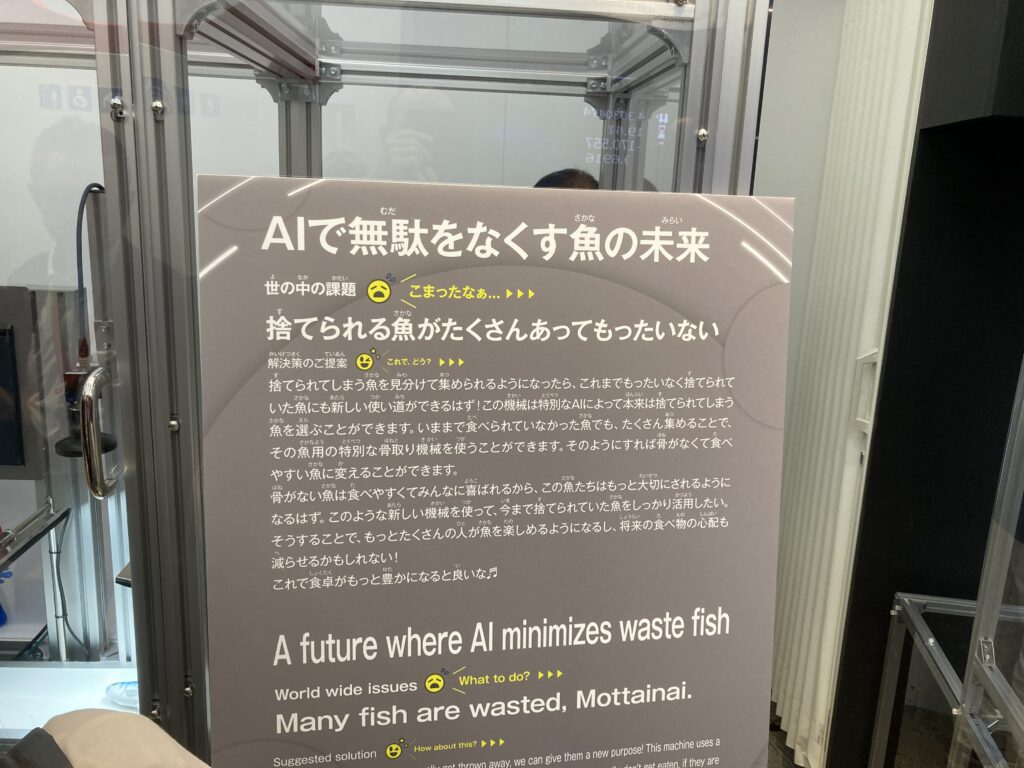
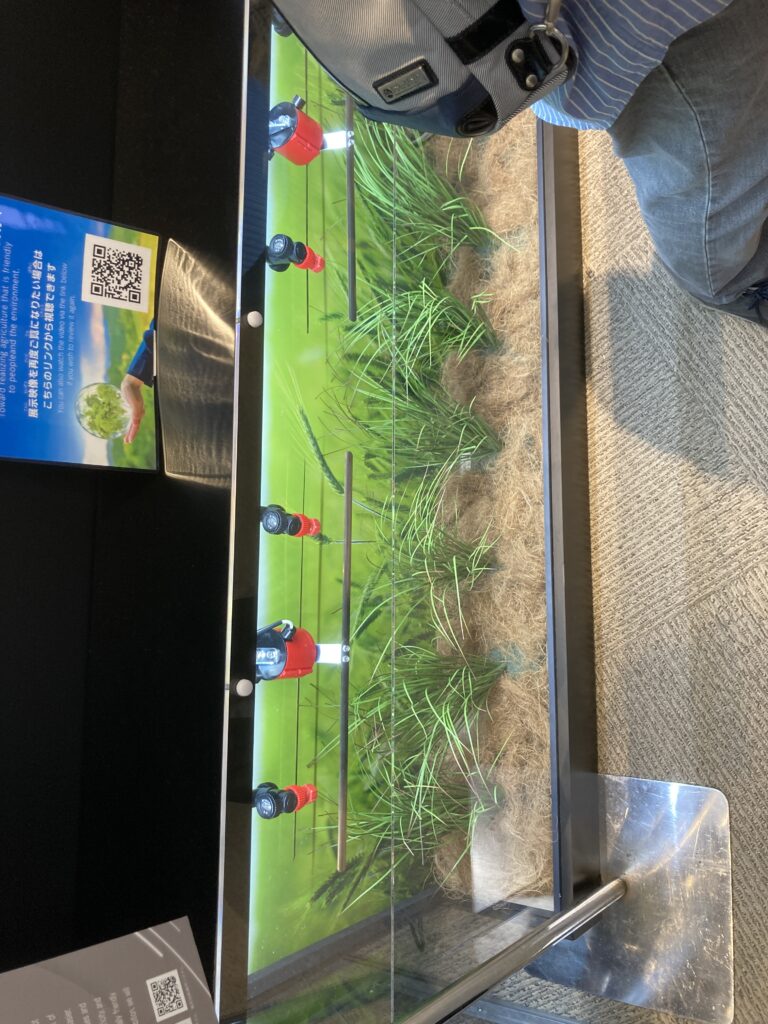
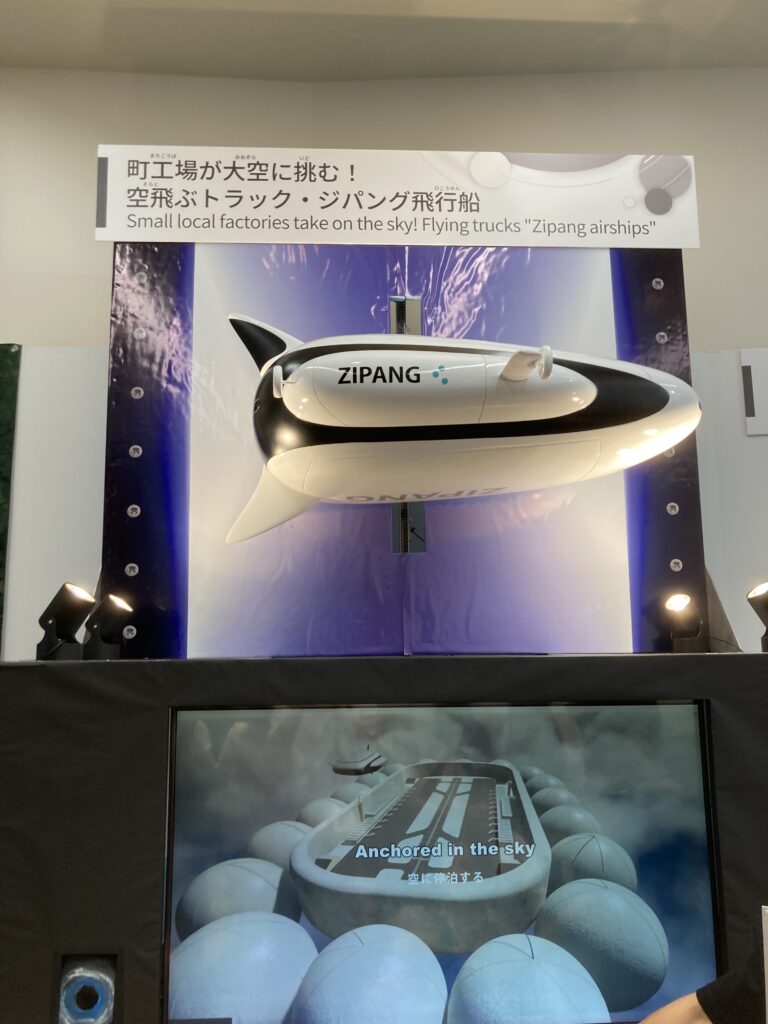







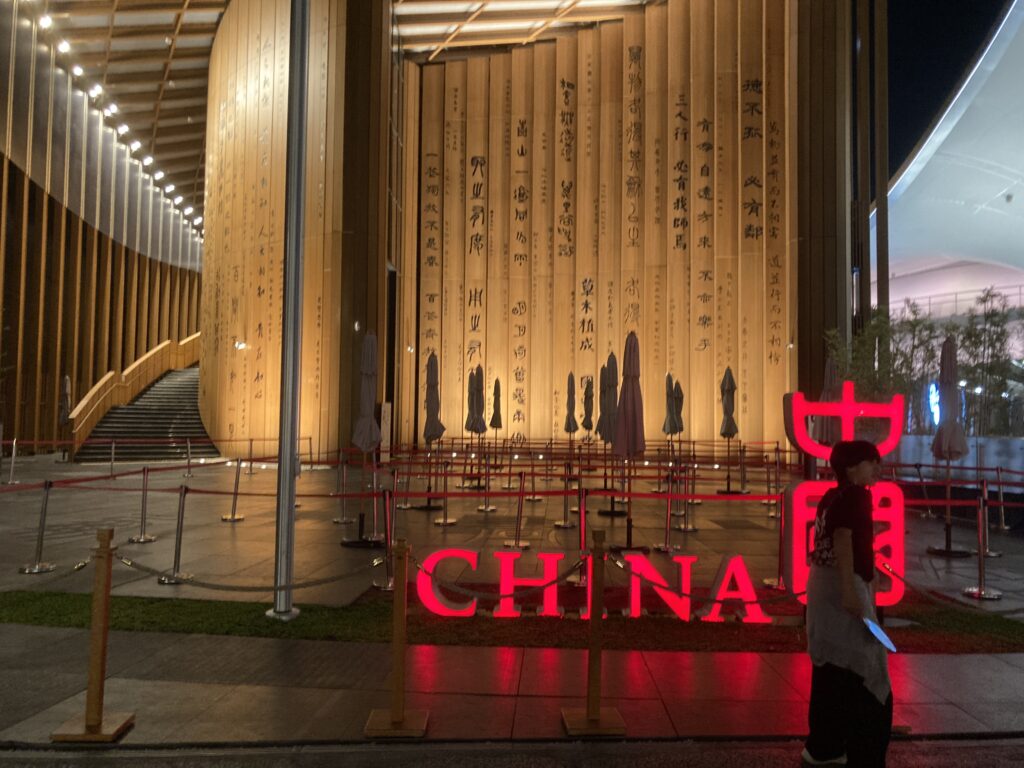
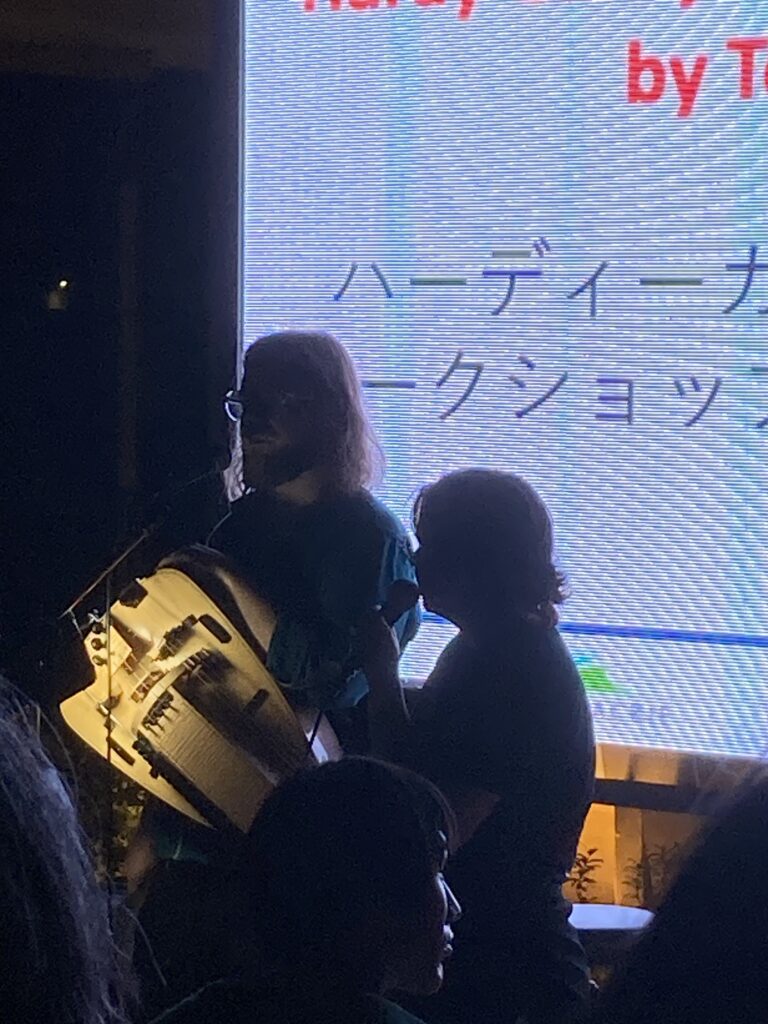












通天閣──商魂と人情の入り混じる街で
翌朝、通天閣へ向かった。
ビリケンさんを拝むために1時間待ち、
エレベーター待ちで30分、展望台までさらに30分。
大阪の商魂はここでも健在だ。
写真撮影1500円。ゲーム機やお土産販売が所狭しと並ぶ。
それでも、この混沌と商売っ気こそ大阪らしさなのだろう。
東京にはない、人間くさい逞しさを感じた。
↓串カツの名店「だるま本店」──有名人の色紙がずらり。




↓城下町のような通天閣界隈の風景。展望台からみえる大阪の市内。


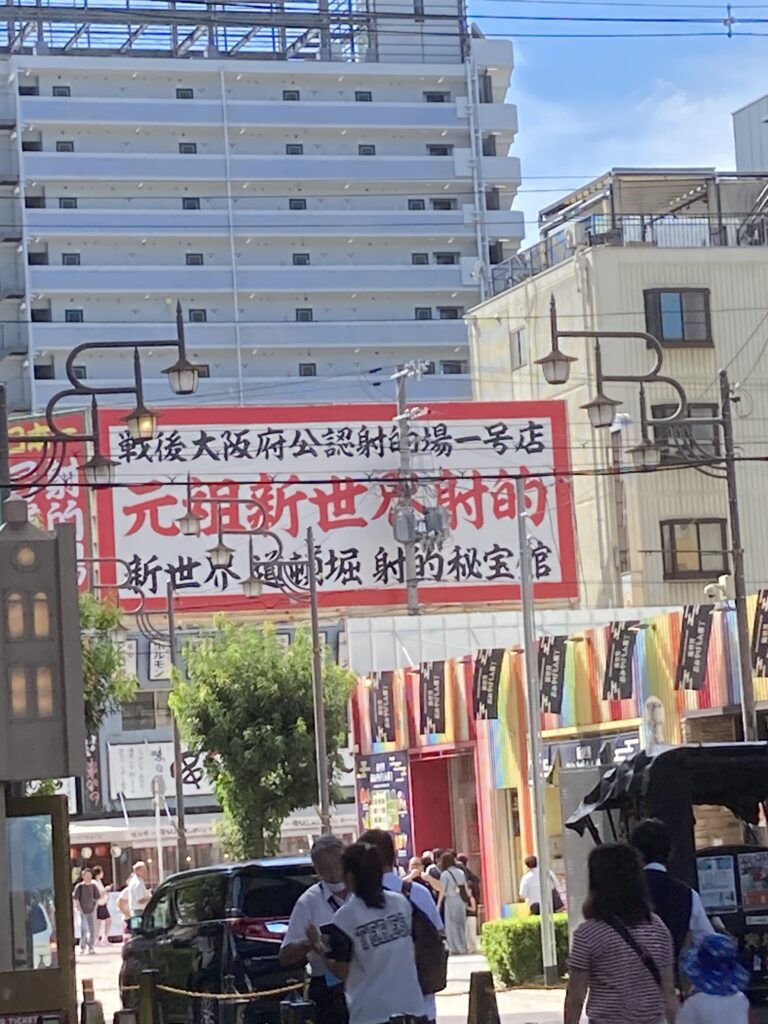




















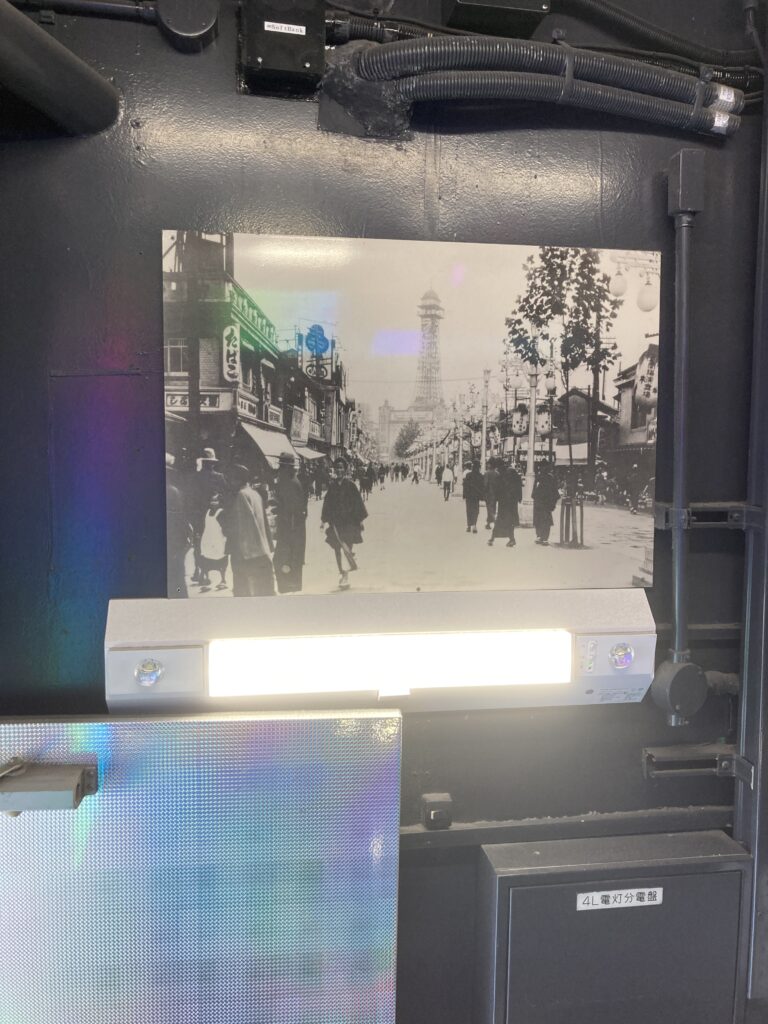


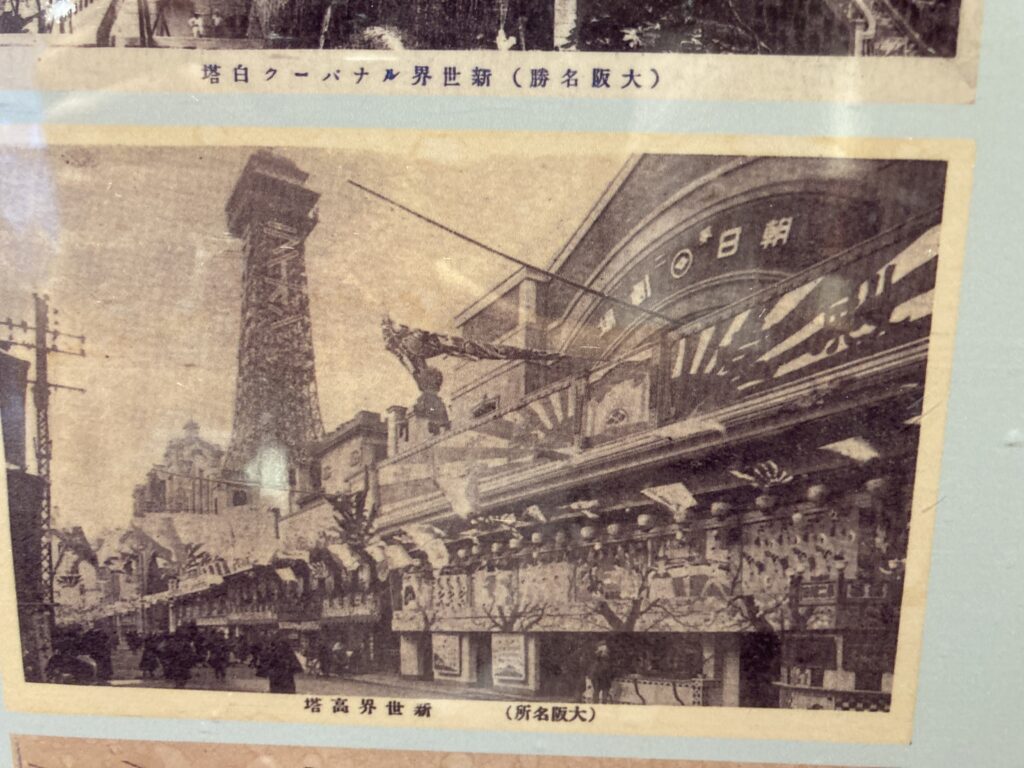
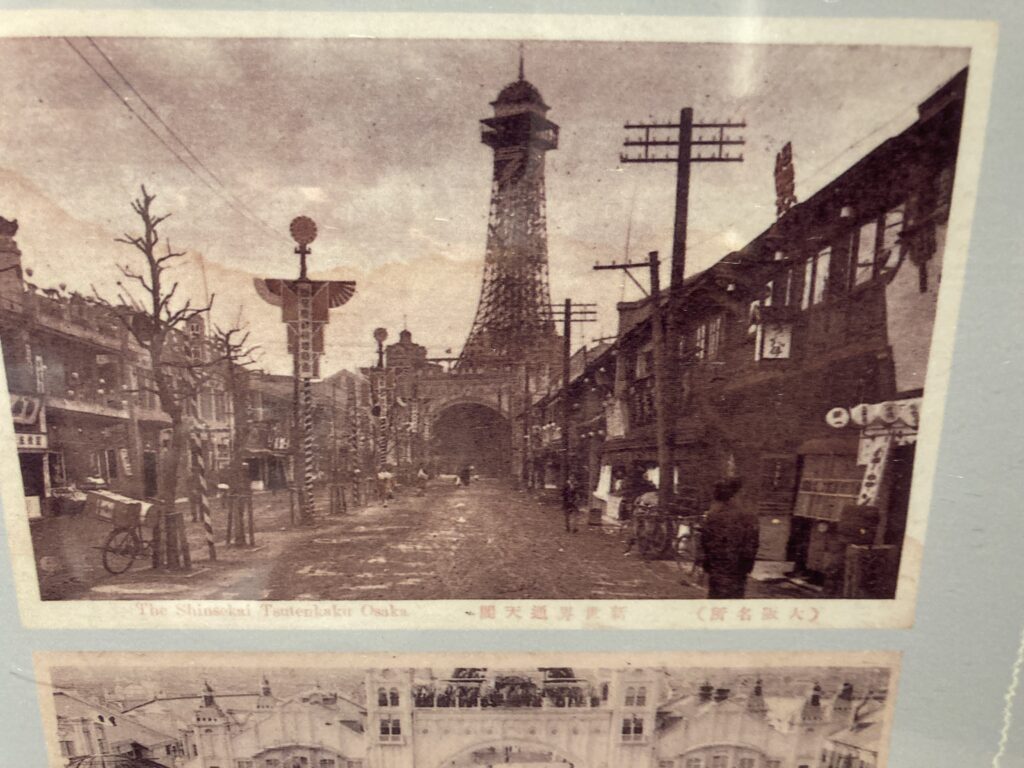

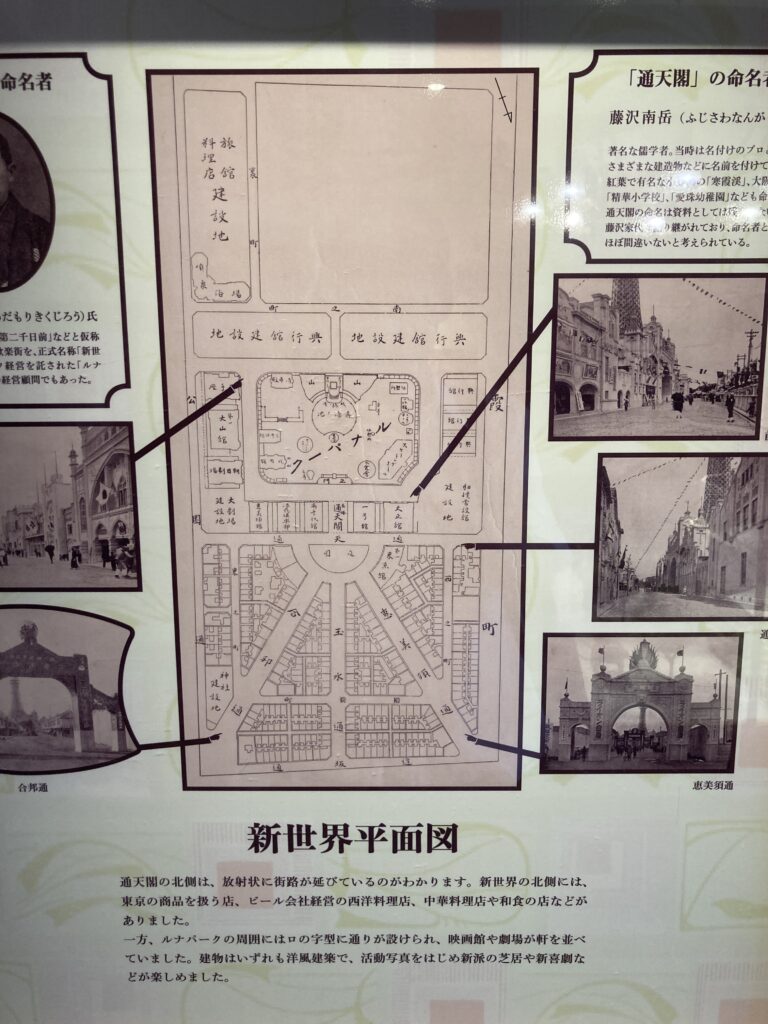
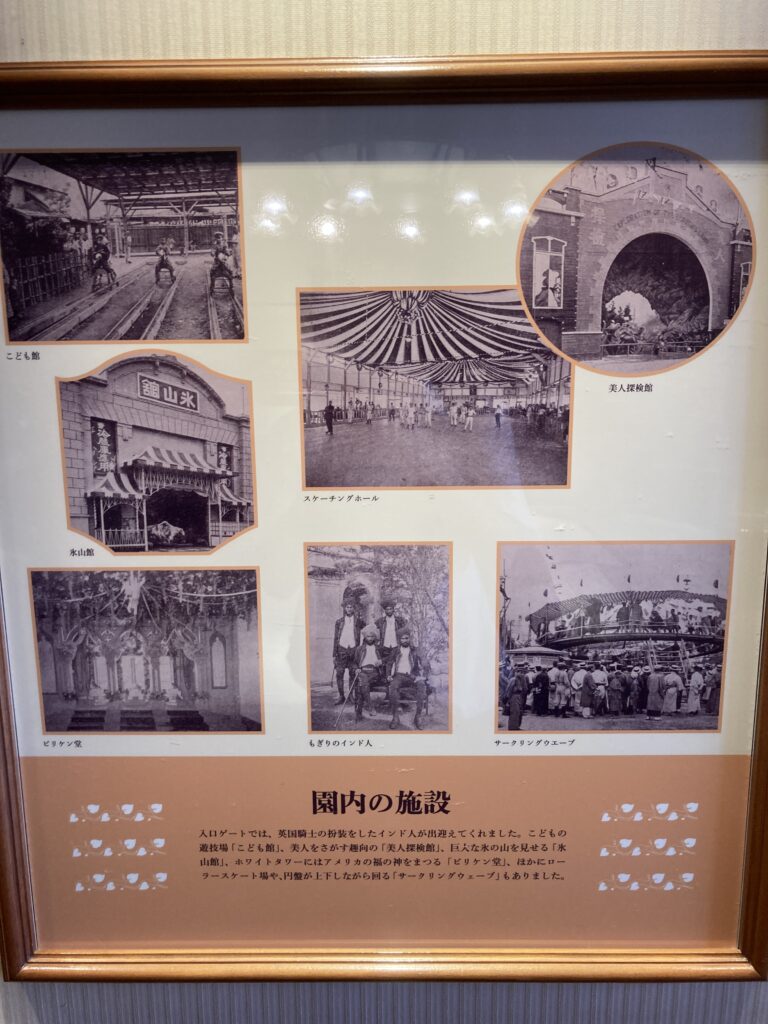
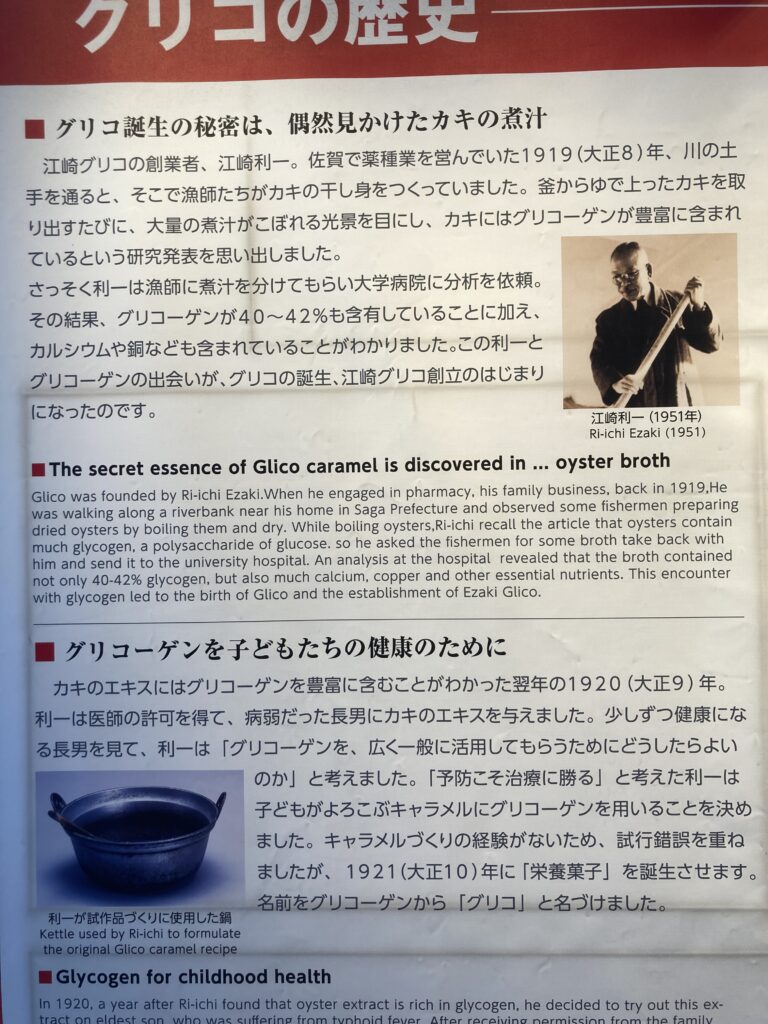
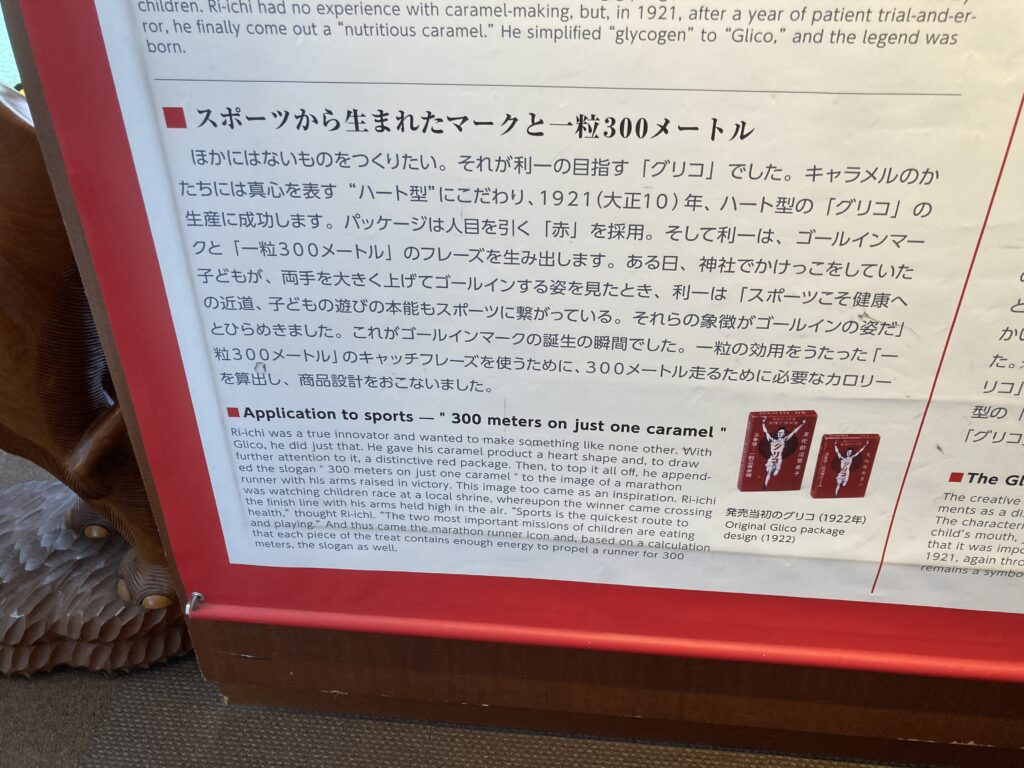






↓外国人観光客が殺到する包丁屋の活気。

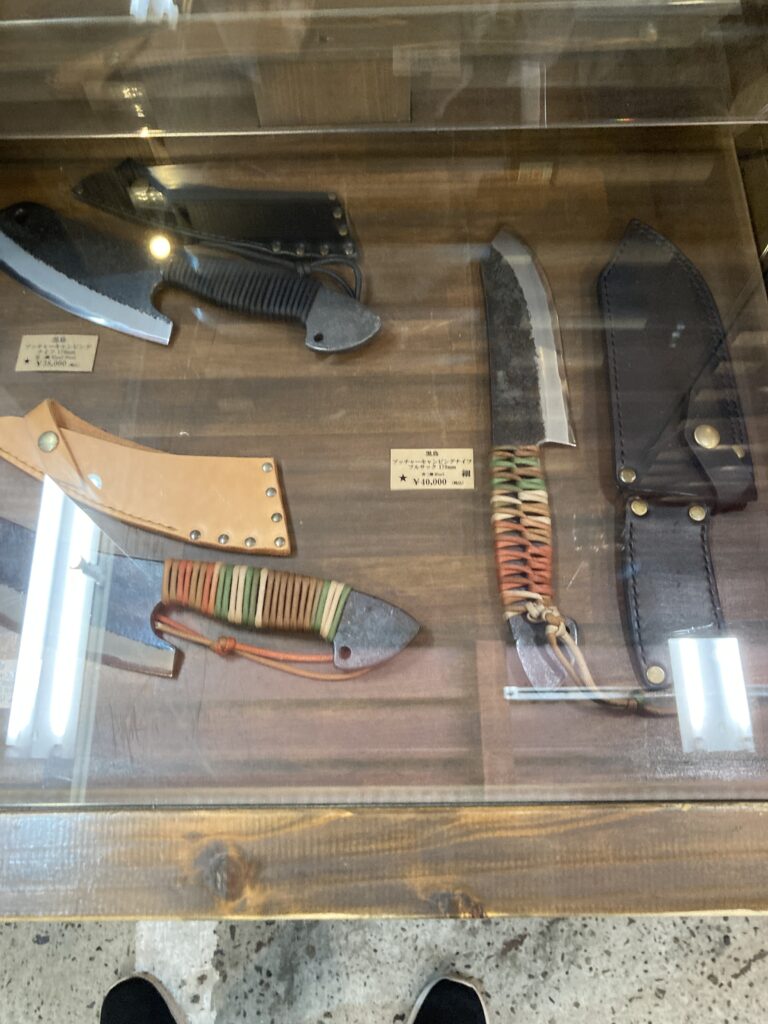

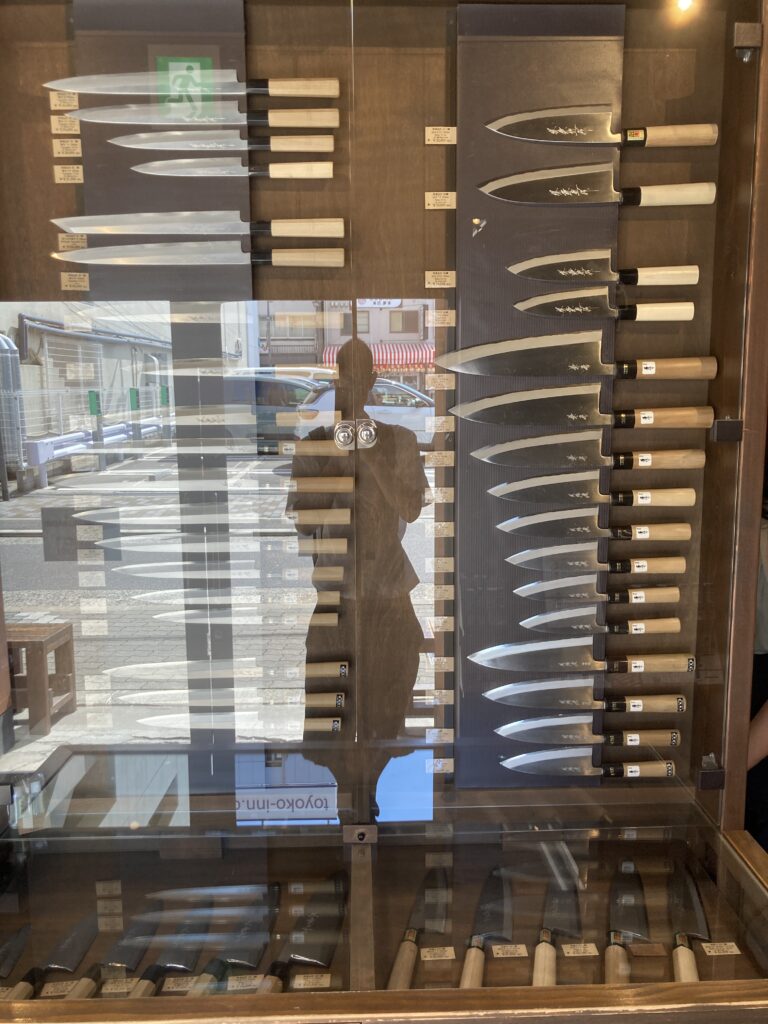


そして——
万博を歩き尽くした2日間。
朝3時半に始まり、夜9時半に終わるまで、私はひとりで歩いた。
けれど、決して孤独ではなかった。
人のやさしさ、文化の熱、自然の息吹。
それらが一つの「地球の鼓動」として胸に残った。
帰りの電車の窓に映る自分の顔が、少しだけ誇らしげに見えた。







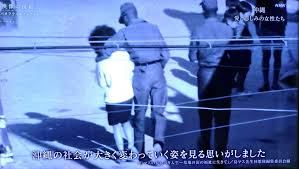



コメント