2025年の大阪・関西万博が、いよいよ閉幕まで残りわずかとなった。
私は、9月16日に訪れたときに20万人の人の波を経験している。
その教訓から、今回は「朝9時にトップ入場」を目指し、万全の準備で挑んだ。
午前11時を過ぎれば人の流れが膨張し、12時以降は身動きが取れなくなる——それを肌で知っていたからだ。
前回は、アメリカ館や「いのちの未来」を観たあと、油断してスシローでくつろいでしまい、
「未来の都市」に辿り着いた頃には、すでに人の渦に飲まれていた。
今回はその反省を踏まえ、X(旧Twitter)で情報を収集し、
「最短動線で効率的に回る」戦略を練り直した。
西ゲートへ──午前3時台のタクシー戦争
朝3時に起床。
3時35分に予約していた「タクシーGO」が、ぴったり時間通りにやってきた。
運転手は大阪弁全開で、「大屋根リングは2025メートルあるんやで!」と教えてくれた。
さすが大阪。豆知識までサービス精神旺盛だ。
ただ、彼は午前5時で勤務終了らしく、通行止めにぶつかって少し焦っていた。
西ゲート前では、すでにタクシーの列ができており、「4時半までは開かへんで」と警備員が叫ぶ。
運転手が「東ゲートまで回るか? メーター上がるけど」と気遣ってくれたが、
私はXで仕入れた最新情報で、4時半以降にしか進入できないルールに変更されたことを知っていた。
そのため、逆に運転手へ説明できたのだ。
情報が命を救うとはこのこと。
知らずに行っていたら、今日一日のプランは崩壊していただろう。
夜明け前の行列──“ガチ勢”たちとの静かな連帯
4時40分、車を降りると、まだ空は群青色。
西ゲート前には、すでに長蛇の列ができていた。
私は20番目前後。両隣は静かで落ち着いた人たちだった。
私はトイレが近く、2度離れたのだが、その間、隣の強面の男性が
「バッグ持っとくで」と笑ってくれた。
彼の優しさに驚くと、隣の女性も「気にしないでください」と微笑んだ。
聞けば、彼女は万博初体験で「イタリア館を見てみたい」と言う。
私は「つじさんの万博初心者マップ」を2枚持っていたので、1枚を渡した。
「ありがとうございます!」と満面の笑み。
朝焼け前の空気の中で、見知らぬ人に小さな善意を渡すことの尊さを、改めて感じた。








8時52分、入場──人生最良の朝
開門と同時に進み、8時52分に入場成功。
パソナ館の列に並びながらスマホで当日予約を試み、見事「住友館 13:50」を確保!
画面に「予約完了」と出た瞬間、全身が熱くなった。
この上ない達成感。まるで試験に合格したようだった。
パソナ館──鉄腕アトムが語る「廃墟の美」
パソナ館のテーマは「いのちの再生」。
iPS細胞を用いた心筋シートが、自律的に動く様子を目の前で見た時、
科学が“魂”に近づいているように感じた。
映像展示では、地球が荒廃していく様子と、その後に芽吹く緑が描かれていた。
美しい世界が、一瞬で廃墟へと変わる——その瞬間に私は思った。
「究極の美は、滅びの中にある」。
三島由紀夫の言葉が脳裏をよぎった。
写真を撮ろうとしたが、映像は一瞬で切り替わってしまった。
刹那的な美を残すことはできなかったが、心には深く刻まれた。
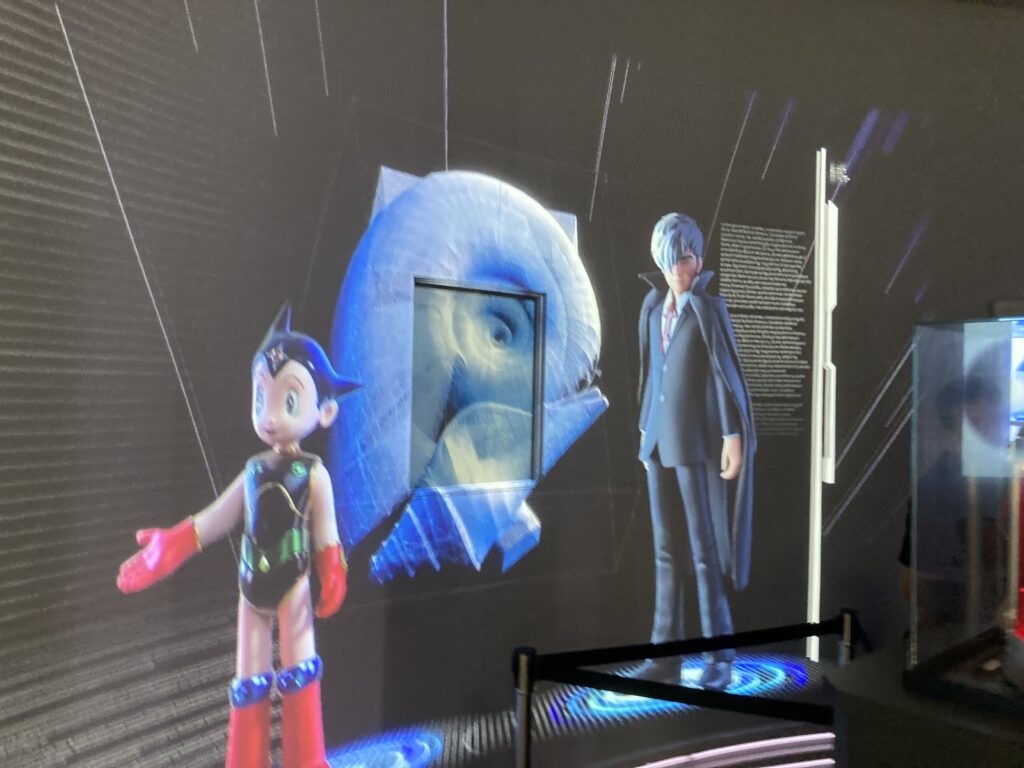

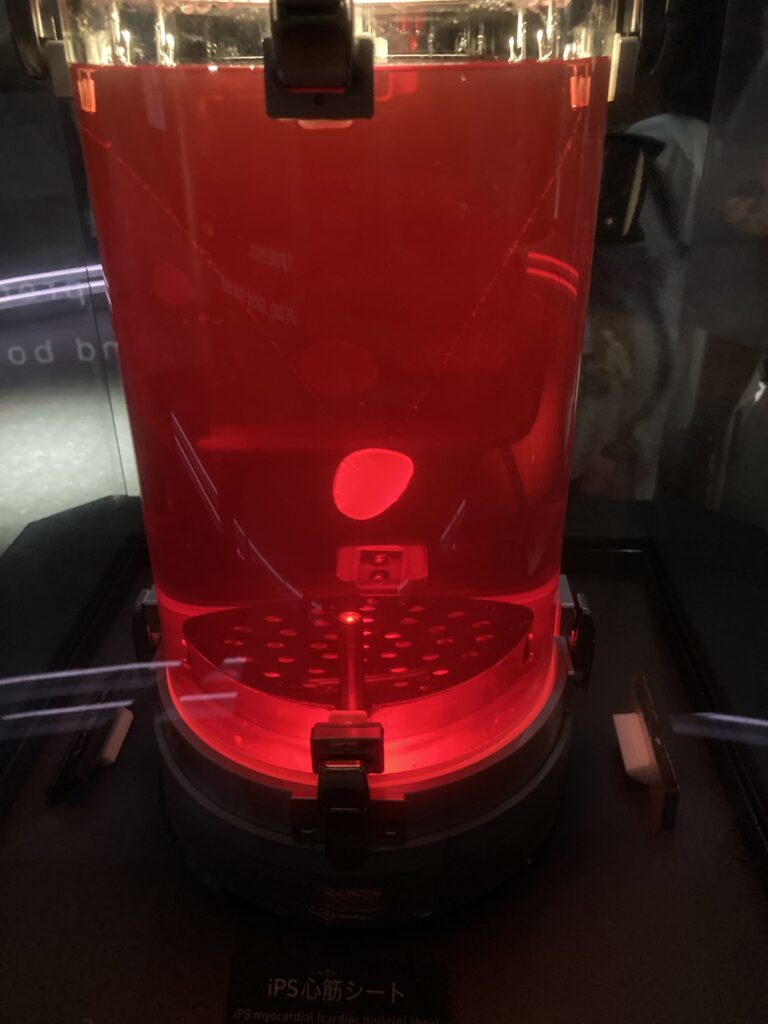
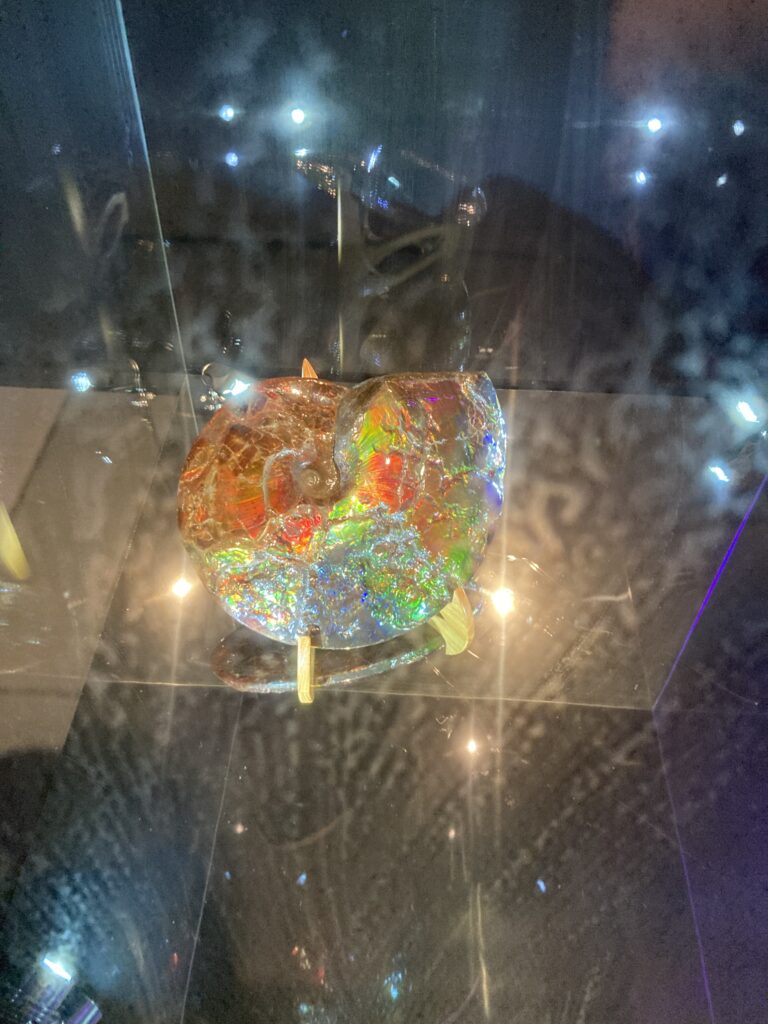



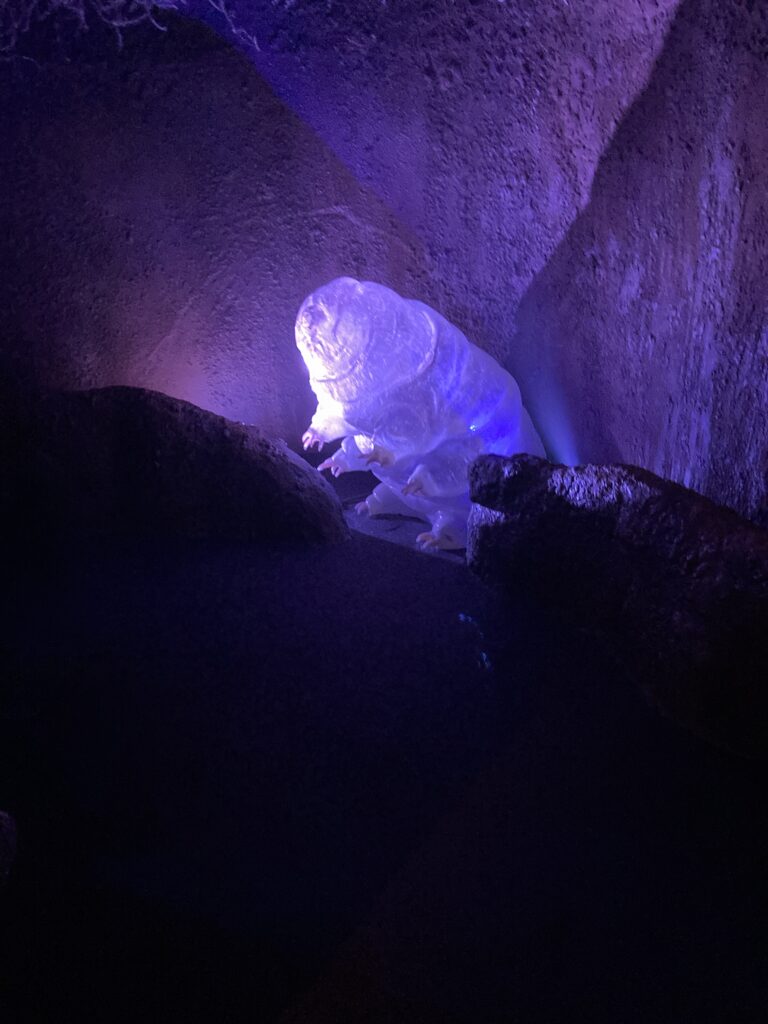



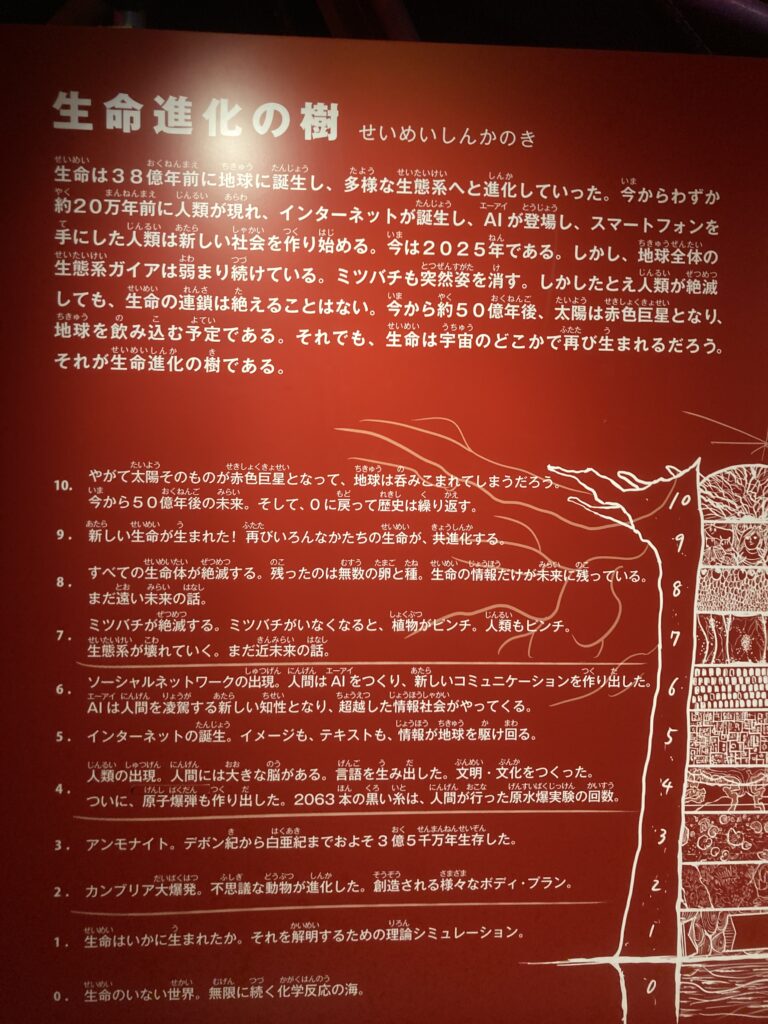

インド館──カオスの中の神性
続いて入ったインド館。
入口では象や女人像が出迎え、香辛料の香りが漂う。
中はまさにカオスだが、不思議と心地よい。
仏像、菩提樹、色彩と音楽。
それぞれが互いを主張しながらも、見事に調和している。
「混沌の中に秩序あり」。
この言葉がふさわしい空間だった。
インドネシア館──“頑張れば報われる”空間
次に訪れたインドネシア館は、今回もっとも好印象だった。
入口に入った瞬間、熱帯雨林の湿った空気と雨音が広がる。
床までがスクリーンになっており、森の中を歩くような錯覚を覚える。
スタッフの笑顔も印象的で、異国で迎え入れられるような温かさがあった。
このパビリオンは、SNSでの人気をきっかけに人が押し寄せるようになったという。
誠実に作り込めば、人の心に届く。
インドネシアが教えてくれたのは、そんなシンプルな真理だった。


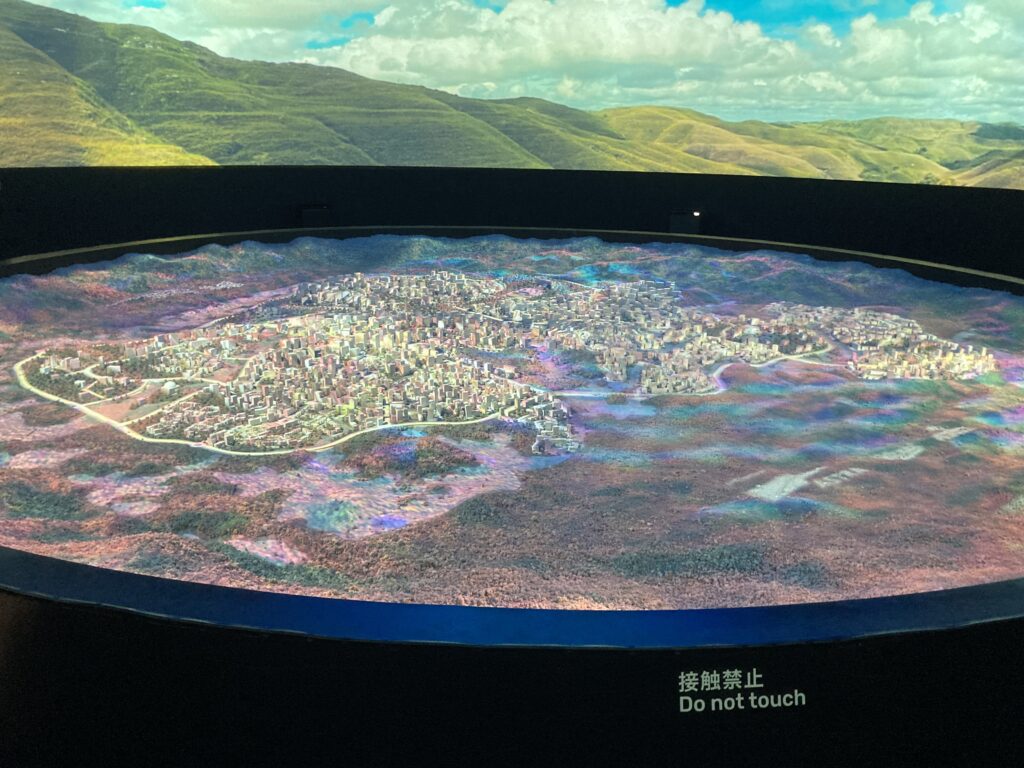
サウジアラビア館──美男美女とアラブの道
サウジアラビア館の入口には、まるでモデルのような男女スタッフが立っていた。
人々が思わず見とれるほどの美男美女。
中に入ると、吹き抜けの通りが砂漠の街を再現しており、まるで本物のサウジを歩いているようだった。
香料の香り、重厚な音楽、装飾の繊細さ。
**「これぞ万博」**というスケールの大きさだった。
商店街のように並ぶ展示ブースが、そのまま未来の都市構想を示していた。
ドイツ館──循環経済と“サーキュラーちゃん”
ドイツ館では、手のひらサイズの“サーキュラーちゃん”という球体端末を渡される。
展示を見ながら端末を当て、耳を近づけると音声が流れる仕組みだ。
テーマは「循環型社会」。
環境、素材、エネルギーといったテーマを真面目に掘り下げており、
ドイツらしい堅実さとユーモアのなさが、逆に信頼を感じさせた。
最後に天井を鏡で映す演出があり、
「循環とは、自分の心を映す鏡である」と締めくくられる。
ヒトラーとアインシュタイン——相反する二つの顔を持つ国らしさを感じた。



アラブ首長国連邦館──“砂の国”の多様性
アラブ首長国連邦館は、行列も少なくすぐ入れた。
アラブ風の衣装を着たスタッフが展示品の説明をしてくれるが、
中には日本語ができず英語で一生懸命伝える人もいて、そのぎこちなさが逆に温かかった。
砂漠の砂にも種類があることを初めて知り、
国ごとに色味や粒子が違うと聞いて驚いた。
展示ブースの中央には、巨大な柱が何本もそびえ立ち、
この国の“支柱”を象徴しているようだった。
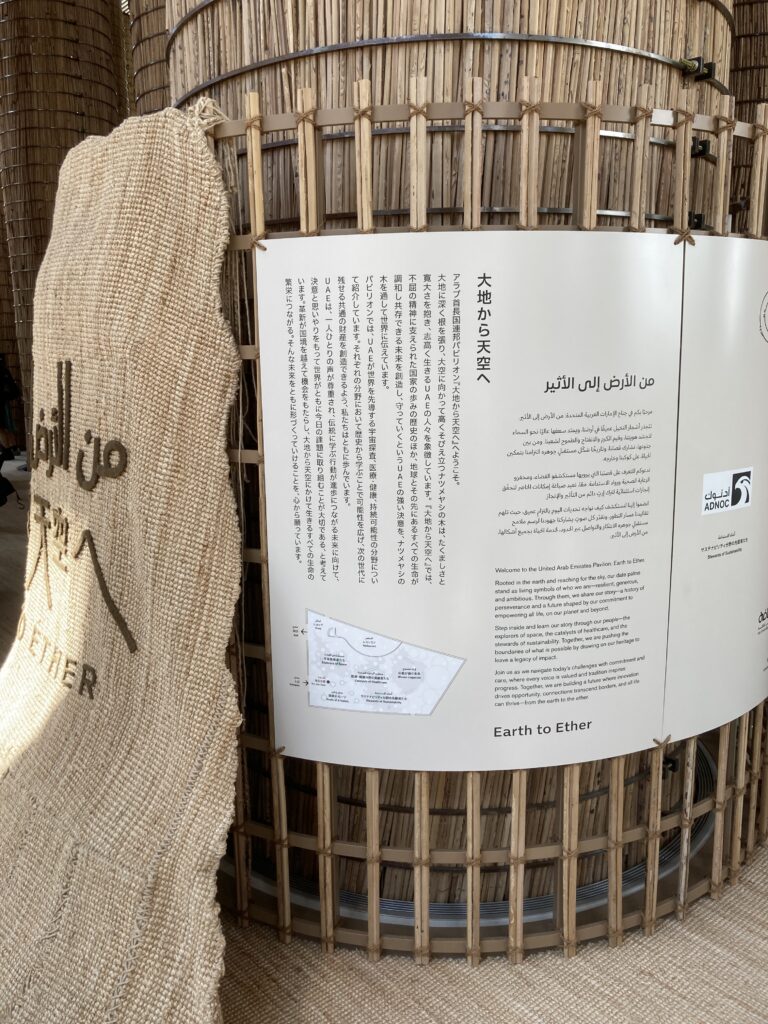

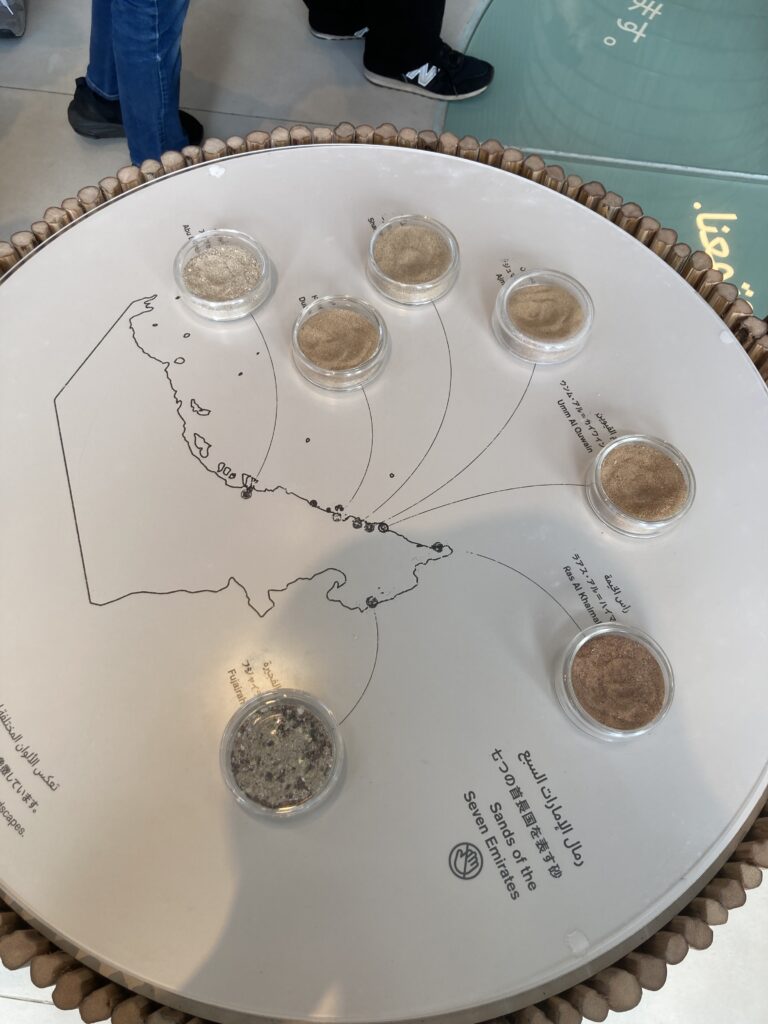


中国館──「背伸び」が美しい国
住友館まで少し時間があったので、
クウェート館と迷った末に中国館へ。
「待ち時間3時間」と書かれていたが、実際は50分程度。
入口の係員が誇らしげに「スリーアワー!」と叫ぶその“誇張”に、
中国らしい背伸びの美学を感じた。
中に入ると、巨大スクリーンに古代の絵画が映し出され、
春夏秋冬それぞれの人物がAIによって動いていた。
24節気を表す映像の美しさは圧巻で、
大陸的なスケールと細部への執念が同居している。
やや過剰な演出もあるが、それもまた中国。
「どんな時代でも、自国の歴史と誇りを演出する」——
その姿勢が、むしろ清々しく見えた。




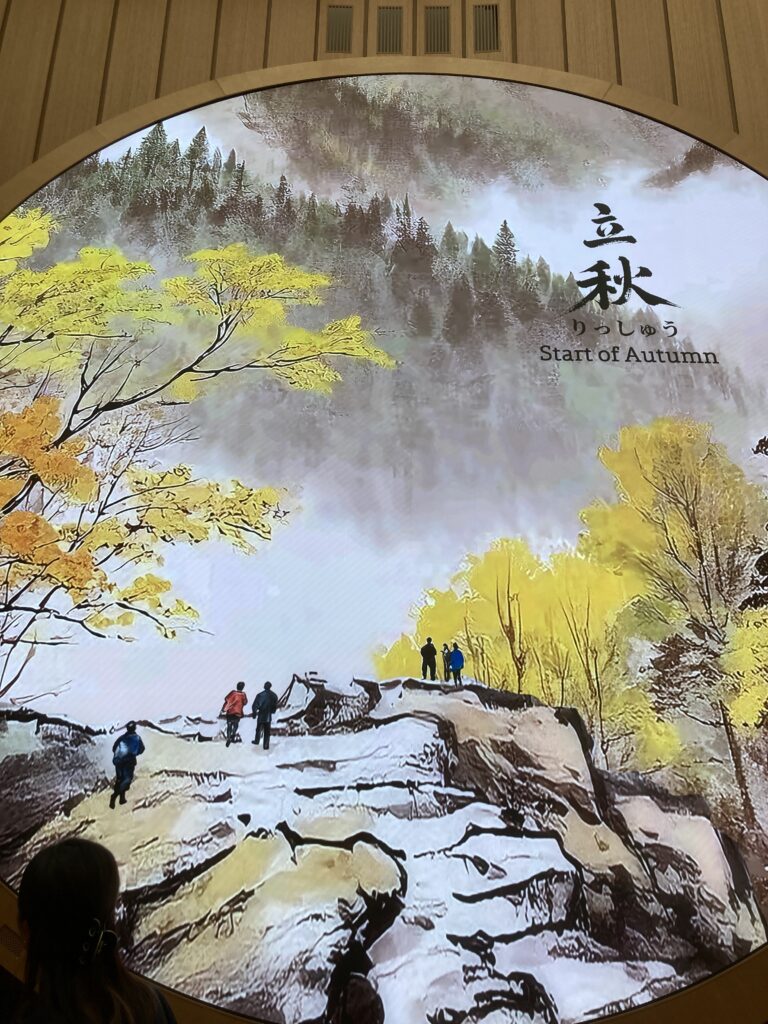
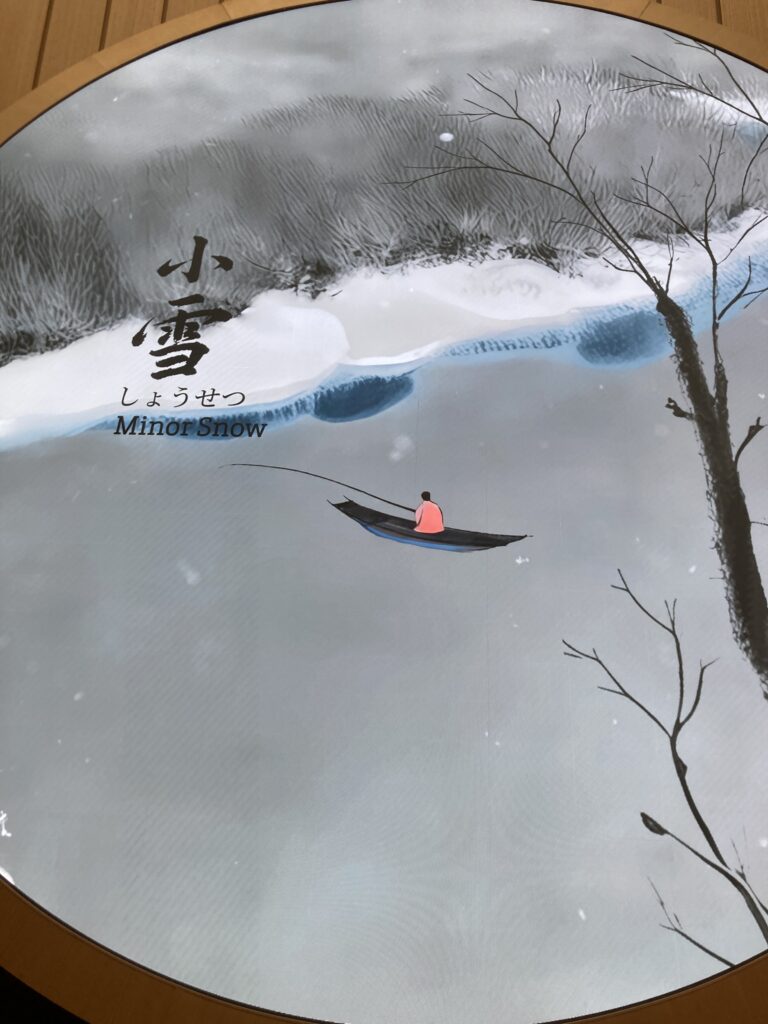
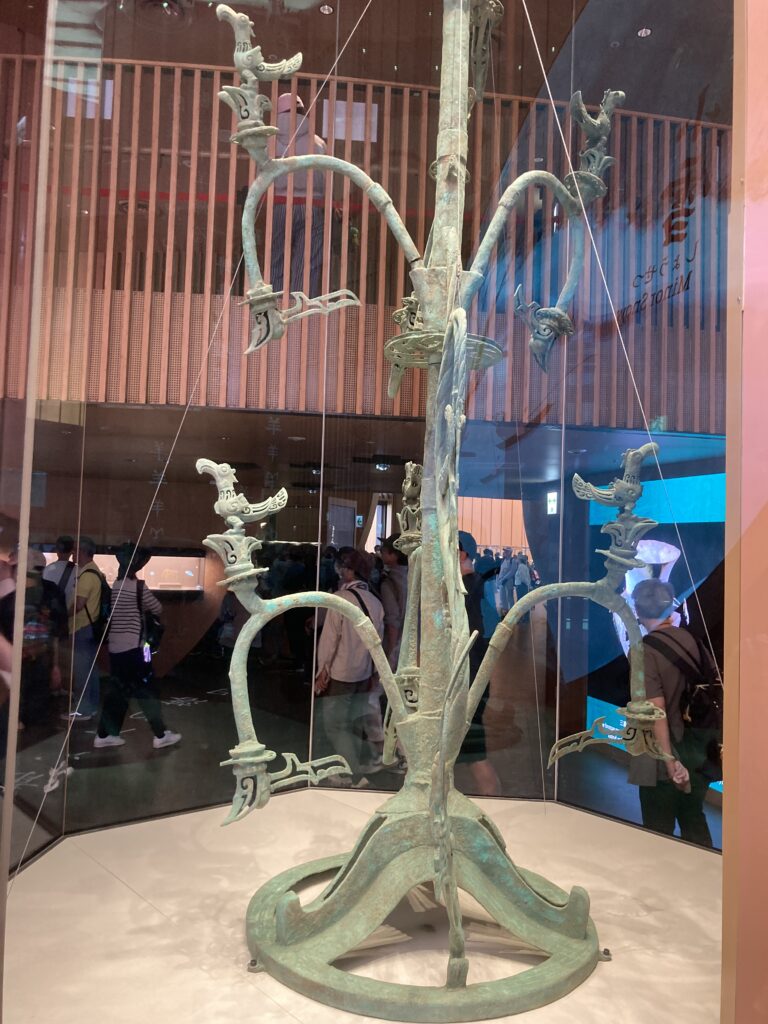
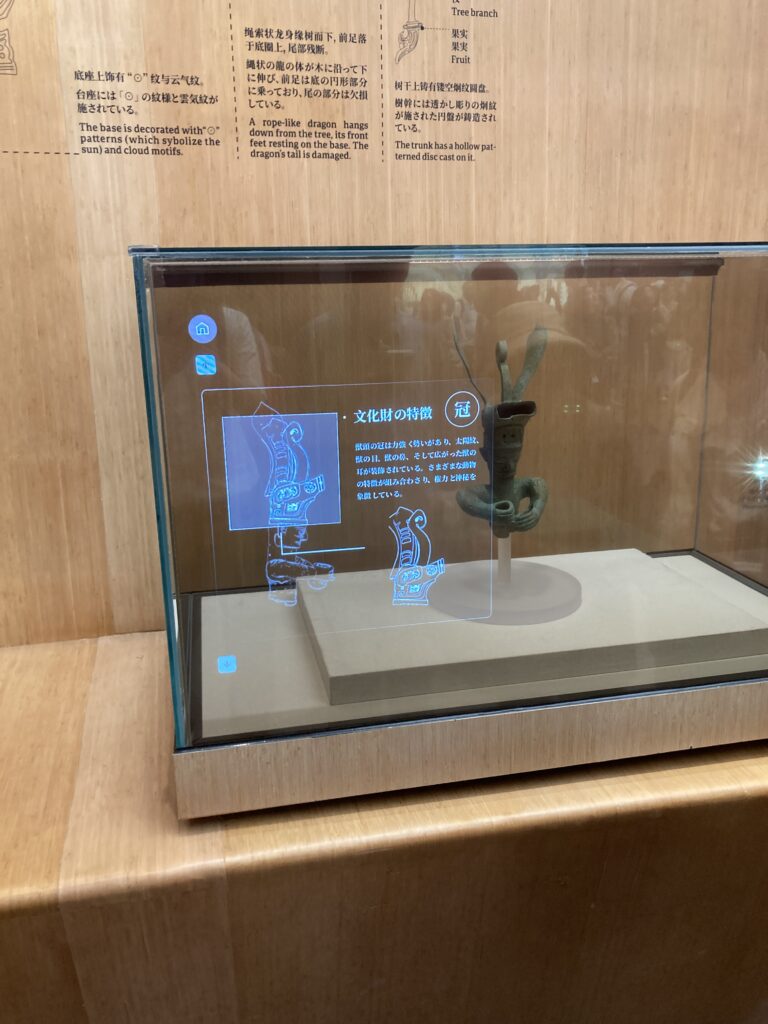










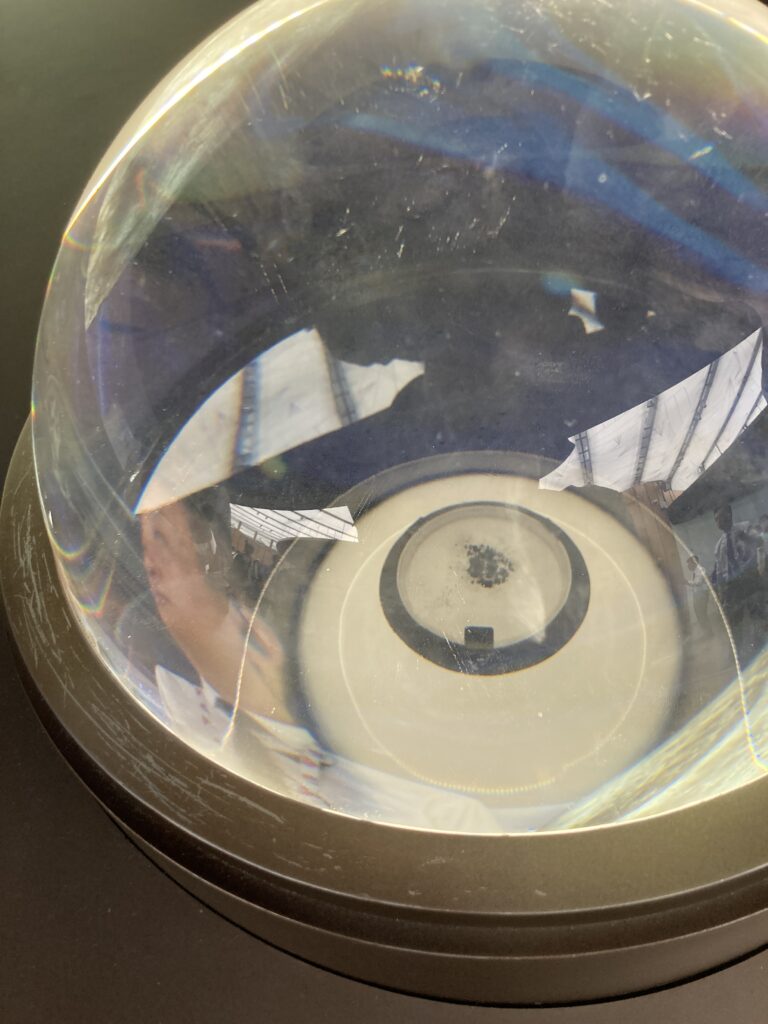
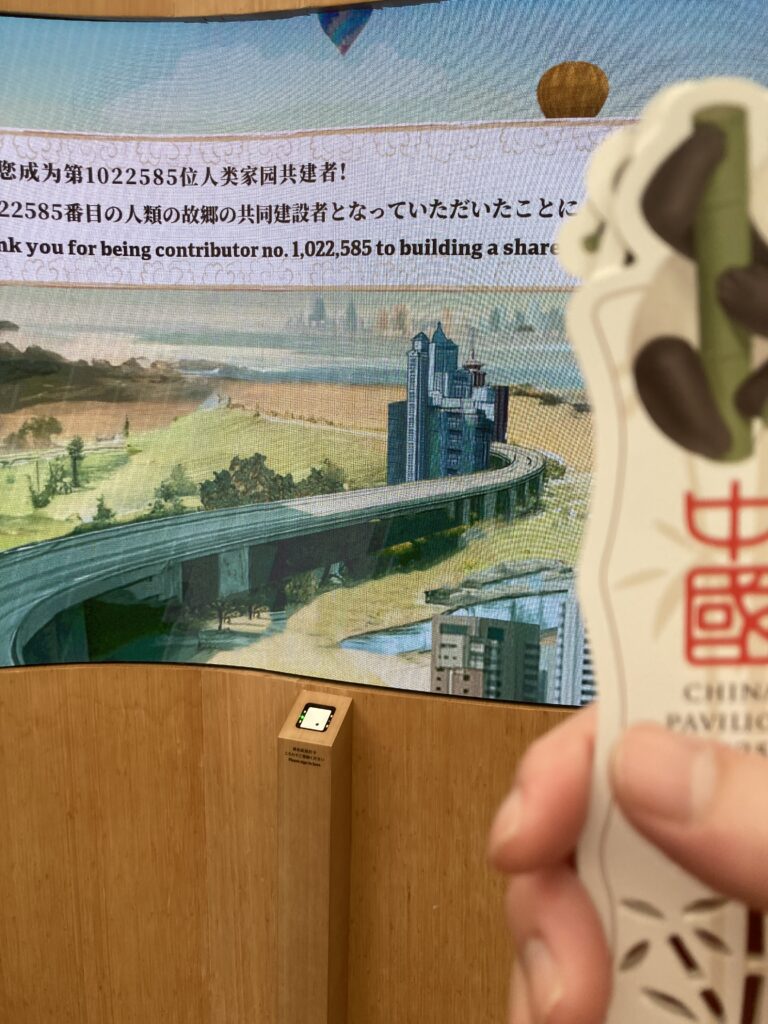

次回は、いよいよ本命の「住友館」から、
オランダ館、飯田グループ×大阪公立大学館、ガンダム、大阪ヘルスケアリボーン無し。そしてフランス館へと続く。
中秋の名月が輝く夜、大屋根リングで感じた“人の営みの美”を描く後編に続きます。





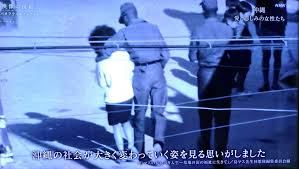



コメント